漢詩紹介
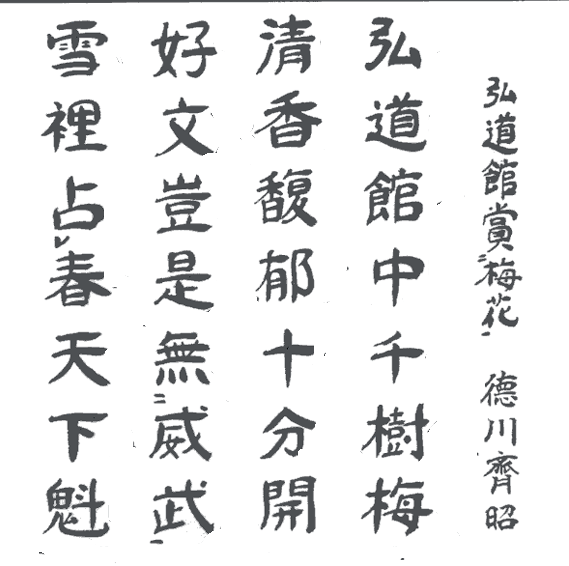
CD②収録 吟者:増田苑水
2015年3月掲載
読み方
- 弘道館に梅花を賞す <徳川 斉昭>
- 弘道館中 千樹の梅
- 清香馥郁 十分に開く
- 好文 豈是 威武無からんや
- 雪裡春を占む 天下の魁
- こうどうかんにばいかをしょうす <とくがわ なりあき>
- こうどうかんちゅう せんじゅのうめ
- せいこうふくいく じゅうぶんにひらく
- こうぶん あにこれ いぶなからんや
- せつりはるをしむ てんかのさきがけ
詩の意味
弘道館の中には千本もあろうかと思われる梅の木があり、いま満開に咲き誇り、清香を漂わせている。
(昔、晋の武帝が学問を好むと梅の花が咲き、学問をやめると咲かなくなった故事から梅の木を好文木と称するようになったというが)梅に武の威力がないといえようか。寒中の雪を冒して咲き、春の魁をなすのは、この花の他にあるまい。
語句の意味
-
- 弘道館
- 水戸の藩校 文武二館に分かれ城内の三の丸に在った 今はそのあたりは公園になっている
-
- 馥 郁
- 香気の盛んなさま
-
- 好 文
- 梅の異名で好文木という
-
- 威 武
- 勢いのたけだけしく強いこと
-
- 魁
- 他に先んじる
鑑賞
威武たる梅の精神は水戸藩の心
単なる観梅の詩ではなく、斉昭の教学の方針の象徴として植えた梅に対する感慨である。梅が寒風を破って春一番に可憐な花をつけて人の心を和ませる詩は、新島襄の「寒梅」を始めとして多々あるが、この詩はもう一段意味が深い。前半2句は千本の梅の清香を詠い、風雅で穏やかであるが、後半2句に斉昭らしさが見える。
一般に梅の印象としては、可憐とか馥郁という表現が似合うのであって、「威武」という物々しい言葉はあまり見かけない。しかし「よく見るがよい。梅は風雅でありながら、雪の中から誰よりも早く力強く咲き始める。これこそ威武と言えるのではないか」と詠う。視点が武人らしい。ここに文武両道を尊ぶ水戸学の象徴が表現されている。梅にも、さまざまな向き合い方がある。
参考
①「弘道館」の名の由来
「論語」の衛霊公編に次の章がある。
子曰く「人能弘道、非道弘人也」(人能く道を弘む、道人を弘むるに非ざるなり=人は正しい道を自らの力で押し広めることができる。決して何もしないで人の正しい道が自然に人を広めるのではない)
なお、幾棟もあった弘道館そのものは火災に遭い、現在では二、三の建物が当時の面影を残しているだけである。広大な庭は昔通りで、「偕楽園」として春は観梅の名所となっている
②同名の藩校が佐賀県、滋賀県に在る
佐賀県の場合、前身は1709年の学問所であるが、1839年に佐賀藩の城内に拡張改築され、主として身分別の武芸修行を目的とした。
滋賀県の場合は、彦根藩の藩校「稽古館」は11代藩主井伊直中が寛政11年(1799)に設立、その後12代藩主直亮(なおあき)は名称を弘道館に改めた。
詩の形
仄起こり七言絶句の形であって、上平声十灰(かい)韻の梅、開、魁の字が使われている。
| 結句 | 転句 | 承句 | 起句 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者
徳川斉昭 1800~1860
幕末の水戸藩主・思想家
江戸に生まれた。景山、潜龍閣と号した。文政12年(1829)、兄の斉脩(なりのぶ)の死に伴い、藤田東湖ら藩政改革派の推戴(すいたい)により藩主となった。海防強化、殖産興業、西洋式軍備、軍事学など藩政改革を進めた。また藩校弘道館を設立し、社寺の整備にもあたるが、その思想は尊皇攘夷論の先駆けをなし、安政の大獄に連座して蟄居(ちっきょ)を命ぜられる。万延元年没す。享年61。
