漢詩紹介
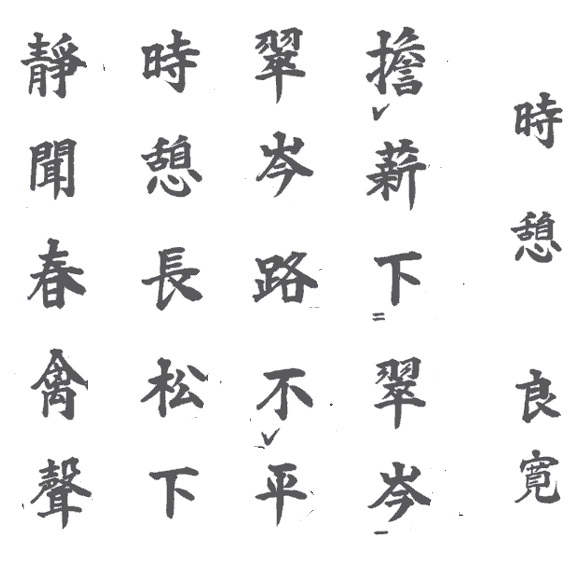
CD収録 吟者:松浦菖帑
2014年10月掲載
読み方
- 時に憩う <良 寛>
- 薪を担うて 翠岑を下る
- 翠岑 路は 平らかならず
- 時に憩う 長松の下
- 静かに聞く 春禽の声
- ときにいこう <りょう かん>
- たきぎをにのうて すいしんをくだる
- すいしん みちは たいらかならず
- ときにいこう ちょうしょうのもと
- しずかにきく しゅんきんのこえ
詩の意味
薪を背負って春の山路を下ってくる。美しいみどりの峰であるが、狭い路はやたら凸凹(でこぼこ)して平らかでない。
青空に聳え立つ松の下にたどりつき休んでいると、どこからともなく春を告げる鳥の声が聞こえ、疲れをなごませてくれる。耳を澄ますとあたりの静けさがひときわ深く感じられるのである。
語句の意味
-
- 担
- かつぐ 背負う
-
- 翠 岑
- 春の青々した峰
-
- 路
- 小規模な道 道は一般に大規模な道
-
- 長 松
- 丈の高い松
-
- 春 禽
- 春の鳥(鶯であろうか)
鑑賞
求め続けた脱俗の世界「五合庵」
関西吟詩には良寛の絶句が3首採用されている。「余生」「半夜」と「時憩」である。何れの詩も本山を持たぬ修行僧が全く俗世間と無縁な生活で、自然と一体となって暮らしていることに無上の喜びを感じている。この詩も五合庵での独居生活の一コマである。翠の峰・長松そして小鳥のさえずりが背景に在ってその中に静かな良寛がいる。素朴すぎる表現であるが、これが彼の日常である。そしてそれが永遠に続くことが悟りの世界に至ることができるというのだから奥が深い。最後は対句で緩慢になりがちな流れをひき締めている。
参考
五合庵
良寛が備前の国玉島から修行を終え、47歳から13年間(39歳から20年間の説あり)過ごした庵である。「五合庵」の名は、1684年ころから国上寺に身を寄せ、荒廃していたその寺を、時の住職を助けて再興に生涯をささげた万元上人にこの草庵と日に粗米五合を贈られたことから名づけられたといわれている。
五合庵 良寛
索々たる五合庵 室(しつ)は懸磬(けんけい)の如く然(しか)り
戸外には杉千株 壁上には偈(げ)数編
釜中(ふちゅう)時に塵有り 甑裏(しょうり)更に煙無し
唯東村の翁有り 時に敲(たた)く月下の門
(注)索々=風に吹かれてカサカサと音を立てている
懸磬=「磬」は石でできた薄い楽器 吊るして打ちならす
偈=仏の徳をたたえた絶句の形をした韻文
甑=土製のせいろう 蒸し器
詩の形
良寛の天衣無縫の性格の如く全く破格の詩である。平仄も度外視されている。
平起こり五言古詩の形であって、下平声八庚(こう)韻の平・声の字が使われている。転句・結句は対句になっている。
| 結句 | 転句 | 承句 | 起句 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者
良 寛 1758~1831
江戸時代後期の僧侶。
本姓は山本、幼名は栄蔵、字は曲(まがり)、出家して良寛または大愚と号した。越後(新潟県)出雲崎の人。家は代々神職と名主を兼ね、父泰雄は(越後俳壇で)以南と号した。良寛はその長子。成長して備中(岡山県)玉島(現倉敷市)の円通寺で国仙和尚に学び。後諸国を行脚して帰国し、国上山の五合庵に入り、40歳からここに住んだ。晩年には麓の乙子神社の庵に移り、天保2年1月、島崎の木村家(良寛庵)で貞心尼に看取られ没す。享年74。良寛は俳句・短歌・書の道にも通じていた。
