漢詩紹介
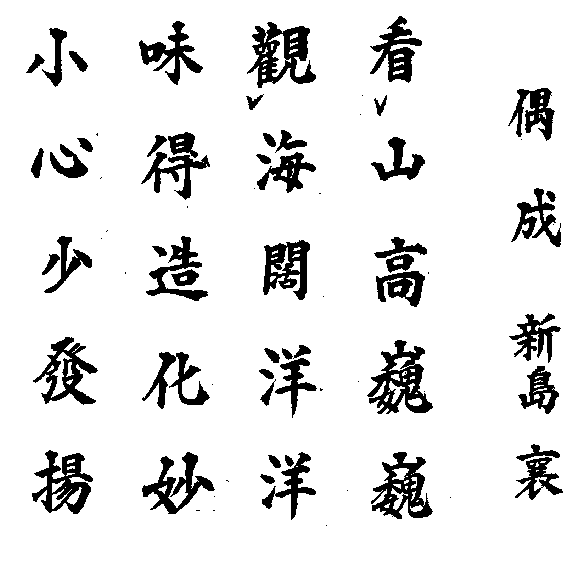
読み方
- 偶 成 <新島 襄>
- 山を看れば 高きこと巍巍たり
- 海を観れば 闊きこと洋洋たり
- 味わい得たり 造化の妙なるを
- 小心 少しく発揚す
- ぐうせい <にいじま じょう>
- やまをみれば たかきことぎぎたり
- うみをみれば ひろきことようようたり
- あじわいえたり ぞうかのみょうなるを
- しょうしん すこしくはつようす
詩の意味
山を見ると高く大きく、海を見れば果てしなく広々としてゆったりとしている。
この素晴らしい山や海をつくり出した自然の理の優れていることを感じると、こせこせした私の心も、山の如く大きく海の如く広い心を持たなければならない、と意気が上がるのである。
語句の意味
-
- 巍 巍
- 山が大きく高いさま
-
- 闊
- 広く雄大なさま
-
- 洋 洋
- ゆったりと のびのびしているさま
-
- 造 化
- 万物をつくり出した自然の理
-
- 妙
- たえ 優れている
-
- 発 揚
- 意気が上がる
鑑賞
ついに発意した壮大な計画、同志社大学創設
雄大な自然を眺めて感動し、造化の妙にまた感動する。これは新島襄に限ったことではないので、ある意味では素朴で、ありふれている。しかしわれわれは彼の活躍の軌跡を承知しているからかも知れないが、結句には啓蒙思想家としての強い志がにじみ出ている。欧州を見聞して明治7年に帰国した彼は天地が逆転したような明治維新に当たり、これからの日本は儒教でもなく仏教でもなくキリスト教が先導し、日本の津々浦々に「聖書」の教えを普及させたいと願った。控えめな表現であるが、意気の高揚がうかがえる。彼は決して小心者ではない。米国に密航したり、欧州まで赴いてその文化や思想を学ぼうとした事実がそれを証明している。彼は謙遜して自分を小心者と紹介しているだけである。実際彼は多くの知遇を得て果敢にも同志社設立の実現に向かったのである。
参考
その人柄を知る逸話
(その一)新島襄は下級武士の長男として生まれた。身分制度の枠の中で不平等がまかり通っている社会に疑問を抱いていた。後年ローマを訪れた時、法皇に拝謁する機会を得たが、慣例としてうやうやしく膝まづかなければならないことを知ると、「法皇様に対して、わたしの膝は固すぎるようです」と言って謁見を断念したという。
(その二)同志社を設立した彼は校長であるのだが、学生を含めて人を呼び捨てにしなかった。必ず姓の下に「さん」をつけて呼び、学生にも自分を「新島さん」と呼ばせたという。
詩の形
平起こり五言古詩の形であって、下平声七陽(よう)韻の洋・揚の字が使われている。起句・承句は対句になっている。
| 結句 | 転句 | 承句 | 起句 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者
新島 襄 1843~1890
江戸末期から明治時代の宗教家・教育者。
天保14年正月、上州(群馬県)安中藩(あんなかはん)の江戸一ツ橋邸で生まれた。父民治は藩の右筆(書記役)。幼児期から漢学を修め、蘭学は杉田玄白について学んだ。21歳の時聖書に触れて感激、翌年幕府の禁を犯して渡米し、神学・理学を学ぶ。明治4年、岩倉具視が大使として訪米した折には案内役として欧州にも赴いた。明治7年帰国後、キリスト教主義の学校を目指し、京都に同志社を開き、さらに大学にすべく奔走中病に倒れた。明治23年没す。享年48。
