漢詩紹介
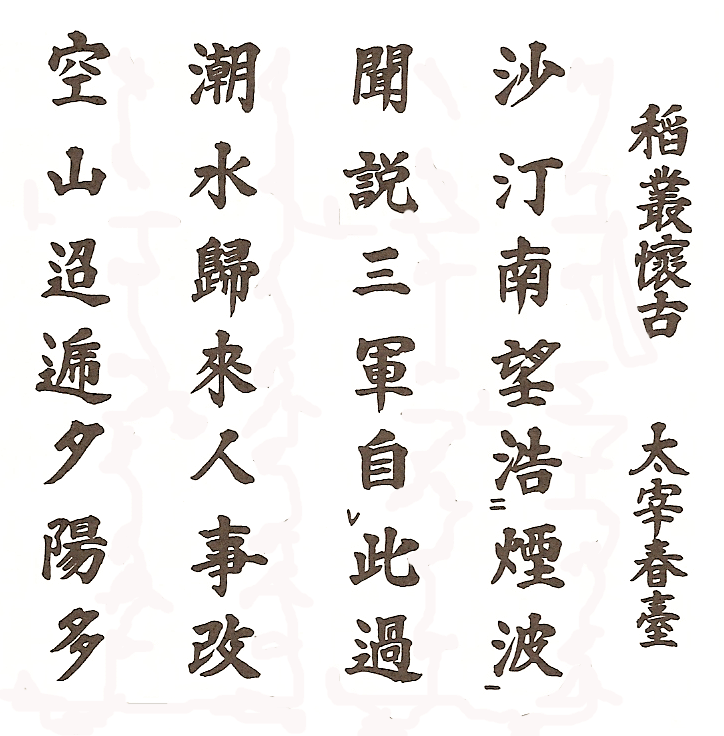
読み方
- 稲叢懐古 <太宰春台>
- 沙汀南望すれば 煙波浩たり
- 聞くならく三軍 此れ自り過ぐと
- 潮水帰来して 人事改まり
- 空山迢逓 夕陽多し
- いなむらかいこ <だざいしゅんだい>
- さていなんぼうすれば えんぱこうたり
- きくならくさんぐん これよりすぐと
- ちょうすいきらいして じんじあらたまり
- くうざんちょうてい せきようおおし
詩の意味
稲村ケ崎の砂浜遠く南を望めば、広々と靄(もや)が立ち込めている。聞くところによると、新田義貞(にったよしさだ)の大軍がここから干潟(ひがた)を渡り、鎌倉に攻め入り、北条高塒を亡ぼしたという。
いったん退いた海水も元に帰り、人の世の事も変わってしまい、今は敵味方もすべて跡かたもない。ただ人けのない山が遠く連なり、夕日がいっぱいに照らしている。
語句の意味
-
- 稲 叢
- 神奈川県鎌倉市の南部 「叢」は村に同じ
-
- 沙 汀
- 砂浜の波打ちぎわ
-
- 煙 波
- 霞とか靄のかかった波
-
- 聞 説
- 聞くところによると
-
- 三 軍
- 大軍 ここでは足利軍の配下の新田軍
-
- 迢 逓
- 遥遠くに隔たること
鑑賞
奇策の新田義貞の英雄譚も今は夢
この詩も時代背景をしっかり掴まなければならない。詩は元弘3年(1333)、所は鎌倉の稲村ケ崎。北方は険しい山に阻まれやむなく南の海から攻め入ることにした。奇跡に近く、大軍は鎌倉に侵入し、ついに目的を果たした。大将義貞の勇猛ぶりを懐古したものである。作者は稲村ケ浜を訪れ、ここが義貞の運命を決めた土地であることをしのびつつ、あれから300年、潮水は昔と変わらないのに、人の世は改まったと、しみじみと歴史を振り返りしばらくその場を離れられなかった詩人が目に浮かぶ。
備考
鎌倉幕府と新田義貞
元寇の役などで疲弊していた鎌倉幕府を打倒せよという命を足利尊氏から受けていたのは、関東に根拠地を持ち、尊氏と家系を同じくする新田義貞であった。彼は利根川を渡り鎌倉に迫っていたが、鎌倉は天然の要塞としての山々を得て、三方は完全に防備ができていて侵入できない。そこで義貞軍は南に回り、稲村ケ崎から海を通って鎌倉に乱入しょうと計画した。この時、当地の海は馬も通れない潮であった。そこで、義貞は黄金の太刀を海神に献じ「願わくは潮も万里の外に退け、三軍の途を開かせたまえ」と祈った。するとその夜、月の入り方には潮は干上がり大軍を通すことができた。北条高時は攻められ、一族とともに自刃し、北条氏(鎌倉幕府)は滅亡したのである。(1333年)(参考=太平記)
尊氏を援護する義貞の功績はこのようでありながら、のち尊氏と確執し、越前(福井県)にのがれたが、最後は尊氏軍によって包囲され自殺した。(1338年)
参考
この英雄ぶりを歌った文部省唱歌「鎌倉」(一・二番のみ)
七里ヶ浜の磯伝い
稲村ヶ崎 名将の
剣(つるぎ)投ぜし古戦場
極楽坂(ごくらくざか) 超(こ)え行(ゆ)けば
長谷観音(はせかんのん)の堂(どう)近(ちか)く
露座(ろざ)の大仏おわします
詩の形
平起こり七言絶句の形であって、下平声五歌(か)韻の波・過・多の字が使われている。
| 結句 | 転句 | 承句 | 起句 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者
太宰春台 1680~1747
江戸中期の儒者。
名は純(あつし)、字は徳夫(とくふ)、幼名は千之助、通称弥右衛門、春台または紫芝園(ししえん)と号した。もと平手姓であったが父の代に太宰謙翁の養嗣子となり太宰家を継ぐ。主に従って下野(=しもつけ 千葉県)より信州(長野県)飯田に移る。のち出石(いずし)候(兵庫県北部)に仕え、また森川出羽守にも仕えたが、36歳以後自由の身となり専(もっぱ)ら文筆を事とする。たまたま赤穂浪士復讐の件起こるや、師の荻生徂徠(おぎゅうそらい)とともに幕府同情無罰論に反して浪士の処刑を主張したように、情を捨て理をとる理論家であったが、詩は流麗であった。多くの著書がある。享年67。
