漢詩紹介
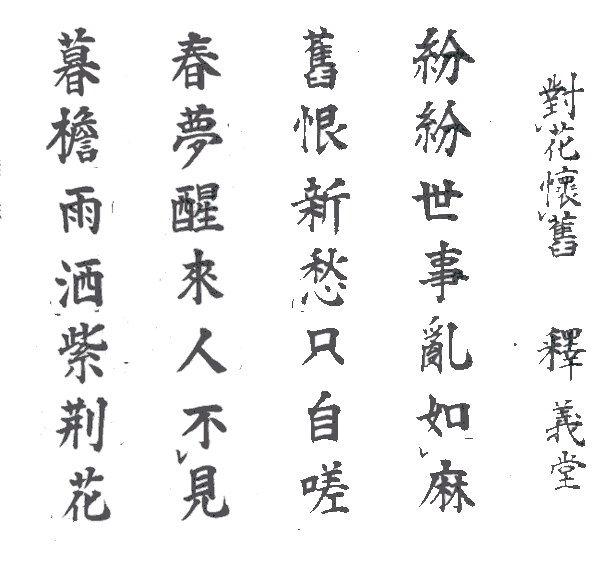
読み方
- 花に対して旧を懐う <釈 義堂>
- 紛紛たる世事 乱れて麻の如し
- 旧恨新愁 只自ら嗟く
- 春夢醒め来たって 人見えず
- 暮檐 雨は洒ぐ 紫荊の花
- はなにたいしてきゅうをおもう <しゃく ぎどう>
- ふんぷんたるせじ みだれてあさのごとし
- きゅうこんしんしゅう ただみずからなげく
- しゅんむさめきたって ひとみえず
- ぼえん あめはそそぐ しけいのはな
詩の意味
煩わしく取り乱れている世の中はまるで麻糸のもつれたようである。亡くなった知人に対する辛く口惜しい思いや新しい愁い事で私の心はただ嘆くばかりである。
春のうたた寝から醒めてみれば、今夢の中で見た人はもう見えず、夕暮れの軒端に雨が降り注いで紫荊の花を濡らしているのである。
語句の意味
-
- 懐 旧
- 昔のことを思う
-
- 紛 紛
- 煩わしいさま
-
- 旧 恨
- 亡くなった知人に対する辛く口惜しい思い
-
- 暮 檐
- 夕暮れの軒端
-
- 紫荊花
- 花蘇芳(はなずおう) 兄弟が仲良くする故事を持つ花
鑑賞
南北朝の戦乱で戦死した人々に捧げる詩
南北朝時代(1338~1392)は足利氏の北朝対後醍醐天皇系朝廷の南朝が張り合った約60年間をいう。作者11歳の時、楠正成が湊川で自刃し、23歳の時は正行が四条畷で自害した。この南北朝時代の最大の戦いは作者25歳の時起こった「観応の擾乱(じょうらん)」である。この乱は北朝内部で兄尊氏と弟の直義が対立し、さらに南朝方も加わった三つ巴の戦いであった。おそらく多くの犠牲者が出たことであろう。この詩の成立年代は明らかでないが、この乱の中に作者の知人が幾人もいたと考えられる。醜い欲望の渦に巻き込まれた知人たちへの悲痛な思いが歌となった。もういい加減に殺し合いに終止符を打ったらどうなのか、と仏門に身を置くものとしての切なる思いがうかがえる。その思いは結句の「紫荊の花」の3文字に込められている。最後に引き締まった格調ある詩である。
備考
紫荊花について
中国原産のマメ科の落葉小高木で庭木として栽培する。荊(いばら)だが枝にとげはなく、葉は心臓型で、4月ごろ紅紫の蝶の形をした花をつける。実はこの花には珍しい秘話がある。「続斎諧記」からあらすじを紹介する。
都に住む田真(でんしん)兄弟3人が父の遺産を分割しようとした。分割可能なものはみな平等に分けたが、家の前の紫荊樹も3等分しようとして、翌日に実行することにした。その話を聞いた紫荊樹はたちまち枯れて、炎のような様相になっていた。みんな驚いた。兄が弟たちに言った。「木の株は1つのものなのに切り分けようとして枯れたのだ。3人が分け前ばかり考えていることはこの木にも劣る。自分たちは己の心を抑えきれず、木のことに思いが至らなかった。」と。木はこの言葉を聞いてもとのように茂り始めた。兄弟は父の財産をひとまとめにして共有することにした。その後、この3人の家は親孝行者の家柄と称えられるようになり、3人ともそれぞれに出世した。(大漢和辞典)
つまりこの言葉は、兄弟が仲よくすれば家は栄えることを教えている。足利兄弟に聞かせてやりたかっただろう。
詩の形
平起こり七言絶句の形であって、下平声六麻(ま)韻の麻・嗟・花の字が使われている。
| 結句 | 転句 | 承句 | 起句 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者
釈 義堂 1325~1388
南北朝時代の高僧。
姓は平氏、名は周信(ちかのぶ)、字は義堂、号は空華道人(くうげどうじん)。土佐高岡郡の人。正中2年正月に生まれる。14歳で剃髪、比叡山の道円阿闍梨(どうえんあじゃり)・京の夢窓国師(むそうこくし)・建仁寺(けんにんじ)の竜山徳見(りゅうざんとくけん)などに学ぶ。鎌倉報恩寺の第1世となり、さらに建仁寺・南禅寺に住み、慈氏院(じしいん)に退休(たいきゅう)する。嘉慶(かけい)2年に病にかかり、摂津の有馬温泉に浴した時、後光厳(ごこうげん)天皇から安否を問われ、天恩を謝す。同年4月3日、衆に生死の始末を説き、翌4日端座(たんざ)したまま示寂(しじゃく)したという。享年64。漢詩文集「空華集」20巻、その他がある。
