漢詩紹介
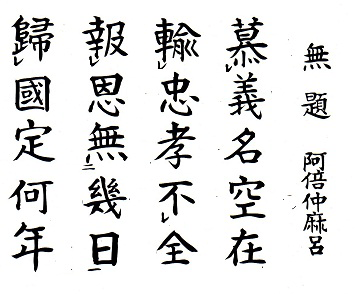
読み方
- 無 題 <阿部 仲麻呂>
- 義を慕う 名 空しく在り
- 忠を輸すも 孝 全からず
- 恩に報ゆるに 幾日も無し
- 国に帰るは 定めて何れの年ぞ
- むだい <あべの なかまろ>
- ぎをしとオ な むなしくあり
- ちゅうをいたすも こう まったからず
- おんにむくゆるに いくにちもなし
- くににかえるは さだめていずれのとしぞ
詩の意味
人のふみ行うべき道を求めて励んできたが、空しい名声だけがあるばかり。日本を離れ、唐の国に来ているのは、祖国に忠を尽くすことにはなるが、親に孝を尽くすことはできない。
この先、恩に報いたくても老いてきた今、もうあと何日もなくなってしまった。果たして日本へ帰国できるのはいつであろうか。
語句の意味
-
- 義
- 人としてふみ行うべき道
-
- 輸
- 真心を持って人に尽くす
-
- 定
- いったい 果たして
鑑賞
孝養を果たせず無念の客死
この詩は作者が帰国を試みた40歳前のころか、船団遭難後、奇跡的に長安に帰り、再び政府要人として活躍し、当地で客死する60歳代後半のものかは定かではない。いずれであっても日本人の心を打つ名詩である。当時の遣唐使たちは留学生も含めて、その思うところは唐文化を輸入し、日本の未来を拓く先駆者となり、併せて帰国の暁には高位高官を得て、よい意味で名を馳(は)せたいと思ったに違いない。
しかしこの詩を見るとそれだけではない。いかなる時も人として基本である親に孝を尽くすことを忘れては人間ではないという思想に改めて感動する。そういう作者だから、ついに祖国の土を踏めないとわかった時、断腸の思いで涙したことだろう。「何れの日にか帰年ならん」(絶句二)と歌った杜甫もやはり、故国に帰ることができなかった。両人とも無念なりとしか言いようがない。
備考
王維が仲麻呂に贈った送別の古詩
積水(せきすい)極むべからず 安(いずく)んぞ知らん滄海(そうかい)の東
九州何(いず)れの処か遠からん 万里空(くう)に乗るがごとし
国に向かって惟(た)だ日を看(み) 帰帆但(た)だ風に信(まか)すのみ
鰲身(ごうしん)天に映じて黒く 魚眼(ぎょがん)波を射(い)て紅(くれない)なり
郷樹扶桑の外(ほか) 主人孤島の中(うち)
別離方(まさ)に異域(いいき) 音信若為(いかん)してか通ぜん
参考
遣唐使について
日本から唐に派遣された外交使節。630年(飛鳥時代)から894年(平安中期)までの約260年間で19回にわたった。目的は唐の先進文物(ぶんぶつ)、制度を輸入することと、日本が蝦夷(えぞ)や新羅(しらぎ)国などより上位の国であることを示すためであった。8世紀には4隻に、大使を先頭に副使、判官、錄事の4等官のほか留学生、通訳、医師、兵士、占い師、操縦士、船大工、料理人、雑役、こぎ手などを含めて500人が乗船した。航路は難波津(なにわづ)の港から瀬戸内海、博多を経て、初期は朝鮮半島沿いを北上したが、8世紀には東シナ海を横断し、蘇州に上陸するコースをとった。いずれにしても遭難する船が続出し、まさに命がけの航海であった。唐に滞在中は唐側がその経費を負担した。新羅との国交断絶や唐帝国の哀退を背景に意義が薄れ、菅原道真の建議により廃絶した。
詩の形
仄起こり五言絶句の形であって、下平声一先(せん)韻の全、年の字が使われている。
| 結句 | 転句 | 承句 | 起句 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者
阿倍仲麻呂 698? 701?~770
奈良時代の遺唐留学生
霊亀(れいき)2年(716)16歳?で選ばれて翌、養老元年、吉備真備(きびのまきび)らとともに唐に留学。名を朝衡(ちょうこう)または晁衡(ちょうこう)と改め、玄宗皇帝に仕えた。科挙に合格し進士となり諸官を歴任した。博学多才。皇帝に寵遇(ちょうぐう)され、李白、王維など著名文人と交際し文名があった。のち海難に帰国を阻まれて果たさず在唐50余年。その間、節度使として安南(今のベトナム)に赴き治績をあげた。従三品の高位に昇り、宝亀元年(唐の大暦5年)唐で没す。享年69?。
