漢詩紹介
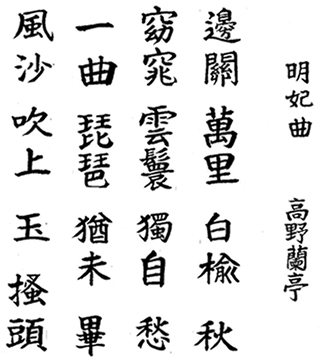
読み方
- 明妃の曲 <高野 蘭亭>
- 辺関万里 白楡の秋
- 窈窕たる雲鬟 独り自ら愁う
- 一曲の琵琶 猶未だ畢らず
- 風沙吹き上る 玉搔頭
- めいひのきょく <たかの らんてい>
- へんかんばんり はくゆのあき
- ようちょうたるうんかん ひとりみずからうれう
- いっきょくのびわ なおいまだおわらず
- ふうさふきのぼる ぎょくそうとう
詩の意味
万里も隔たった匈奴の辺塞の地で、白い楡(にれ)の木が落葉する秋、奥ゆかしく美しく、そして豊かな髪をした明妃は、一人で愁いに沈んでいる。
この悲しみを琵琶の一曲を弾いて慰めようとするが、それをまだ弾き終わらないうちに風沙(ふうさ)が吹きあがって、美しい玉の簪(かんざし)を汚すのである。
語句の意味
-
- 明 妃
- 王昭君
-
- 辺 関
- 辺塞の関所
-
- 白 楡
- 白いニレの木
-
- 窈 窕
- 奥ゆかしく美しい
-
- 雲 鬟
- 雲のように豊かな美しい髪 「鬟」は束ねて丸くした髪形
-
- 風 沙
- 風に舞う砂漠の砂
-
- 玉搔頭
- 玉の簪
鑑賞
永遠の悲劇のヒロイン 王昭君
この詩は前漢の10代皇帝元帝(紀元前30年ころ)の宮女である明妃つまり王昭君が匈奴の王による屈辱的な要求のため、側室とならざるを得なかった、憐れむべき境遇を、作者が追慕(ついぼ)したものである。
日本の高野蘭亭がモンゴルに行ったわけではないから、すべて想像の詩である。ニレの木は確かに寒地に生育する木であるが、はたして当地に在ったのか、紀元前にすでに琵琶が中国に伝来していたのか、モンゴルは草原地帯と聞いているが砂漠の国だったのか、などなど腑(ふ)に落ちない語句もあるが、作者は精いっぱい北方匈奴を描こうとしているので、十分にその気持ちは通じる。
それはさておき、この詩の主題である「憐れむべき昭君」の境遇を作者とともに共感したい。「悲劇のヒロイン王昭君」とは多くの書籍の評語(ひょうご)となっている。結句の「砂漠の砂が吹きあがって美しい簪を汚す」がいい。広大な匈奴と、憂いに沈む一人の美しい女性が対照的に表現され、昭君を眼前に見るようである。
備考
昭君の匈奴送りには2説ある
王昭君の生没年は不詳であるが、もう少し調べてみる。
「漢書(かんじょ)」には「匈奴の王・単于(ぜんう)との間に1男を、次帝とには2人の娘をもうけた」とある。「後漢書」には「良家の娘として後宮(こうきゅう)にいたが、元帝のお手付きがなかった。単于が来朝した時、和睦のため5人の宮女を与える約束をした。元帝に悲怨(ひえん)を募(つの)らせていた昭君は自ら工作して単于に嫁ぐことを希望した」とある。また「西京雑記」という本には「匈奴の頼みを約束した元帝は奥御殿の女官たちの肖像画を画家に描かせ、もっとも醜い女官を選んで贈ることにした。他の女官は画家に賄賂を贈って美しく描かせ、賄賂を贈らなかった昭君はもっとも醜く描かれ、匈奴行きに選ばれた。送別の宴で元帝が昭君に会ってみると、宮廷一の美女であった。昭君は泣く泣く匈奴に送られ、画家は処刑された」とある。
いずれにしても真偽は定かでないが、昭君は悲運の人であったことは想像に難くない。
詩の形
平起こり七言絶句の形であって、下平声十一尤(ゆう)韻の秋、愁、頭の字が使われている。
| 結句 | 転句 | 承句 | 起句 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者
高野蘭亭 1704~1757
江戸時代中期の儒者
江戸に生まれる。名は惟馨(いけい)、字は子式(ししき)、蘭亭または東里と号す。荻生徂徠の門にはいり、学識抜群であったが、17歳の時に失明した。徂徠の助言によって漢詩の道に志し、ついに服部南郭と互角の名声を得た。七言律詩を得意とした。生前自己の詩集の発行を許さなかったが、没後門人らが編集した「蘭亭先生遺稿」10巻がある。晩年鎌倉円覚寺のそばに庵を作り死所としたが、宝暦7年江戸において没す。詩作は万首に及ぶ。享年54。
