漢詩紹介
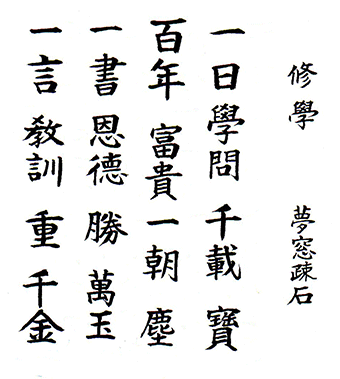
読み方
- 修学 <夢窓 疎石>
- 一日の学問 千載の宝
- 百年の富貴 一朝の塵
- 一書の恩徳 万玉に勝る
- 一言の教訓 重きこと千金
- しゅうがく <むそう そせき>
- いちにちのがくもん せんざいのたから
- ひゃくねんのふうき いっちょうのちり
- いっしょのおんとく ばんぎょくにまさる
- いちごんのきょうくん おもきことせんきん
詩の意味
わずか一日の浅い学問であっても自分の身につけば、永遠に宝となって残るが、逆に百年もの年月を経て蓄えられた財産や身分でも、おろそかな心があれば、わずかの間にあとかたもなく消えうせる。
意義ある1冊の書物から受ける恩徳というものは、多くの宝玉よりも貴重なものであり、師の一言の教訓は、千金の重さに値する。
語句の意味
-
- 千 載
- 千年 永遠 「載」は歳
-
- 富 貴
- 金持ちで身分地位が高い
-
- 一 朝
- わずかな間 一時
-
- 一 書
- 1冊の本
-
- 恩 徳
- 恵み 情け
-
- 万 玉
- 多くの宝
-
- 千 金
- 非常に高価
鑑賞
公武から尊崇された偉大な禅僧・夢窓疎石
この詩は学問・知識の大切さ、貴重さについて、自らの体験から述べたものである。作詩の時代は不明。1、2句は今でも通ずる修学上の掟のようなもの。邪念に捉われ現(うつつ)をぬかすと学問は成就しないという戒(いまし)めは古今数多くある。いずれも貴重な教えとなっている。
さて、一書・一言が気になる。どんな本のどんな言葉が大切なのか。臨済宗だから日本での開祖者・栄西(えいさい)の著した「興禅護国論」か「喫茶養生記」か。まさか「論語」や「孟子」ではなかろう。一言とは疎石の師である中国から来日の一山一寧師か、日本人の高峰顕日師の言葉かもしれない。しかし何も特定する必要はなく、一般論として、書物の大切さや師の教えの貴重さを感じれば、この詩は生きてくる。
参考
天竜寺建立のいきさつ
南北朝時代の初期、疎石が味方していた後醍醐天皇は吉野に追われ、天下は足利氏のものとなった。尊氏の追及を覚悟していた疎石を、逆に尊氏は師弟の礼を以て迎えたのであった。1339年に後醍醐天皇が崩御すると疎石は「雲よりも高き所に出でてみよ なにとて月をへだてやはする」の歌を詠み、天皇の業績を咎(とが)めるばかりでなく、大きな心で寛容に天皇を菩提(ぼだい)するよう尊氏に勧めた。これにより尊氏が後醍醐天皇のために建立したのが天竜寺である。方丈の前の石庭は疎石の作と伝えられている。
備考
結句は「一言の教訓千金より重し」と読んだ方が対句となって口調もよく、教訓詩らしく引き締まるが、本会では採らない。
詩の形
平仄・押韻が整っていないし、一字重出もあるので、七言古詩の形であって、平仄は問わない。
| 結句 | 転句 | 承句 | 起句 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者
夢窓疎石 1275~1351
鎌倉末期・南北朝時代の禅僧(臨済宗)
伊勢(三重県)の人。姓は源、号は夢窓。禅宗歴代の高僧の中でも並外れた傑物で、実力者だった。後醍醐天皇に召されて、2度南禅寺に入り、足利尊氏の天竜寺建立に開祖として迎えられた。また、後醍醐、・光厳・光明の3天皇から国師号を賜った。造園技術にも優れ、西芳寺(さいほうじ=苔寺)、天竜寺、瑞泉寺等の作庭にも偉才を見せた。享年76。
