漢詩紹介
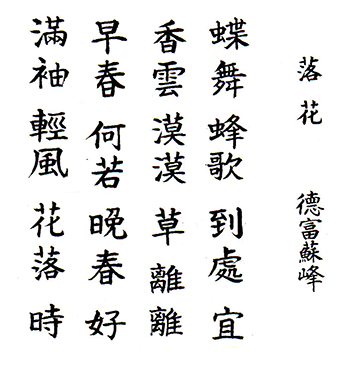
読み方
- 落花 <徳富 蘇峰>
- 蝶は舞い 蜂は歌う 到る処宜し
- 香雲漠漠たり 草離離たり
- 早春何ぞ若かん 晩春の好きに
- 満袖の軽風 花落つるの時
- らっか <とくとみ そほう>
- ちょうはまい はちはうとオ いたるところよろし
- こううんばくばくたり くさりりたり
- そうしゅんなんぞしかん ばんしゅんのよきに
- まんしゅうのけいふう はなおつるのとき
詩の意味
蝶が舞っているように飛び交い、蜂は歌っているように飛んで、どこへ行ってもよい光景である。桜の花が群がって咲き、草も青々とずっと並び連なっている。
春の初めは春の終わりの景にどうして及ぶだろうか。到底及ばないだろう。袖いっぱいに軽やかな風を受けて花の散る情景はすばらしい。
語句の意味
-
- 香 雲
- 群がり咲く桜
-
- 漠 漠
- 一面に広がるさま
-
- 離 離
- 草が並び連なる姿
-
- 何 若
- どうして……に及ぶだろうか(いや到底及ばない)
-
- 満 袖
- 袖いっぱい
鑑賞
昭和の論客が落花を詠う
蘇峰と言えば昭和の大評論家であり論客である。鋭い風刺の利いた詩を期待する人も多いだろうが、この詩は何と穏やかなことか。落花に寄せて晩春の良さを詠じている。新島襄の「寒梅」に代表されるように、早春の喜びを詠うものは多いが、福沢諭吉の「花を惜しむ」のように晩春にも風情(ふぜい)があるという詩もある。この詩では晩春は早春に勝るものがあると述べているが、こういう情緒(じょうちょ)に関することは、その優劣を争うものではない。
昭和初期の蘇峰といえば、世界大戦を前にして東京で大評論活動を行っていた。「国民新聞」は次第に政治色が濃くなり、対アメリカ戦への正当性を訴えていた。慌(あわ)ただしいこの時期において、一時の涼を取るように、蝶や蜂、また桜や青草を静かに眺めて、心の安寧(あんねい)を得ようとしたのではないか。あるいは晩年の作か。
漢詩の小知識
「宜」について
<音>はギ <訓>はよろシ と読むが、意味は微妙に複雑。
➀筋道にかなっている[事宜(じき)](時宜を得た政策)
②都合が良い [便宜(べんぎ)](便宜な交通手段)
③ほどよいかげん [適宜(てきぎ)](適宜な温度で)
特別な使い方
1 むべナリ 当然である
(牡丹之愛、宜乎=牡丹を之愛するは宜なるかな)
2 再読文字 よろシク……べシ ……するのがよろしい
(用人、宜取其所長=人を用いるは宜しく其の長たる所を取るべし)
詩の形
仄起こり七言絶句の形であって、上平声四支(し)韻の宜、離、時の字が使われている。
| 結句 | 転句 | 承句 | 起句 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者
徳富蘇峰 1863~1957
明治から昭和の評論家・歴史家・漢詩人
名は正敬(まさたか)または猪一郎(いいちろう)、蘇峰は号。熊本県水俣(みなまた)に生まれる。家は代々庄屋兼代官を務めた。熊本洋学校に学び、キリスト教を知った。のち同志社に移り新島襄から洗礼を受けた。その後上京し、明治20年民友社を作り、雑誌「国民の友」を発刊、さらに「国民新聞」を発行して、平民主義を喧伝(けんでん)し、言論人として確立した。生涯「近世日本国民史」百巻を完成させることに専念した。昭和18年文化勲章受章。享年94。
