漢詩紹介
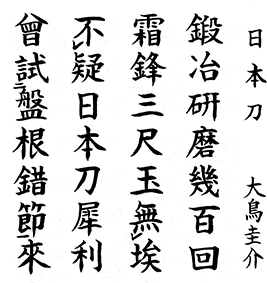
読み方
- 日本刀 <大鳥 圭介>
- 鍛冶研磨す 幾百回
- 霜鋒三尺 玉に埃無し
- 疑わず 日本刀の 犀利なるを
- 曽て 盤根錯節を 試み来る
- にっぽんとう <おおとり けいすけ>
- たんやけんます いくひゃっかい
- そうほうさんじゃく たまにちりなし
- うたがわず にっぽんとうの さいりなるを
- かつて ばんこんさくせつを こころみきたる
詩の意味
鍛え抜き、磨き抜くこと幾百回であろうか。そこをくぐり抜け、霜のように光る先端を持つこの三尺の見事な刀には、埃(ほこり)ひとつついていない。
美しいばかりか、この日本刀は、本当に堅くて鋭利なることは疑いのないことである。かつて、明治維新期の困難な局面に際して、事にあたり、この日本刀で切り開くように問題解決を試みてきた。
語句の意味
-
- 鍛 冶
- 金属を鍛えること 「鍛」は金属をたたく 「冶」は溶かす
-
- 霜 鋒
- 霜のように光る先端
-
- 犀 利
- 堅く鋭い 「犀」は野獣のさいの角のことで堅いことのたとえ
-
- 盤根錯節
- わだかまっている根と入り組んだ節 転じて困難な事柄
鑑賞
名刀の輝きに今も忘れ得ない幕末の日々
作者が35歳の若いころ江戸を出て、関東、奥羽を転戦し、幕府艦隊を引き連れた榎本武揚(たけあき)らとともに函館の五稜郭に立てこもり、官軍に抗戦したことを数年後に思い出しながら詠った詩である。いわゆる戊辰戦争への懐古詩である。未だ輝きを失わない名刀に見惚れつつ、国難を乗り越えなければならないという使命のもとに戦ってくれた日本刀に改めて労をねぎらっているところである。
備考
故事成語「盤根錯節」の由来
後漢時代(2世紀)、若い帝が即位した。当時、并州(へいしゅう)と涼州はたびたび匈奴に侵されていた。大将軍は国費不足を理由に涼州を放棄しようとした。この時、虞詡(ぐく)なる人物が「涼州は昔から烈士が出ています。匈奴に任せてはいけません」というと群臣も賛同した。それ以来大将軍は己の政策に難を示す虞を憎んだ。そのころ安徽省(あんきしょう)の一部で暴動があった。大将軍は処刑代わりに過酷な任務をこの虞に命じた。皆は戦死を心配したが、彼は平気で言った。「曲がった根っことか、入り混じった節とかにぶつからないと鋭い刃物の値打ちもわからない」と。虞は進んで苦難に飛び込み自分の力を試そうとした。ここから「盤根錯節に遭うて利器を知る」という故事成語が広まった。現在は、平和な時には人の値打ちが分からないが、困難に遭って初めてわかる、という意味に使われる。「盤根錯節」で大きな困難を意味することもある。
参考
戊辰戦争とは
明治元年から翌年まで行われた新政府と旧幕府側との戦いの総称。8つの戦いからなる。主なものを挙げる。
鳥羽・伏見の戦い 薩長軍対旧幕府軍 旧幕府軍は敗退した
上野戦争 旧幕臣約1000人が挙兵 西郷隆盛を苦しめたが大村益次郎の作戦により戦端を開いてから1日で壊滅した
奥羽越列藩同盟 東北・北陸が新政府に対抗 鎮圧される
会津戦争 会津藩が抵抗 若松城(鶴が城)が炎上 白虎隊悲話
五稜郭の戦い 函館五稜郭で榎本・大鳥が新政府に抵抗 共和国樹立を宣言したが敗戦
詩の形
仄起こり七言絶句の形であって、上平声十灰(かい)韻の回、埃、来の字が使われている。
| 結句 | 転句 | 承句 | 起句 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者
大鳥圭介 1833~1911
幕末から明治時代の政治家
播磨の国(兵庫県)赤穂市の医家に生まれた。名は純彰、号は如楓。閑谷(しずたに)学校、適塾に学んだ。学者の道に見切りをつけ陸軍に転じた。慶応4年(明治元年)戊辰戦争が起こると、自ら編成した伝習隊を率いて函館に向かった。五稜郭に立てこもり新政府に対抗したが降服した。敗戦後投獄された。赦(ゆる)されたのち新政府のもと工部(こうぶ)大学長、学習院長などの要職に就いた。明治26年には朝鮮国公使となり敏腕を発揮したがすぐに解任され、翌年帰国後には枢密(すうみつ)院顧問に昇った。明治44年没す。享年79。男爵を授かる。
