漢詩紹介
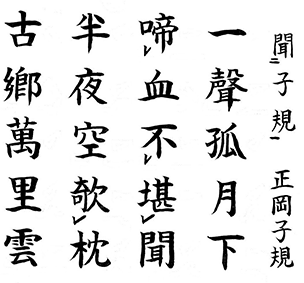
読み方
- 子規を聞く <正岡 子規>
- 一声 孤月の下
- 血に啼いて 聞くに堪えず
- 半夜 空しく枕を欹つ
- 古郷 万里の雲
- ほととぎすをきく <まさおか しき>
- いっせい こげつのもと
- ちにないて きくにたえず
- はんや むなしくまくらをそばだつ
- こきょう ばんりのくも
詩の意味
夜のホトトギスの一声が、一輪の月のもとに響き渡る。血を吐くような鋭い鳴き声は尋常でなく、とても聞くに堪えられない。
真夜中のその声を聞いた旅人は、空しい心で枕を傾け、万里の空の向こうにある故郷に思いを馳(は)せるのである。
語句の意味
-
- 子 規
- ホトトギス 他に杜鵑・時鳥・不如帰・郭公など表記は多数ある 文学上は夏の鳥
-
- 啼 血
- 鋭い声が血を吐くようなと例えられる
-
- 半 夜
- 真夜中
-
- 欹 枕
- 枕を傾ける
鑑賞
まさかこの詩が11歳の時の作品とは 天才子規
この詩は題詠(決められた題のもとに作るもの)の一種である。作者が自分に「ホトトギス」という題を課して作詩したもので、遠く故郷を離れて実体験したものではない。
一輪の月の下にホトトギスが鋭く鳴くのを聞いて故郷を思い出すという構図は漢詩に古くからあるものだが、これが11歳の作だというから驚きである。今でいえば小学校高学年である。漢詩の基本を踏まえ、いかにもありそうな孤独の旅人の心情をみごとに表現している。
22歳の時喀血(かっけつ)して作者は、それを機に号を子規と定めたというが、この11歳の詩と11年後の作者とは運命的因縁がありそうな気がする。
参考
歌集「竹の里歌」からホトトギスを詠んだ歌3首
〇 五月雨の 闇の山道 辿りゆく
松明消えて 鳴くホトトギス 松明=たいまつ
〇 葛城の み谷に眠る ゐのししの
鼾の上に 鳴くホトトギス 鼾=いびき
〇 五月雨の 雨降り注ぐ 紫の
花あやめ田に 鳴くホトトギス
平安文学に見るホトトギス
〇 ほととぎす 鳴きつるかたを 眺むれば
ただ有明の 月ぞ残れる (藤原実定・千載集)
〇 夏山に 鳴く時鳥 心あらば
もの思ふ我に 声な聞かせそ (作者不明・古今集)
詩の形
平起こり五言絶句の形であって、上平声十二文(ぶん)韻の聞、雲の字が使われている。
| 結句 | 転句 | 承句 | 起句 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者
正岡子規 1867~1902
明治時代の俳人・歌人
名は常規(つねのり)、号は子規、竹の里人など多数ある。父は松山藩の下級武士だったが、子規が5歳の時他界。漢学を祖父に、書を伯父から学んだ。11歳のころから漢詩を作り始めた。17歳で上京し、大学予備門にはいる。ここで夏目漱石に出会った。のち東京帝国大学国文科に入学し、俳句の復興に志した。大学中退後、日本新聞社に入り創作活動を展開。29歳の時従軍記者として清国に渡ったが2度目の喀血をして帰国した。脊椎カリエスで歩行困難に陥り、生涯病床生活であった。雑誌「ホトトギス」「アララギ」で俳句や短歌の革新運動の先頭に立った。享年36。歌集「竹の里歌」、随筆「墨汁一滴」など著書多数。
