漢詩紹介
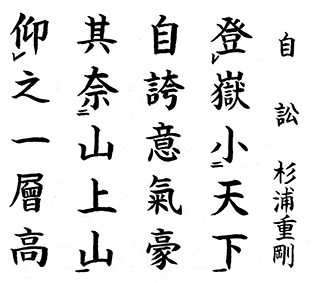
読み方
- 自 訟 <杉浦 重剛>
- 岳に登って 天下を小とす
- 自ら誇る 意気の豪なるを
- 其れ山上の 山を奈んせん
- 之を仰げば 一層髙し
- じしょう <すぎうら しげたけ>
- がくにのぼって てんかをしょうとす
- みずからほこる いきのごうなるを
- それさんじょうの やまをいかんせん
- これをあおげば いっそうたかし
詩の意味
高い山に登ってみると、下界の天下は小さいものに思われ、まるで今の自分のようで、自らの意気の盛んなることを誇りに思うのである。
だがしかし、世界にはもっと高い山がある。(自分はまだまだその山の高さには至っていない) この山を仰げば、一層高く聳えているのである。(自分より上の人が居るから、決して慢心してはいけない。さらに勉学をして向上しなければならないと自らを戒めているのである)
語句の意味
-
- 自 訟
- 自ら責める 「訟」は訴えるまたは責める
-
- 豪
- 盛んな様子
-
- 奈
- どうする
-
- 山上山
- 今登っている山よりもっと高い山
鑑賞
学問の道は山の如し いよいよ登ればいよいよ高し
もちろんこの詩は、山の高さの尊さを詠じているものではない。作者は22歳で英国へ国費留学して、5年後帰国している。そのころの作と思われる。当時留学体験者は、留学したというだけで高く評価され、栄進の道も約束されていた。作者はそれに驕(おご)ることなく、自分を戒めている詩である。
「孟子」尽心(じんしん)上編に「孔子東山に登り魯=孔子の生まれた小国=を小とし、泰山=たいざん、中国第一の名山=に登って天下を小とす」とある。泰山からの眺めでは天下など小さいものだと感じたという。普通の認識では天下はとてつもなく広いものであるが、高所からの展望は登ってみなければわからない。作者はまだ泰山に匹敵する山に登っていない。学問にしろ人間陶冶(とうや)にしろ、上には上があるのだから、泰山に登るべく、1日も勉学を怠ってはならない。今の自分に慢心してはならないと自戒し、さらに向上せんとする心意気を訴えている。
江戸後期の学者、草場佩川の詩「山行同志に示す」の後半「山に登るは恰も書生の業に似たり、一歩歩高くして光景開く」とあるのも、学生たちが現状に満足してはいけないことを戒めている。相通ずるものがある。
参考
杉浦重剛の「日本主義」
日清戦争から明治30年代中ごろまで流行した思想。海外進出を唱え、その指導理念として建国の精神を主張した。国家至上の見地から、世界主義に反対し、宗教を批判した。とくにキリスト教を攻撃した。(日本史小辞典=山川出版)
わが国の伝統的精神を、政治・経済・文化などあらゆる側面の根本基調にすべきであるとする思想または主張(広辞苑)
詩の形
仄起こり五言絶句の形であって、下平声四豪(ごう)韻の豪、高の字が使われているが、平仄の配列が規則に合わないので拗体である。
| 結句 | 転句 | 承句 | 起句 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者
杉浦重剛 1855~1924
明治・大正時代の学者・教育者
近江の国(滋賀県)膳所(ぜぜ)藩の家に生まれる。号は梅窓または天台道士。16歳で選ばれて大学南校(東京大学の前身)に入る。22歳で英国に5年間留学した。帰国後、大学予備門校長、文部省専門学務局次長を務めた。民間に移り新聞の発刊に努めた。当時の急速な欧化主義に反対し日本主義を唱えた。読売、朝日の両新聞の社説を担当した。明治25年に日本中学校を創立し子弟の教育にあたった。43年、國學院大學学監となる。大正3年東宮学問所の御用係となった。大正13年没す。享年70。勲二等旭日重光章を賜った。
