漢詩紹介
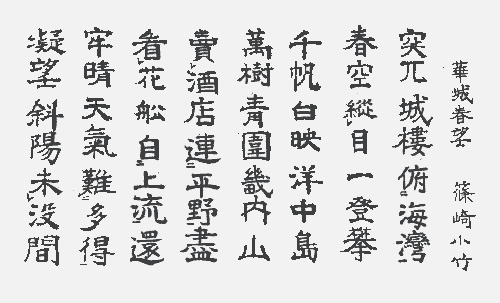
吟者:山口華雋 松野春秀
2006年8月掲載
読み方
- 華城春望<篠崎小竹>
- 突兀たる城樓 海灣を俯す
- 春空目を縦にせんと 一たび登攀
- 千帆白く映ず 洋中の島
- 萬樹靑く圍む 畿内の山
- 酒を賣るの店は 平野に連なって盡き
- 花を看るの船は 上流自り還る
- 牢晴の天氣 多く得難し
- 凝望せん斜陽の 未だ沒せざる間に
- かじょうしゅんぼう<しのざきしょうちく>
- とっこつたるじょうろう かいわんをふす
- しゅんくうめをほしいままにせんと ひとたびとうはん
- せんぱんしろくえいず ようちゅうのしま
- ばんじゅあおくかこむ きないのやま
- さけをうるのみせは へいやにつらなってつき
- はなをみるのふねは じょうりゅうよりかえる
- ろうせいのてんき おおくえがたし
- ぎょうぼうせんしゃようの いまだぼっせざるあいだに
字解
-
- 華城
- 大阪城 かつては大阪のことを浪華(なにわ)と呼んだ
-
- 突兀
- 高く突き出ているさま
-
- 海灣
- 大阪湾 江戸時代では大阪城のすぐ下あたりで寝屋川と淀川が合流していて海に流れ出ていた
-
- 俯
- みおろす
-
- 縦
- 思い通りにする 存分にする
-
- 畿内
- 山城・大和・河内・和泉・摂津を指す その山とは、生駒・葛城・金剛・六甲などを指す
-
- 牢晴
- よく晴れたさま 「牢」はかっちりとしたさま
-
- 凝望
- じっと眺める 「凝」はこらす
-
- 斜陽
- 夕日
意解
高く突き出しているお城の楼閣は、大阪湾を見下ろしているようである。今日の春空に、一度あたりの景色を存分に眺めてみたいと思ってこの城に登ってみた。
すると、多くの帆掛け船が白く海の上に浮かんでいて、湾内の島々に美しく映えており、青々と茂っている畿内の山々が、この大阪を取り囲んでいる。
遊覧の客を待つ酒屋が、遠くの方まで続いているのが見え、(寝屋川や淀川のほうを眺めると)花見の客を乗せた船が上流から下って還ってくるのが見える。
今日のようなよく晴れたお天気は、なかなか数多く得難いことであるから、夕日がまだ海に沈まない間に、十分そこらあたりの景色を眺めておきたいものだ。
備考
この詩の構造は仄起こり七言律詩の形であって、上平声十五刪(さん)韻の灣、攀、山、還、間の字が使われている。
律詩は第三句と第四句、第五句と第六句には、各対句を用いるのが特徴である。
| 尾聯 | 頸聯 | 頷聯 | 首聯 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者略伝
篠崎小竹 1781-1851
江戸時代後期の儒学者。諱(いなみ)は弼(たかし)、字(あざな)を承弼(しょうひつ)、通称長左衛門、幼名は金吾。畏堂(いどう)、小竹、南豊(なんほう)、退庵(たいあん)、些翁(さおう)等を号す。豊後(ぶんご)《大分県》の医師、加藤吉翁の次子、天明元年四月大坂に生まれる。幼い頃から鋭敏で、九歳のとき篠崎三島(さんとう)の門に入り養子となる。江戸に出て尾藤二洲(びとうにしゅう)に学び、また古賀精里(こがせいり)の門に入る。諸侯のなかには教えを求める者が多かった。蔵書も多く万巻に上るという。嘉永四年五月没す。年71。
参考
一つの詩が八句でできている詩を律詩といい、一句が七字の時七言律詩という。第一句の二字目が仄字である時、仄起こり七言律詩という。
