漢詩紹介
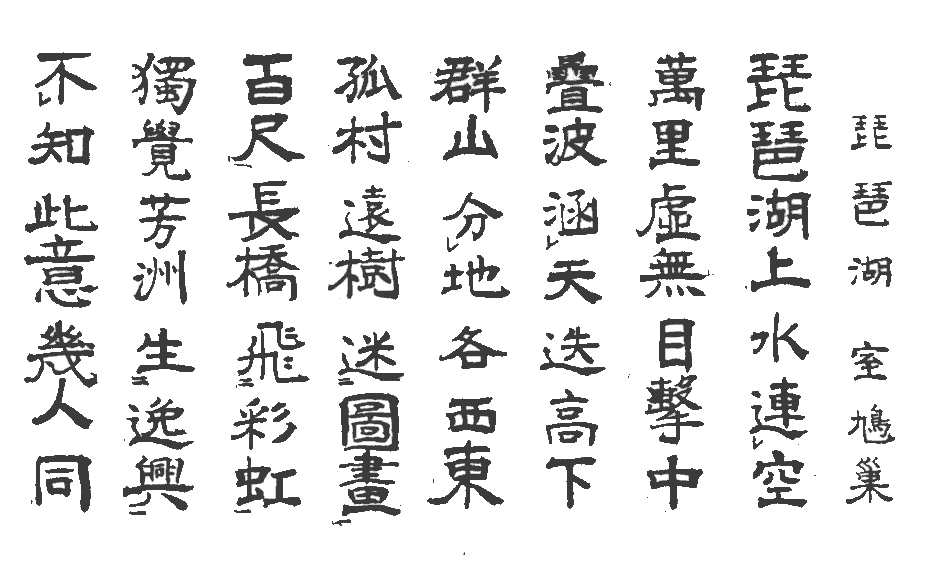
読み方
- 琵琶湖<室鳩巣>
- 琵琶湖上 水空に連なり
- 萬里虚無 目撃の中
- 畳波天を涵して 迭いに高下し
- 群山地を分かって 各西東
- 弧村の遠樹 図画に迷い
- 百尺の長橋 彩虹を飛ばす
- 獨り覚ゆ芳洲の 逸興を生ずるを
- 知らず此の意 幾人か同じき
- びわこ<むろきゅうそう>
- びわこじょう みずそらにつらなり
- ばんりきょむ もくげきのうち
- じょうはてんをひたして たがいにこうげし
- ぐんざんちをわかって おのおのせいとう
- こそんのえんじゅ ずがにまよい
- ひゃくしゃくのちょうきょう さいこうをとばす
- ひとりおぼゆほうしゅうの いっきょうをしょうずるを
- しらずこのい いくにんかおなじき
字解
-
- 虚 無
- 何も無い
-
- 畳 波
- 重なり押し寄せる波
-
- 群 山
- 多くの山 ここでは東岸の近江富士・伊吹山、西岸の比良山・比叡山などをさす
-
- 弧村遠樹
- ここでは唐崎の松の絶景をさす
-
- 百尺長橋
- 瀬田の大橋
-
- 彩 虹
- きれいな虹
-
- 芳 洲
- 花などが咲いて芳しい河原
-
- 逸 興
- すぐれた趣
意解
琵琶湖を一望すれば、水面が空に連なって、万里の遠方まで目に入るものは何も無い。
ただ幾重にも重なって押し寄せる波だけが、大空を浸すばかりに互いに上下して、その周辺の多くの山々は、地の東西に別れて裾野を広げてそびえている。
(さらに目を転じると)一つの離れた村に見える遠方の樹々は、図画にどう描いてよいかわからないほど美しく、幾百尺もある瀬田の大橋は、まるで彩り鮮やかな虹が横たわっているようである。
私は一人、花の咲いている芳しい河原を見ては非常に興味の生ずるのを覚えるのだが、この自分の心持ちと同じ者が果たして何人いるだろうか。
備考
この詩の構造は、平起こり七言律詩の形であって、上平声一東(とう)韻の空、中、東、虹、同の字が使われている。第三句は平仄が二四不同になっていない。
| 尾聯 | 頸聯 | 頷聯 | 首聯 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者略伝
室 鳩巣 1658-1734
江戸時代中期の儒学者。名は直清(なおきよ)、字は師礼(しれい)、又は汝玉(じょぎょく)、通称は新助、号は鳩巣、又は滄浪(そうろう)という。 一説に熊谷直実(くまがいなおざね)《源平一の谷合戦の武将》の末裔(まつえい)といわれる。父の玄僕(げんぼく)は備中英賀(あが)郡中井村《現岡山県上房(上房)郡北房(ほくぼう)町》の人で、江戸に出て医を業とした。鳩巣は江戸谷中(やなか)に生まれ、幼い時から秀才で木下順庵につき、朱子学を学び詩文に勝(すぐ)れた。新井白石の推挙により幕府の儒官になる。赤穂浪士の快挙を讃えて有名で、徳川吉宗から駿河台(するがだい)に邸(やしき)を与えられ、駿台(すんだい)先生と呼ばれた。享保19年8月没す。年76才。
参考
第一句の二字目が平字であるとき、平起こり七言律詩という。
