漢詩紹介
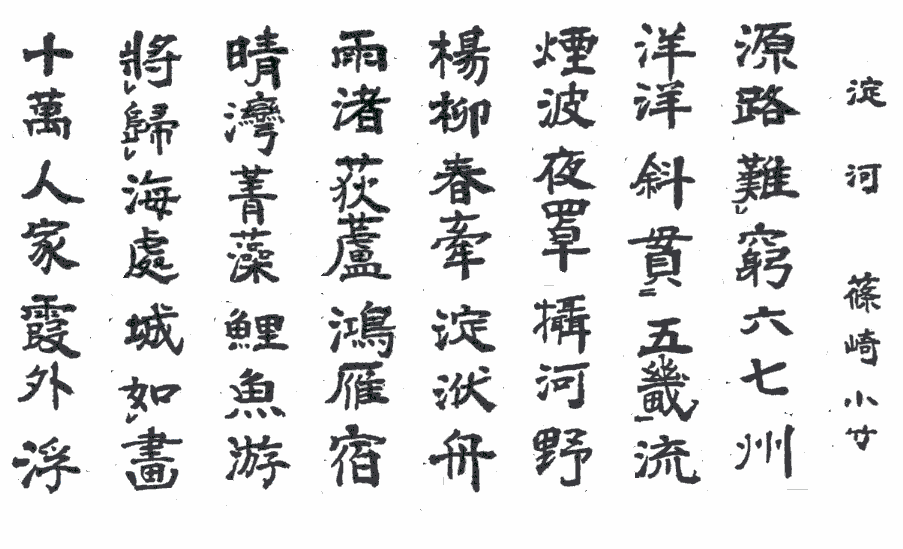
読み方
- 淀河<篠崎小竹>
- 源路極め難し 六七州
- 洋洋として斜めに五畿を貫いて流る
- 煙波夜罩む 攝河の野
- 楊柳春牽く 淀洑の舟
- 雨渚の荻蘆には 鴻雁宿り
- 晴灣の菁藻には 鯉魚游ぐ
- 將に海に歸らんとする處城畫の如く
- 十萬の人家 霞外に浮かぶ
- よどがわ<しのざきしょうちく>
- げんろきわめがたし ろくしちしゅう
- ようようとして ななめにごきを つらぬいてながる
- えんぱよるこむ せつかの の
- ようりゅうはるひく でんぷくのふね
- うしょのてきろには こうがんやどり
- せいわんのせいそうには りぎょおよぐ
- まさにうみにかえらんとするところ しろえのごとく
- じゅうまんのじんか かがいにうかぶ
字解
-
- 六七州
- 六つか七つの国
-
- 五 畿
- 山城・大和・河内・和泉・摂津の総称
-
- 煙 波
- 靄 もや 水蒸気 水煙り
-
- 淀 洑
- 淀川の流れ 「洑」はめぐり流れること
-
- 雨 渚
- 雨の降る川辺
-
- 荻 盧
- おぎやあしの草
-
- 鴻 雁
- 大小の雁
-
- 菁 藻
- うき草
-
- 將
- 「まさに・・・す」と読む再読文字 「今にも・・・しようとする」
意解
淀川の源はどこから発しているのか十分には見窮(みきわ)めがたいが、多分六つか七つの国々から発しているのであって、ひろびろと斜めに五つの国境(くにざかい)を貫いて流れている。
夜になるとその川の水煙が靄のようになって、摂津や河内の野に一面にこもり、春になると川岸の柳が芽吹き、その長くたれた枝が風に吹かれて、ちょうど淀川の流れに浮かぶ舟を引いているように見える。
雨の日の川岸のおぎやあしの茂みでは、大小の雁が宿を借りているし、晴れた日の入り江の浮き草の中では、鯉が泳いでいる。
川が海に注ぎ込もうとするあたりには、大阪城が絵のように美しくそびえ、十万もあろうか、大阪の町の人家が霞の上に浮かんでいるようである。
備考
この詩の構造は仄起こり七言律詩の形であって、下平声十一尤(ゆう)韻の州、流、舟、游、浮の字が使われている。
| 尾聯 | 頸聯 | 頷聯 | 首聯 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者略伝
篠崎小竹 1781-1851
江戸時代後期の儒学者。諱(いなみ)は弼(たかし)、字(あざな)を承弼(しょうひつ)、通称長左衛門、幼名は金吾。畏堂(いどう)、小竹、南豊(なんほう)、退庵(たいあん)、些翁(さおう)等を号す。豊後(ぶんご)《大分県》の医師、加藤吉翁の次子、天明元年四月大坂に生まれる。幼い頃から鋭敏で、九歳のとき篠崎三島(さんとう)の門に入り養子となる。江戸に出て尾藤二洲(びとうにしゅう)に学び、また古賀精里(こがせいり)の門に入る。諸侯のなかには教えを求める者が多かった。蔵書も多く万巻に上るという。嘉永四年五月没す。年71。
参考
再読文字 漢文には一字で副詞と助動詞や動詞との二つの意味を併せもっているものがある。まず、副詞的に読み、次に返り点に従って返り、助動詞や動詞にあたる意味として読む。
