漢詩紹介
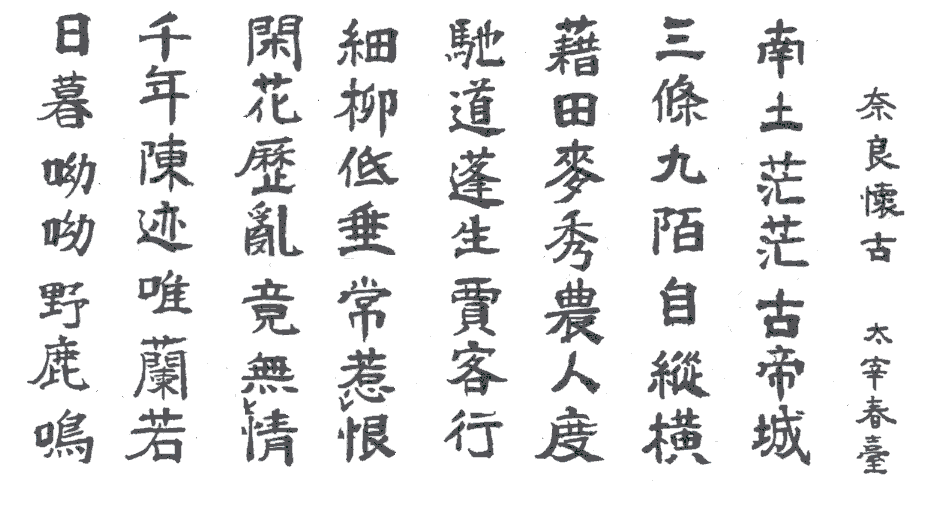
読み方
- 奈良懐古<太宰 春臺>
- 南土茫茫たり 古帝城
- 三條九陌 自ずから縦横
- 藉田麥秀でて 農人度り
- 馳道蓬生じて 賈客行く
- 細柳低く垂れて 常に恨みを惹き
- 閑花歴亂として 竟に情無し
- 千年の陳迹 唯蘭若
- 日は暮れて呦呦 野鹿鳴く
- ならかいこ<だざい しゅんだい>
- なんどぼうぼうたり こていじょう
- さんじょうきゅうはく おのずからじゅうおう
- せきでんむぎひいでて のうじんわたり
- ちどうよもぎしょうじて こかくゆく
- さいりゅうひくくたれて つねにうらみをひき
- かんかれきらんとして ついにじょうなし
- せんねんのちんせき ただらんにゃ
- ひはくれてゆうゆう やろくなく
字解
-
- 南土
- 奈良 本来は南都と書く 京都を北都というのに対する語
-
- 古帝城
- 古い帝都 平城京 「城」は町
-
- 三條九陌
- 東西の道筋 「條」は縦の道筋 「陌」はあぜ道
-
- 藉田
- 祖廟を祭る供米を作るため天皇自身が耕される田 大内裏(皇居のあるところを内裏といい、その上に諸官庁所在の地を含めていう) の中にあった
-
- 馳道
- 天皇や貴族の通る道 朱雀大路を指す
-
- 賈客
- 商売人 物売り
-
- 閑花
- のどかな花
-
- 歴亂
- 咲き乱れる
-
- 陳迹
- 古跡 「陳」は古い
-
- 蘭若
- 寺院
-
- 呦呦
- むせぶような鹿の鳴き声
意解
奈良の地は広々としていて、千年を経た古い帝都であり、三条九通りの道が縦横に交わっている。
歴代の天皇が自ら耕された藉田には今では麦が実り、商人達が通行している。(昔の面影はない)
細い柳の枝は低く垂れ下がって、(帝の寵愛を失って池に身を投じたという女官の)悲しみを常に思い起こさせるようでもあり、のどかな花はあちらこちらに咲き乱れ、(この世の歴史の変化をよそに)全く無情のようである。
千年の古跡として残っているものはただ寺院ばかりで、日が暮れてくると、野鹿の悲しく鳴く声が聞こえてくる。
備考
この詩の構造は仄起こり七言律詩の形であって、下平声八庚(こう)韻の城、横、行、情、鳴の字が使われている。
| 尾聯 | 頸聯 | 頷聯 | 首聯 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者略伝
太宰春臺 1680-1747
江戸時代中期の儒者。名は純(あつし)、字は徳夫(とくふ)、幼名千之助、通称弥右衛門、春臺または紫藝園(紫芝園)と号した。もと平手姓であったが父の代に太宰謙翁の養嗣子となり太宰家を嗣ぐ。主に従って下野より信州飯田に移る。のち出石侯や森川出羽守にも仕えたが36歳以後自由の身となり専ら文筆をこととする。たまたま赤穂浪士復讐の事件が起こると、師の荻生徂徠と対立した。情を捨て理をとる理論家であったが詩は流麗であった。多くの著書がある。永享4年5月没す。年68。
参考
平城京奈良時代(710-794)の都、現在の奈良。
710年藤原京から平城京に都が移され、784年の長岡京遷都まで74年間、元明、元正、聖武、孝謙、淳仁、称徳、光仁、桓武天皇の都となった。
南北に上、中、下の三道があり、下を朱雀大路とし、東を左京、西を右京とした。横に通ずる大路は北から順に一条大路から九条大路とかぞえた。
