漢詩紹介
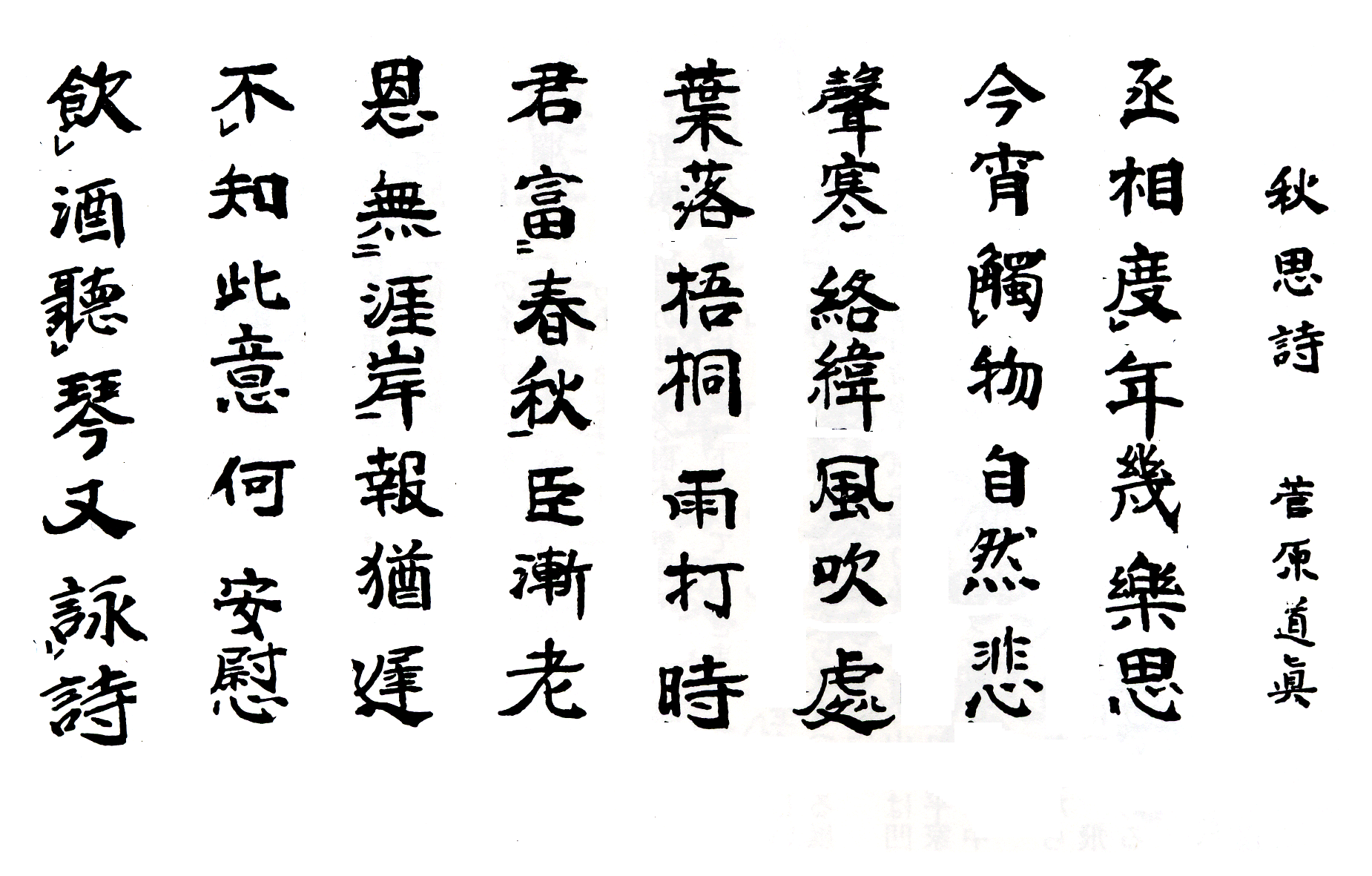
吟者:鈴木永山 松野春秀
2006年7月掲載
読み方
- 秋思詩<菅原 道眞>
- 丞相年を度って 幾ばくか楽思せる
- 今宵物に觸れて 自然に悲しむ
- 聲寒き絡緯 風の吹く處
- 葉の落つる梧桐 雨の打つ時
- 君は春秋に富み 臣は漸く老いたり
- 恩は涯岸無くして 報ゆる猶遲し
- 知らず此の意 何が安慰せん
- 酒を飲み琴を聽き 又詩を詠ず
- しゅうしのし<すがわらのみちざね>
- じょうしょうとしをわたって いくばくからくしせる
- こんしょうものにふれて しぜんにかなしむ
- こえさむきらくい かぜのふくところ
- はのおつるごどう あめのうつとき
- きみはしゅんじゅうにとみ しんはようやくおいたり
- おんはがいがんなくして むくゆるなおおそし
- しらずこのこころ なにがあんいせん
- さけをのみことをきき またしをえいず
字解
-
- 丞相
- 大臣 道眞は五十五歳で右大臣となり 菅丞相と呼ばれていたこのとき帝は十五歳であった
-
- 聲寒
- 声がもの淋しい
-
- 絡緯
- 秋の虫 こおろぎ きりぎりすくつわむしの総称
-
- 梧桐
- 青桐
-
- 君
- ここでは醍醐天皇
-
- 富春秋
- 年齢がまだ若く先が長い
-
- 漸
- しだいに
-
- 無涯岸
- 果てしない 無限である
-
- 飲酒…
- 白楽天の「北總三友詩」を踏まえている(三つの友人とは琴と酒と詩のこと)
意解
右大臣を拝命し年を越したが、(責任のあまりの重大さや公卿たちの不穏な空気を肌に感じて)どれほどの楽しい思いをしたことがあろうか、そのため今宵も何かにつけて自然に悲しく思うのである。
秋風の吹くところに、もの淋しく鳴く秋の虫達の声を聞き、また雨の降る夜には青桐の葉がカサカサと落ちる音を聞くにつけても、ことさらその思いを深くする。
わが君は御年もまだ若くていらっしゃり、自分はしだいに老境に向かっているのに、限りない君の御恩にはまだお報いしないままでいる。
このやるせない心を何が慰めてくれるであろうか、自分にはわからなく、〔白楽天に倣(なら)って〕ただ酒を飲み、琴を聴き、また詩を吟詠しているばかりである。
備考
醍醐天皇の昌泰三年(九00)九月十日の宮中の宴に「秋思」の勅題を賜り、この詩を詠じて奉答した。「九日後朝(こうちょう)同賦秋思應制」(九日後朝同じく秋思を賦し制に應ず)が本題であるが、本会では「秋思詩」と簡略にした。
この詩の構造は、仄起こり七言律詩の形であって、上平声四支(し)韻の思、悲、時、遲、詩の字が使われている。第一句は孤平になっている。
| 尾聯 | 頸聯 | 頷聯 | 首聯 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者略伝
菅原道眞 845-903
菅原是善(すがわらのこれよし)の三男。平安時代の大政治家として、当代随一であった。宇多(うだ)、醍醐(だいご)の二朝に仕えたが、権勢の拡大を左大臣藤原時平(ふじわらのときひら)から疎(うと)まれ延喜元年(九〇一)大宰権帥(だざいのごんのそつ)に左遷され、大宰府で没す。年五十九。没後、太政大臣を拝命し、名誉が回復され後世御霊(ごりょう)となり天満大自在天神として崇敬され、大宰府天満宮・北野神社などに祀られた。漢詩集「菅家文草(かんけぶんそう)」「菅家後集」がある。
参考
白楽天の洛陽住まいの詩集「洛中集」の「北總三友詩」に次の一説がある。
今日北總の下(もと)自(みずか)ら問ふ何の為す所ぞ
欣然三友を得たり 三友とは誰とか為す
琴罷(や)めば輒(すなわ)ち酒を挙げ 酒罷めば輒ち詩を吟ず
三友逓(たが)ひに相引き 循環して己(や)む時なし
一弾中心に〔?〕(かな)ひ 一詠四肢を暢(の)ぶ
なほ中に間(ひま)あるを恐れ 酒を以て之を弥縫(びぼう)す…‥
これを詠んだ道眞は「三友中の詩友だけが真友であり死までの伴侶である」と詠じている。
