漢詩紹介
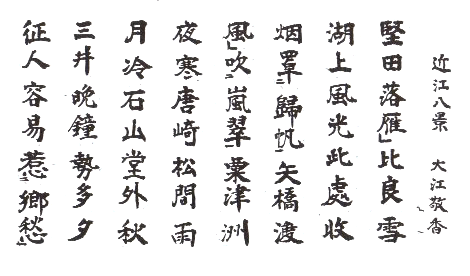
吟者:中 永捷
2017年10月掲載
読み方
- 近江八景<大江敬香>
- 堅田の落雁 比良の雪
- 湖上の風光 此の處に収まる
- 烟は歸帆を罩む 矢橋の渡
- 風は嵐翠を吹く 粟津の洲
- 夜は寒し唐崎 松間の雨
- 月は冷ややかなり石山 堂外の秋
- 三井の晩鐘 勢多の夕べ
- 征人容易に 郷愁を惹く
- おうみはっけい<おおえけいこう>
- かたたのらくがん ひらのゆき
- こじょうのふうこう このところにおさまる
- けむりはきはんをこむ やばせのわたし
- かぜはらんすいをふく あわづのしま
- よはさむしからさき しょうかんのあめ
- つきはひややかなりいしやま どうがいのあき
- みいのばんしょう せたのゆうべ
- せいじんよういに きょうしゅうをひく
字解
-
- 近江八景
- 琵琶湖の南部にある八勝景 中国の瀟湖(しょうこ)八景に模して定めた 堅田の落雁・比良の暮雪・粟津の青嵐・唐崎の夜雨・矢橋の歸帆・石山の秋月・三井の晩鐘・勢多の夕照
-
- 風光
- 景色
-
- 烟
- 靄(もや)
-
- 嵐翠
- ここでは青々とした松並木 {嵐」は本来青々と見える山の気配「翠」も青緑
-
- 征人
- 旅人
-
- 郷愁
- 故郷をしみじみ思う情
意解
堅田の浮御堂(うきみどう)あたりでは、飛び降りてくる雁の群れがよく似合うし、遠く聳(そび)える比良山の暮雪が琵琶湖に映じている景色などはまことにみごとである。
矢橋の渡し場に向かう帆掛け船には夕暮れの靄がたちこめ、風が青々とした粟津の松並木を吹いているのも眺められる。
夜寒くなって唐崎の松林の間に降る雨にも風情があり、月が皓皓(こうこう)と輝く石山寺あたりの秋も美しい。
三井寺の晩鐘や勢多(瀬田)の唐橋の夕暮れ時の景色も深い趣があり、ここを通り過ぎる旅人はたちまち故郷をしみじみ思う情に誘われてしまう。
備考
この詩の構造は平起こり七言律詩の形であって、下平声十一尤(ゆう)韻の収、洲、秋、愁の字が使われている。第一句は踏み落としになっており、第三句、第五句、第七句は平仄が整っていない。第七句は孤平になっている。
| 尾聯 | 頸聯 | 頷聯 | 首聯 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者略伝
大江敬香 1857-1916
明治、大正時代の漢詩人。徳島藩士《のち浜松県典事(てんじ)》の大江孝文の長男として江戸八丁堀で生まれる。名は孝之(たかゆき)、字は子琴(しきん)、号は敬香、楓山(ふうざん)、愛琴(あいきん)などがある。明治5年慶応義塾に入り、卒業後東京大学文学部に入学するが、病により中途退学し、冀北(きほく)学舎に入りのち教師になる。漢詩は21歳(明治11年)より始め、七言律詩を得意とし、婦人の琴雨もまた詩をよくした。「花香月影」「風雅報」などを刊行する。大正5年10月病のため没す、年60。
