漢詩紹介
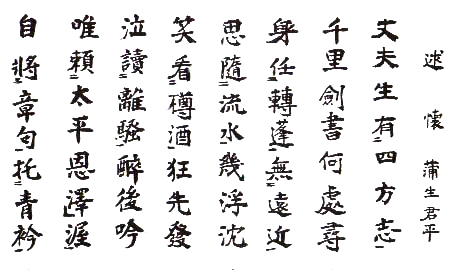
CD④収録 吟者:藤本曙冽
2016年 9月掲載
読み方
- 述懐<蒲生君平>
- 丈夫生まれて 四方の志有り
- 千里劍書 何れの處にか尋ねん
- 身は轉蓬に任せて 遠近無く
- 思いは流水に随うて 幾浮沈
- 笑うて樽酒を看て 狂先ず發し
- 泣いて離騒を讀んで 酔後に吟ず
- 唯太平恩澤の 渥きに賴りて
- 自ら章句を将って 青衿に托す
- じゅっかい<がもうくんぺい>
- じょうふうまれて しほうのこころざしあり
- せんりけんしょ いずれのところにかたずねん
- みはてんぽうにまかせて えんきんなく
- おもいはりゅうすいにしたごうて いくふちん
- わろうてそんしゅをみて きょうまずはっし
- ないてりそうをよんで すいごにぎんず
- ただたいへいおんたくの あつきによりて
- みずからしょうくをもって せいきんにたくす
字解
-
- 丈夫
- 一人前の男子
-
- 四方志
- 諸国に遠遊する志
-
- 劍書
- 刀剣と書物 文武両道をいう
-
- 轉蓬
- 蓬(よもぎ)が風で飛ぶようにあちこちとさまよう
-
- 樽酒
- 酒樽(さかだる)の酒
-
- 狂
- 酔態を演じる
-
- 離騒
- 楚の屈原の詩文集「楚辞」中の編名 屈原は忠誠を尽くして宮廷に仕えたがねたみに遇って王に信任されず追放された その折の失意をのべたもの
-
- 恩澤
- 天皇の恩恵
-
- 握
- てあつくゆき届いている
-
- 章句
- 学問
-
- 青衿
- 青年 「衿」はえり 青年は襟を青くした
意解
一人前の男子として生まれたからには、諸国に遊学して世事に携わろうという大志を抱くもので、自分も千里の道を剣と書を携えて、(文武両面にわたって修行するため)どこを尋ねたらよいのだろうかと意気盛んであった。
今まで自分の身は蓬が飛ぶに任せるように、遠く近くの地を流浪し、自分の思いも氷の流れに従うように、(さまざまな思想に触れながら)幾度も浮き沈みを経験してきた。
(あるときは自分の不甲斐無さのために)自嘲しながら酒を飲んで酔態を演じたり、(またあるときは)憂国の詩人屈原の{離騒」を泣きながら読んで酔後に詩を吟じたりした。
ただ幸いなことに、今の世は太平で天皇の恩恵もゆき届いているので、自分はこれからは学問の師となって教え、青年たちに我が希望を託すのである。
備考
この詩の構造は平起こり七言律詩の形であって、下平声十二侵(しん)韻の尋、沈、吟、衿、の字が使われている。第一句は踏み落としになっている。
| 尾聯 | 頸聯 | 頷聯 | 首聯 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者略伝
蒲生君平 1768-1813
江戸時代後期の尊王家、著述家、漢詩人、宇都宮の灯油商、福田正栄の第四子として生まれる。名は秀実(ひでざね)、字は君平、号は修静庵、通称伊三郎という。祖父から蒲生氏郷(がもううじさと)の子孫と聞き、蒲生と改めたという。14歳で鈴木石橋(せっきょう)に師事した。のち水戸の藤田幽谷(ゆうこく)《藤田東湖の父》や仙台の林子平と交わり、水戸学の影響を受け尊王の志を厚くする。古学を特に学び諸国各地の天皇陵を調べて「山稜志」を著述する。高山彦九郎、林子平と共に寛政の三奇人の一人。文化10年7月病のために没す。年45。
