漢詩紹介
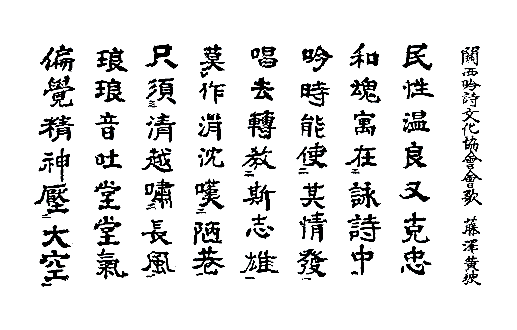
吟者:教養指導部(女性)
読み方
- 関西吟詩文化協會會歌<藤澤 黄坡>
- 民性温良にして 又克く忠なり
- 和魂寓して 詠詩の中に在り
- 吟ずるときは能く 其の情をして發せしめ
- 唱え去って 轉斯の志をして 雄ならしむ
- 作す莫れ消沈して 陋巷に嘆ずるを
- 只須らく清越 長風に嘯くべし
- 琅琅たる音吐 堂堂の氣
- 偏に覺ゆ精神の 大空を壓するを
- かんさいぎんしぶんかきょうかいかいか<ふじさわ こうは>
- みんせいおんりょうにして またよくちゅうなり
- わこんぐうして えいしのうちにあり
- ぎんずるときはよく そのじょうをしてはっせしめ
- となえさって うたたこのこころざしをして ゆうならしむ
- なすなかれしょうちんして ろうこうにたんずるを
- ただすべからくせいえつ ちょうふうにうそぶくべし
- ろうろうたるおんと どうどうのき
- ひとえにおぼゆせいしんの たいくうをあっするを
字解
-
- 又
- 更に
-
- 寓
- 含まれている
-
- 轉
- しだいに
-
- 陋巷
- 狭い路地裏 ここでは俗世間
-
- 須
- 「すべからく……べし」と読む再読文字「ぜひとも……するのがよい」の意
-
- 清越
- 清らかで高い気持ち
-
- 嘯
- 大きな声で詩を歌う
-
- 長風
- 勢いのよい風
-
- 琅琅
- 金属や玉がふれてなるよい音ここでは清らかな声
意解
我が国民性は温良で、さらにまた十分誠を尽くす心があり、このようないわゆる大和魂は、詩を吟ずる中に含まれている。
そこで、詩を吟ずるときには、我々は自分の感情を湧き上がらせることができるし、歌い終われば、しだいに我々の心を雄大にさせるものである。
したがって、詩を吟ずるものは意気消沈して俗世間での暮らしがさえないのを嘆いてはいけないのであって、ただぜひとも、清らかで高い気持ちで朗らかな声を出して、勢いのよい風に乗って歌うのがよろしい。
このように、朗々とした吟声と、堂々とした気勢のあがるところに、我々はその精神が大空を圧倒するほどの気持ちになっていくことをひたすらに感じるのです。
備考
この詩の構造は仄起こり七言律詩の形であって、上平声一東韻の忠、中、雄、風、空の字が使われている。
| 尾聯 | 頸聯 | 頷聯 | 首聯 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者略伝
籐澤黄坡 1876-1948
藤澤南岳の第二子として生まれ、先祖は讃岐の人で家代々漢字の名門。名は章(あきら)。通称章次郎といい、字は士明(しめい)、黄坡は号。父南岳の後を継いで門下を指導された。また関西唯一の漢字塾「泊園書院」院長で、詩書をよくされ「逍遥吟社」の社友を指導される。関西大学名誉教授。昭和九年関西吟詩同好会(現、社団法人関西吟詩文化協会)の初代会長として吟詩の普及に尽くされた。昭和23年12月没す。年74。
参考
明治維新以後の代表的な詩人
日柳燕石 城野静軒 西郷南洲 大槻盤渓 村上佛山 菊池渓琴
森 春濤 元田永孚 勝 海舟 正岡子規 夏目漱石 国分青厓
徳富蘇峰 土屋竹雨 鈴木豹軒 その他
