漢詩紹介
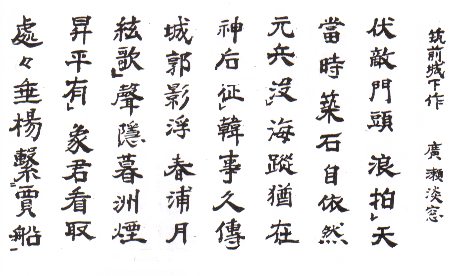
CD④収録 吟者:辰巳快水
2016年 10月掲載
読み方
- 筑前城下の作<廣瀬淡窓>
- 伏敵門頭 浪天を拍ち
- 當時の築石 自ずから依然たり
- 元兵海に沒せし 蹤猶在り
- 神后韓を征せし 事久しく傳う
- 城郭の影は浮かぶ 春浦の月
- 絃歌の聲は隱る 暮洲の煙
- 昇平象有り 君看取せよ
- 處處の垂楊に 賈船を繋ぐ
- ちくぜんじょうかのさく<ひろせたんそう>
- ふくてきもんとう なみてんをうち
- とうじのちくせき おのずからいぜんたり
- げんぺいうみにぼっせし あとなおあり
- じんこうかんをせいせし ことひさしくつとう
- じょうかくのかげはうかぶ しゅんぽのつき
- げんかのこえはかくる ぼしゅうのけむり
- しょうへいしょうあり きみかんしゅせよ
- しょしょのすいように こせんをつなぐ
字解
-
- 筑 前
- いまの福岡市博多地区
-
- 伏敵門
- 筥(はこ)崎八幡宮(福岡市東区)の楼門に亀山上皇(鎌倉中期)の宸筆(しんぴつ)で「敵國降伏」の四字額が掲げられている これは元寇(げんこう)の際に平和裏に降伏を勧めようとした朝廷側の願望の現れである
-
- 築 石
- 水城(みずき=周りに堤を築き水をたたえ敵の侵入を防いだ城)の石垣
-
- 神 后
- 神功(じんぐう)皇后のことで応神(おうじん)天皇の母 4世紀後半の人というが実在不明
-
- 城 郭
- 城を囲む壁 または城全体
-
- 昇 平
- 太平 世の中がおだやかに治まっていること
-
- 有 象
- 実際の姿がある
-
- 賈 船
- 商人の船
意解
「敵國降伏」の四字額を掲げた筥崎八幡宮の楼門あたりは今も波が高く天を拍ち、当時海岸に築かれた水城の石垣跡も依然として昔の光景を残している。
元軍十万の兵が海に没した跡も歴然として残り、神功皇后が征韓の折この地から船出なさったことも久しく伝えられている。
ところが今は様子が変わり、城の姿は春の浦辺の月光に照らされて水面に浮かび、弦歌の声は暮煙たなびく中洲あたりに隠れ聞こえる。
この太平の実際の姿を君たちは良く看取られよ、あちらこちらのしだれ柳には商人の舟が繋がれているのを。(戦争も無く安心して商いができるのも先祖の恩沢によるものである)
備考
福岡城外博多湾東の箱崎付近で、昔の元寇古戦場をしのび太平の御代(みよ)をたたえて作る。
この詩の構造は仄起こり七言律詩の形であって、下平声一先(せん)韻の天、然、傳、煙、船の字が使われている。
| 尾聯 | 頸聯 | 頷聯 | 首聯 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者略伝
廣瀬淡窓 1782-1856
天明2年豊後(ぶんご=大分県)日田(ひた)に生まれる。名は建(けん)、字は子基(しき)、淡窓と号す。天資温厚、学を好み、松下筑陰(まつしたちくいん)に師事、12歳にして七言律を賦す。のち亀井南溟(かめいなんめい)に学び、日田に帰り塾を開き桂林荘(けいりんそう)と称し、多数の門弟を教育する。安政3年11月没す。年75。正五位を贈られる。「遠思楼詩鈔」(えんしろうししょう)「淡窓詩話」(たんそうしわ)などの著書がある。
