漢詩紹介
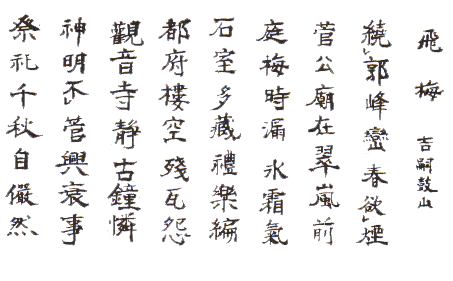
読み方
- 飛梅<吉嗣鼓山>
- 郭を繞る峰巒 春煙らんと欲し
- 菅公の廟は在り 翠嵐の前
- 庭梅時に漏らす 氷霜の氣
- 石室多く藏す 禮樂の編
- 都府樓は空しく 殘瓦を怨み
- 觀音寺は靜かに 古鐘憐れなり
- 神明管せず 興衰の事
- 祭祀千秋 自ずから儼然
- ひばい<よしつぐこざん>
- かくをめぐるほうらん はるけむらんとほっし
- かんこうのびょうはあり すいらんのまえ
- ていばいときにもらす ひょうそうのき
- せきしつおおくぞうす れいがくのへん
- とふろうはむなしく ざんがをうらみ
- かんのんじはしずかに こしょうあわれなり
- しんめいかんせず こうすいのこと
- さいしせんしゅう おのずからげんぜん
字解
-
- 飛 梅
- 昔 菅原道真公は都でことに梅を愛された 左遷されて太宰府に赴くにあたり「東風(こち)吹かば にほひおこせよ梅の花 主なしとて 春な忘れそ」の歌を詠まれたが 梅は菅公を慕って太宰府に飛び成長したと伝えられる
-
- 郭
- 城壁 ここでは太宰府の町
-
- 峰 巒
- 山並み ここでは右の天拝山・左の天鼓山・前の宝満山
-
- 翠 嵐
- 青々としているさま 「翠」も「嵐」もみどり青
-
- 氷 霜
- ここでは性質が清く潔白なこと
-
- 禮 樂
- 礼節と音楽
-
- 神 明
- 天満宮の神様
-
- 不 管
- かかわりが無い 無頓着
-
- 儼 然
- おごそかなさま
意解
太宰府の町を取り囲む山々には今にも春霞がかかろうとしている。道真公を祠(まつ)る天満宮はこの青々とした宝満山の前に鎮座している。
庭の梅は時として色といい香りといい清く潔白な気をもらし、石室の蔵には儒家の書である多くの詩歌礼楽の書物が保存されている。
昔太宰府庁であった都府楼の姿は今は無く(礎石だけが残っていて時々掘り出される)残り瓦を見ると怨めしい感じがし、(菅公が毎日拝した)観音寺は静かにたたずみ、その古い鐘の音を聞けば憐れを感ずる。
天満宮の神様はその後の興衰には無頓着でいらっしゃるが、道真公のお祭りは千年後も厳かに行われている。
備考
この詩の構造は仄起こり七言律詩の形であって、下平声一先(せん)韻の煙、前、編、憐、然の字が使われている。
| 尾聯 | 頸聯 | 頷聯 | 首聯 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者略伝
吉嗣鼓山 ?-1958
太宰府祠畔に住み、南画家拝山の子として父の後をうけ、二代に亙(わた)る南画の大家であり、詩も巧みであった。昭和33年(1958)4月19日没す。
