漢詩紹介
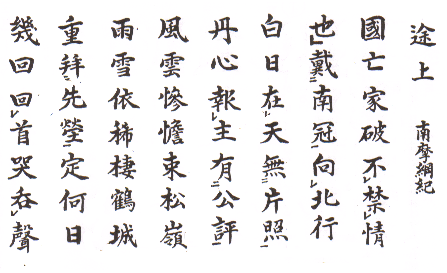
読み方
- 途上<南摩綱紀>
- 國亡び家破れて 情に禁えず
- 也南冠を戴き 北に向かって行く
- 白日天に在って 片照無く
- 丹心主に報ゆる 公評有り
- 風雲惨憺たり 束松嶺
- 雨雪依稀たり 棲鶴城
- 重ねて先塋を拜するは 定めて何れの日ぞ
- 幾回か首を回らして 哭して聲を呑む
- とじょう<なんまつなのり>
- くにほろびいえやぶれて じょうにたえず
- またなんかんをいただき きたにむかってゆく
- はくじつてんにあって へんしょうなく
- たんしんしゅにむくゆる こうひょうあり
- ふううんさんたんたり そくしょうれい
- うせついきたり せいかくじょう
- かさねてせんえいをはいするは さだめていずれのひぞ
- いくかいかこうべをめぐらして こくしてこえをのむ
字解
-
- 國 亡
- 戊辰(ぼしん)戦争(1868)で会津藩が新政府軍に敗れて廃藩
-
- 南 冠
- 南方の地方(楚の国)のかんむり 春秋時代の楚の鐘儀(しょうぎ)が南冠して晉に捕えられた故事から捕虜を言う
-
- 公 評
- 私見を交えない公平な批評
-
- 束松嶺
- 奥州街道二本松にある嶺
-
- 依 稀
- ぼんやりしている
-
- 棲鶴城
- 鶴ケ城
-
- 先 塋
- 先祖の墓
意解
戊辰戦争でわが会津藩は敗(やぶ)れ、一家も滅び君臣父子散りぢりとなり、本当に悲しみの情に耐えない。さらにまた囚われの身となって下北半島に向かって行くのである。
太陽は天にあって人々を公平に照らすものだから、一時賊軍と呼ばれても、我らの誠の心はご主君に報いたいという大義から発したことで、いずれ公平で正しい批評があるだろう。
さて故郷を出て束松嶺にさしかかると風雲が激しく、雨や雪もちらつきはじめ、鶴ケ城はぼんやりとしか見えない。
いつになったら赦(ゆる)されて再び先祖の墓参りができるのだろうかなどと考えながら、幾度も故郷の方を振り返っては、声を殺して泣いたのである。
備考
慶応3年(1867)討幕派は王政復古を宣言、翌年新政府軍と幕府軍は鳥羽伏見で戦い幕府軍は敗れる。会津藩も敗れて故郷を離れ北方に旅立つ道すがらこの詩を作る。
この詩の構造は平起こり七言律詩の形であって、下平声八庚(こう)韻の情、行、評、城、聲の字が使われている。
| 尾聯 | 頸聯 | 頷聯 | 首聯 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者略伝
南摩綱紀 1823-1909
会津藩士(福島県)で号は羽峰(うほう)。昌平黌に学び秀才で詩文に長じた。文久2年に代官となり、のち藩校の教授となったが維新の際に越後の高田に禁錮の身となる。その後許され明治政府に仕え東京大学高等師範の教授となった。明治42年4月没す。年87。著書数編を残している。
