漢詩紹介
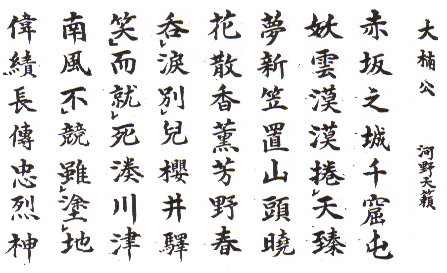
読み方
- 大楠公<河野天籟>
- 赤坂の城 千窟の屯
- 妖雲漠漠 天を捲いて臻る
- 夢は新たなり 笠置山頭の曉
- 花は散り香は薫る 芳野の春
- 涙を呑んで兒に別る 櫻井の驛
- 笑って死に就く 湊川の津
- 南風競わず 地に塗ると雖も
- 偉績長えに傳う 忠烈の神
- だいなんこう<こうのてんらい>
- あかさかのしろ ちはやのたむろ
- よううんばくばく てんをまいていたる
- ゆめはあらたなり かさぎさんとうのあかつき
- はなはちりかはかおる よしののはる
- なみだをのんでこにわかる さくらいのえき
- わらってしにつく みなとがわのしん
- なんぷうきそわず ちにまみるといえども
- いせきとこしえにつとう ちゅうれつのかみ
字解
-
- 大楠公
- 鎌倉末期の武将楠木正成(まさしげ) 後醍醐天皇の南朝再建に尽力した
-
- 赤坂之城
- 楠木正成が挙兵した城 河内の国金剛山にあり 北条氏の大軍を迎撃した
-
- 千窟屯
- 赤坂城と同じ山にある城 正成が籠城した
-
- 妖 雲
- 怪しい気配の雲 北条軍を暗示する
-
- 夢 新
- 「太平記」によると元弘元年後醍醐天皇が笠置山に移られたとき 本殿の南にある大樹の南の枝がこと に繁り天子を護り救うのは楠姓だという霊験がある夢をご覧になったとある
-
- 笠置山
- 1331年後醍醐天皇が逃れた地 京都府相楽郡笠置町にある山
-
- 櫻井驛
- 大阪府三島郡島本町桜井にある地名 ここで正成・正行(まさつら)の親子が今生の別れをした
-
- 湊 川
- 神戸市兵庫区にある ここで正成・正季(まさすえ)が足利勢と戦い戦死した
-
- 塗 地
- 敗れ去る
意解
赤坂・千早の城は楠木氏の堅固な居城であった。そこに怪しい気配の雲が広がって天を覆ってやってきた。(北条側の大軍が侵入してきた)
(これに先立ち天皇は正成を味方につけるべしという)夢を笠置山に逃れたある早朝ご覧になった。そして桜花が散り香りが漂う吉野山でお亡くなりになるまで正成の誠忠は続いた。
桜井の駅で正成は涙を呑んで正行と訣別し、(みずからは足利軍を迎撃せんと、敗戦を承知で)笑って死地に赴き、湊川のほとりで戦死した。
南朝側の勢力は振るわず、遂に敗れ去ったとはいっても、大楠公の偉業はとこしえに忠烈の神として仰ぎ伝えられている。
備考
この詩は、歴史に造詣(ぞうけい)の深い作者が、楠公六百年祭に際し、大楠公の偉勲をたたえて作ったものである。
詩の構造は仄起こり七言律詩の形であって、上平声十三元(げん)韻の屯と上平声十一眞(しん)韻の臻、春、津、神の字が通韻して使われている。
| 尾聯 | 頸聯 | 頷聯 | 首聯 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者略伝
河野天籟 1861-1941
熊本県玉名(たまな)郡長洲町(ながすまち)の人。名を通雄(みちお)といい、天籟は号。熊本師範学校を卒業後小学校長を歴任し作詩に志すこと40年、詩賦自由自在にして漢詩百余篇を蒐録(しゅうろく)した「孟浪餘滴」(もうろうよてき)の冊子を著す。昭和16年5月没す。年80。
参考
1318 後醍醐天皇即位
1324 討幕運動の始まり(正中=しょうちゅう=の変)
この頃正成は赤坂・千早城で北条氏と対戦
1331 2回目倒幕を試みるが失敗(元弘の変)
天皇は笠置山で捕らえられ、隠岐に流罪
1333 鎌倉幕府滅亡
1334 建武の中興後醍醐天皇の親政開始(2年間)
勲功により楠木正成を河内の国守に任命
1335 足利尊氏天皇政治に反逆開始
1336 足利尊氏挙兵天皇は比叡山に逃れる その後吉野に遷宮
湊川の戦 九州から再上洛の足利勢と対戦し正成戦死
1338 尊氏征夷大将軍となる
1339 天皇が吉野で病没 尊氏は冥福を祈り天龍寺を建立
1348 四条畷の合戦 楠木正行が尊氏の執事の高師直と戦い戦死
