漢詩紹介
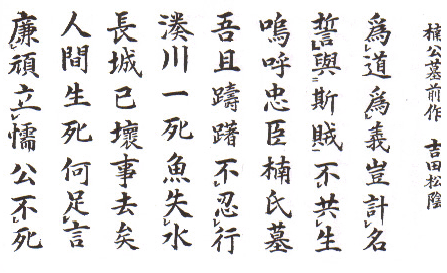
読み方
- 楠公墓前の作<吉田松陰>
- 道の爲義の爲 豈名を計らんや
- 誓って斯の賊と 生を共にせず
- 嗚呼忠臣 楠氏の墓
- 吾れ且く躊躇して 行るに忍びず
- 湊川の一死は 魚水を失う
- 長城已に壞れて 事去りぬ
- 人間の生死 何ぞ言うに足らんや
- 頑を廉にし懦を立つる 公は死せず
- なんこうぼぜんのさく<よしだしょういん>
- みちのためぎのため あになをはからんや
- ちかってこのぞくと せいをともにせず
- ああちゅうしん なんしのはか
- われしばらくちゅうちょして さるにしのびず
- みなとがわのいっしは うおみずをうしのう
- ちょうじょうすでにこわれて ことさりぬ
- にんげんのせいし なんぞいうにたらんや
- がんをれんにしだをたつる こうはしせず
字解
-
- 道
- 人間として行うべき条理
-
- 義
- 君臣の間の道徳精神 仁・義・礼・智・信の五常の一つ
-
- 豈
- 豈…せんやと読む反語の詞 どうして…しようか決してしない
-
- 且
- 少しの間
-
- 躊 躇
- ためらう
-
- 長 城
- 足利を仆(たお)し王政復古したこと
-
- 廉 頑
- 「頑」はかたくな おろか 「廉」は行いの正しい
-
- 立 懦
- 「懦」は臆病 臆病な者を奮い立たせる
意解
楠公は道義のため王事に尽くしたのであって、どうして自分の名声を挙げんが為に事を起こそうとしただろうか、いや決してそうではない。この逆賊とはこの世では生を共にしないと誓ったのである。
今、嗚呼忠臣楠氏之墓に詣で(当時の事を追想し、気高い忠義の精神に胸をうたれ)少しの間ためらって立ち去るのに忍びない。
湊川での楠公の戦死は、魚が水を失ったように、回天の事業(建武の中興)が壊れてしまった。
人間の生死というものは、言うに足りないものだが、楠公の精神は、愚かな者を正しく導き、勇気のない者たちを奮い立たせ、いつまでも生き続け決して死んではいないのである。
備考
1851年(嘉永4年)3月、藩主江戸行の先発として江戸へ向かう途中、湊川の楠木正成の墓に詣で、その墓前で作る。21歳の作。
この詩は20句からなる古詩の前8句であり、下平声八庚(こう)韻の名、生、行と上声四紙(し)韻の水、矣、死の字が使われている。
- 如今朝野 雷同を悦び
- 僅に圭角有れば 乃ち容れず
- 書を讀んで已に 道を衛るの志無し
- 事に臨んで寧ぞ 義を取るの功有らんや
- 君見ずや満清全盛 宇内に甲たり
- 乃ち幺麼の 破砕する所と爲る
- 江南十萬 竟に何をか爲す
- 陳公之外 狗鼠の輩のみ
- 安んぞ楠公 其の人の如きを得ん
- 弊習を洗盡して 一新令めん
- 獨り碑前に跪いて 三たび歎息す
- 満腔の義膽 空しく輪囷
- じょこんちょうや らいどうをよろこび
- わずかにけいかくあれば すなわちいれず
- しょをよんですでに みちをまもるのこころざしなし
- ことにのぞんでいずくんぞ ぎをとるのこうあらんや
- きみみずやまんしんぜんせい うだいにこうたり
- すなわちようまの はさいするところとなる
- こうなんじゅうまん ついになにをかなす
- ちんこうのほか くそのやからのみ
- いずくんぞなんこう そのひとのごときをえん
- へいしゅうをせんじんして いっしんせしめん
- ひとりひぜんににひざまづいて みたびたんそくす
- まんこうのぎたん むなしくりんきん
作者略伝
吉田松陰 1830-1859
江戸時代末期、萩藩士(山口県)杉百合之助の次男として生まれた。幼名を大次郎、通称寅次郎、名は矩方(のりかた)、字を義卿(ぎきょう)、松陰または二十一回猛士と号す。6歳のとき叔父吉田了賢の養子となり、山鹿流兵学を学ぶ。11歳のときには藩主毛利敬親(たかちか)の御前で武教全書を講義する。勤王の志が厚く、佐久間象山に師事した。ペリー再来の時、密航を企てて下獄。その後萩の自邸内に松下村塾を開いて子弟の教育にあたる。その門下には明治維新の大業達成に活躍した高杉晋作・久坂玄瑞・伊藤博文らがいる。安政の大獄に連座し小塚原で刑死した。年29。
