漢詩紹介
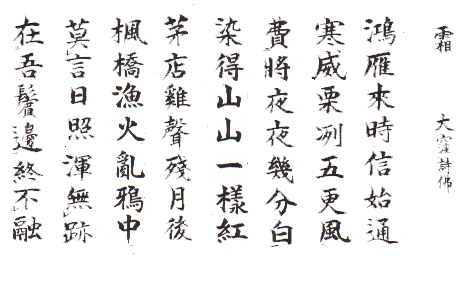
読み方
- 霜<大窪詩佛>
- 鴻雁來る時 信始めて通ず
- 寒威栗冽たり 五更の風
- 夜夜幾分の 白を費し將て
- 染め得たり山山 一樣の紅
- 茅店の鷄聲 殘月の後
- 楓橋の漁火 亂鴉の中
- 言うこと莫れ日照らせば 渾て跡無しと
- 吾が鬢邊に在っては 終に融けず
- しも<おおくぼしぶつ>
- こうがんきたるとき しんはじめてつうず
- かんいりつれつたり ごこうのかぜ
- ややいくぶんの はくをついやしもって
- そめえたりさんざん いちようのくれない
- ぼうてんのけいせい ざんげつののち
- ふうきょうのぎょか らんあのうち
- いうことなかれひてらせば すべてあとなしと
- わがびんへんにあっては ついにとけず
字解
-
- 寒威栗冽
- 寒さのきびしいさま
-
- 五 更
- 午前4時ごろ 夜明け前
-
- 費 白
- 白さを加える
-
- 茅 店
- かやぶきの家 田舎の茶店 温庭<竹かんむりに均>(おんていいん)の詩に「鶏声茅店月 人迹板橋霜」にもとづく
-
- 楓 橋
- 橋の名 張繼の詩に「月落烏啼霜満天 江楓漁火對愁眠」にもとづく
-
- 亂 鴉
- からすの啼き声
意解
雁が飛んでくる頃になると、霜の便りもそろそろ聞かれて、夜明け前の風はとりわけ寒く身にしみる。
夜毎に霜の白さも少しずつ加わり、山々の樹木は一様に紅(あか)さを増している。
(昔中国の詩人が)鶏の声に目覚めて茅ぶきの茶店を夜明けの月が残っているうちに出てみると、人の足跡が既に板橋の霜に残されていたとか、また鴉の鳴く霜の夜に楓橋の漁火に対して眠れなかったと詠んでいる。
その霜も、日が昇れば忽ち跡もなく消えてしまうなどと、そのようなことを言ってはなりません。吾が頭上にふる霜は髪を白く染めていつまでも融けることがないのだから。
備考
この詩の構造は、仄起こり七言律詩の形であって、上平声一東(とう)韻の通、風、紅、中、融の字が使われている。
| 尾聯 | 頸聯 | 頷聯 | 首聯 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者略伝
大窪詩佛 1767-1837
徳川中期の漢詩人。明和(めいわ)4年、常陸(ひたち=茨城県)多賀郡大久保村に生まれる。通称柳太郎、名は行光(ゆきみつ)、字は天民、詩佛は号、また痩梅(そうばい)、詩聖堂の別号あり。江戸に移り住み、諸州に遊び京師の頼山陽をも訪ねた。草書と詩を以て名高く、市河寛斎(かんさい)、柏木如亭(じょてい)、菊池五山(ござん)と共に江戸の四詩家と称せられる。習性洒脱、谷文晁(ぶんちょう)と親交あり、好んで墨竹を画(えが)き甚だ気韻に富む。天保8年2月に没す。年71。相州(神奈川県)藤沢に葬る。著書に「詩聖堂詩集」その他多数の詩集がある。
