漢詩紹介
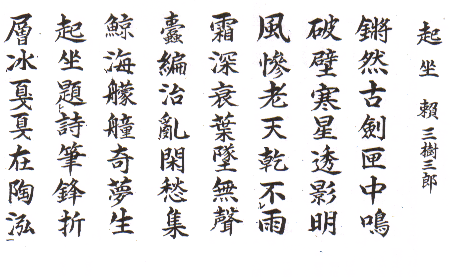
読み方
- 起坐<賴三樹三郎>
- 鏘然として古劍 匣中に鳴る
- 破壁寒星 透影明らかなり
- 風慘として老天 乾きて雨ふらず
- 霜深くして衰葉 墜ちて聲無し
- 蠹編の治亂 閑愁集まり
- 鯨海の艨艟 奇夢生ず
- 起坐して詩を題せんとすれば 筆鋒折る
- 層冰戛戛として 陶泓に在り
- きざ<らいみきさぶろう>
- そうぜんとしてこけん こうちゅうになる
- はへきかんせい とうえいあきらかなり
- かぜさんとしてろうてん かわきてあめふらず
- しもふかくしてすいよう おちてこえなし
- とへんのちらん かんしゅうあつまり
- げいかいのもうどう きむしょうず
- きざしてしをだいせんとすれば ひっぽうおる
- そうひょうかつかつとして とうおうにあり
字解
-
- 鏘 然
- 玉や金属が打ちあって澄んだ音を出すさま
-
- 匣 中
- 小さい箱の中
-
- 風 慘
- 風がきびしく吹く
-
- 老 天
- 歳の暮れの天気
-
- 蠹 編
- むしばんだ書き物 古書
-
- 閑愁集
- 愁いが胸にせまる
-
- 鯨 海
- 鯨の住む海 大海 ここでは日本の近海
-
- 艨 艟
- 軍艦
-
- 層 冰
- 氷の張りつめたさま
-
- 戛 戛
- コツコツという音
-
- 陶 泓
- 陶器製の硯 硯のこと
意解
夜中に箱の中の剣が打ちあっている音を聞いて目が覚めた。破れた壁の隙間からは星が寒々と輝いて見える。
風はきびしく吹き、歳の暮れの天気は雨も降らず乾ききって、霜が深いため葉は自然に落ちて音もたてない。
眠れぬままに古い書物を読みながら、世の興亡のあとをたどっていると愁いが胸にせまってくる。いま日本の近海には異国の軍艦が出没しているというふしぎな夢を見た。(しかし、幕府にこの対策をとる能力がないのは非常に残念である)
(我が国の今の力ではどうしようもないが)起き上がって、この思いを筆をとって詩にしたためようとしたが、筆の穂先は折れており、また硯の水もコチコチに凍っていて書くこともできない。(国の前途を憂うる作者の気概がほとばしっている)
備考
この詩の構造は平起こり七言律詩の形であって、下平声八庚(こう)韻の鳴、明、聲、生、泓の字が使われている。
| 尾聯 | 頸聯 | 頷聯 | 首聯 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者略伝
賴三樹三郎 1825-1859
賴山陽の第三子として京都三本木町に生まれる。幕末の詩人。名は醇(じゅん)、字は子春(ししゅん)、通称は三樹または三樹三郎と称し、鴨厓・古狂生と号した。18歳の時江戸に遊学し昌平黌(しょうへいこう)にて学ぶ傍ら佐藤一斎・梁川星巖などと交流し精研する。勤王の志(こころざし)厚く京都に帰り星巖・梅田雲浜らと尊皇攘夷の大策を画(かく)するも安政の大獄に捕らわれ吉田松陰、橋本左内などと共に安政6年10月小塚原で刑死す。その刑に臨むや従容として一首賦す(B-9号・獄中作)。年35。
