漢詩紹介
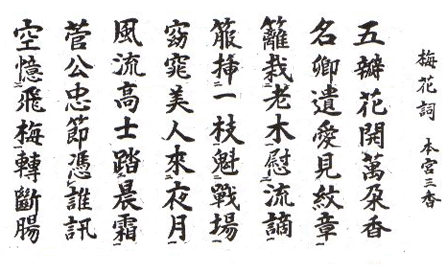
読み方
- 梅花の詞<本宮三香>
- 五瓣花開いて 萬朶香し
- 名卿の遺愛 紋章を見る
- 籬に老木を栽えて 流謫を慰め
- 箙に一枝を插んで 戰場に魁す
- 窈窕たる美人 夜月に來り
- 風流の高士 晨霜を踏む
- 菅公の忠節 誰に憑って訊ねん
- 空しく飛梅を憶うて 轉斷腸
- ばいかのし<もとみやさんこう>
- ごべんはなひらいて ばんだかんばし
- めいけいのいあい もんしょうをみる
- まがきにろうぼくをうえて るたくをなぐさめ
- えびらにいっしをはさんで せんじょうにさきがけす
- ようちょうたるびじん やげつにきたり
- ふうりゅうのこうし しんそうをふむ
- かんこうのちゅうせつ たれによってたずねん
- むなしくひばいをおもうて うたただんちょう
字解
-
- 萬 朶
- 多くの小枝
-
- 名 卿
- 名高い公卿 ここでは菅原道真公
-
- 遺 愛
- 生前大切にして遺(のこ)したもの
-
- 紋 章
- 家紋の図柄
-
- 箙
- 背に負う矢を入れる武具 平家物語に梶原景季(かげすえ)が背に負うた武具に梅の一枝を入れて 生田の森で戦った故事がある
-
- 窈 窕
- 奥ゆかしく上品 この句は次の句とともに高啓の「梅花」の詩句を踏まえている
-
- 高 士
- 高潔な男性
-
- 晨 霜
- 早朝の霜
-
- 斷 腸
- 悲痛な思い
意解
梅の花は五弁の花びらが開いて多くの小枝は芳しく、菅原道真公も生前梅を愛され、その紋章とされた。
道真公は垣根に梅の老木を植えられて流謫の愁いを慰められたというし、梶原景季は背負った箙に梅の一枝を挿して生田の戦場で一番乗りを果たされたという。
(梅の姿を喩=たと=えれば)奥ゆかしく上品な美人が夜の月下に訪ねてくるようでもあり、風流で高潔な男性が早朝の霜を踏みながら逍遙するようでもある。
太宰府に左遷された道真公の忠義心は今となっては誰に向かって尋ねたらよかろうか、それもかなわないのでいたずらに彼の飛梅の故事を思えばいよいよ腸もちぎれるばかりに悲痛な思いがする。
備考
この詩の構造は仄起こり七言律詩の形であって、下平声七陽(よう)韻の香、章、場、霜、腸の字が使われている。
| 尾聯 | 頸聯 | 頷聯 | 首聯 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者略伝
本宮三香 1878-1954
明治11年10月31日千葉県香取郡津宮村(現佐原市津宮=さわらしつのみや)に生まれる。名は庸三(ようぞう)、字は子述(しじゅつ)、別に風土子(ふうどし)と称し、三香は号。幼にして漢学漢詩を学ぶ。日露の役に従軍、第三軍に属し戦場でも詩を作る。39年凱戦後故山に帰り悠々自適の生活を楽しむ。大正2年「江南吟社」を設立、のち水郷吟詠会を組織し木村岳風の日本詩吟学院の講師を委嘱されるなど作詩及び詩吟の普及に力を傾けた。 作詩5千、酒と詩を愛した。昭和29年12月29日没す。年77。
