漢詩紹介
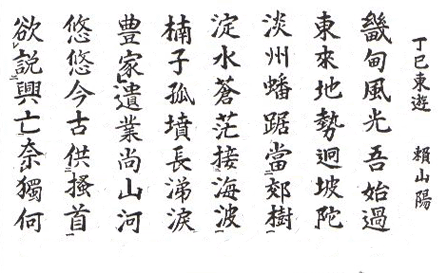
読み方
- 丁巳東遊<賴山陽>
- 畿甸の風光 吾始めて過ぐ
- 東來の地勢 迥かに坡陀たり
- 淡州は蟠踞して 郊樹に當たり
- 淀水は蒼茫として 海波に接す
- 楠子の孤墳に 長く涕涙し
- 豊家の遺業は 尚山河
- 悠悠たる今古 掻首に供す
- 興亡を説かんと欲すれど 獨りを奈何せん
- ていしとうゆう<らいさんよう>
- きでんのふうこう われはじめてすぐ
- とうらいのちせい はるかにはだたり
- たんしゅうはばんきょして こうじゅにあたり
- でんすいはそうぼうとして かいはにせっす
- なんしのこふんに ながくているいし
- ほうかのいぎょうは なおさんが
- ゆうゆうたるこんこ そうしゅにきょうす
- こうぼうをとかんとほっすれど ひとりをいかんせん
字解
-
- 丁 巳
- ひのとみ 1797年
-
- 東 遊
- 江戸の昌平黌への遊学の旅
-
- 畿 甸
- 王城(京都・奈良)を中心として四方500里以内の地域 畿内
-
- 坡 陀
- 斜めに傾いて平らかでないさま
-
- 蟠 踞
- とぐろを巻いてうずくまる
-
- 楠 子
- 楠公 「子」は尊称
-
- 坡 陀
- 斜めに傾いて平らかでないさま
-
- 孤 墳
- ぽつんとある墓
-
- 豊 家
- 豊臣家
-
- 掻 首
- 頭を掻(か)く 心の落ち着かないときの動作
-
- 奈 何
- どのようにしたらよいか
意解
初めて畿内にやってきてその風光を眺めると、芸州より東の国々の地形は斜めに傾いていて平らかでなく高低が続いている。
淡路島は竜がとぐろを巻いてうずくまるように、大阪湾岸の松林の近くにせまっており、淀川は青々として海の波に流れ込んでいる。
湊川神社にぽつんとある楠公のお墓の前で多くの行き交う人たちがいつまでも涙を流し、豊臣家の遺した大事業である大阪城はいまなお山河とともに存在している。
こうしてはるかに遠い歳月の昔から今日まで、有為転変(ういてんぺん)をふりかえってみればどうしても頭を掻くようで落ち着かなく、興亡の跡を人々に説こうと思っても、自分ひとりではどうすることもできない。
備考
1797年(寛政9年)賴山陽18歳の時叔父の賴杏坪が江戸詰めになったので、伴われて江戸に遊学した。その際「丁巳東遊」6首を作り、その第1首である。
この詩の構造は仄起こり七言律詩の形であって、下平声五歌(か)韻の過、陀、波、河、何の字が使われている。
| 尾聯 | 頸聯 | 頷聯 | 首聯 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者略伝
賴 山陽 1780-1832
名は襄(のぼる)、字は子成(しせい)、号は山陽。安永9年12月大坂江戸堀に生まれた。父春水は安芸藩の儒者。7歳の時叔父杏坪について書を読み、18歳で江戸に遊学した。21歳京都に走り脱藩の罪により幽閉される。のち各地を遊歴し天保3年9月病のため没す。年53。 著書に「日本外史」「日本政記」「日本楽府(がふ)」などがある。
