漢詩紹介
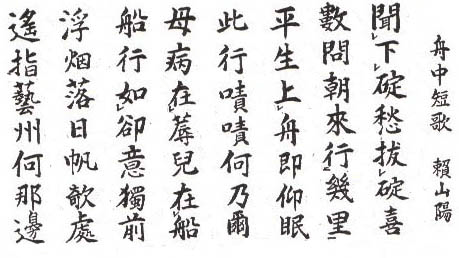
読み方
- 舟中短歌<賴 山陽>
- 碇を下すを聞いては愁い 碇を拔いては喜ぶ
- 數問う朝來 幾里をか行くと
- 平生舟に上れば 即ち仰眠す
- 此の行嘖嘖 何ぞ乃ち爾る
- 母病んで蓐に在り 兒は船に在り
- 船行卻くが如く 意獨り前む
- 浮烟落日 帆の欹つ處
- 遙かに指さす藝州 何那の邊ぞ
- しゅうちゅうたんか<らいさんよう>
- いかりをおろすをきいてはうれい いかりをぬいてはよろこぶ
- しばしばとうちょうらい いくりをかゆくと
- へいぜいふねにのぼれば すなわちぎょうみんす
- このこうさくさく なんぞすなわちしかる
- ははやんでしとねにあり じはふねにあり
- せんこうしりぞくがごとく いひとりすすむ
- ふえんらくじつ ほのそばだつところ
- はるかにゆびさすげいしゅう いずれのへんぞ
字解
-
- 短 歌
- 四句以上十句までの短い詩
-
- 朝 來
- 朝から
-
- 此 行
- このたびの旅行
-
- 嘖 嘖
- 口数が多い
-
- 爾
- そうである
-
- 蓐
- ここでは病床
-
- 浮 烟
- かすみ
-
- 藝 州
- 今の広島市を中心とした地方
-
- 邊
- あたり
意解
港に入って碇を下して船泊まりをすると聞いては、帰郷が遅れることを案じ、碇を捲(ま)き上げて出航すると聞いては安心するが、(船足が遅いので)朝から幾度もどれくらいの里程を走ったかと船頭たちに尋ねる。
日ごろは船に乗るとすぐに仰向けに眠ってしまうのに、この船旅では、船客と口数多く話したりして過ごすが、どうしてそうなってしまうのだろうか。(母のことが気になってしかたがない)
母上が故郷で病床にあり、自分は船で帰郷しつつあるが、(自分の気持ちとはうらはらに)船足は後退するように思えるほど遅く、自分の気持ちだけがはやる。
行く手に夕日が霞の中に沈もうとするころ、帆船の姿が見えるが、はるか遠くを指差して故郷の芸州はどのあたりであろうかと思うのである。
備考
この詩は1830年(天保元年)6月7日、母の病気を聞いて京都を出発し、6月下旬広島に帰る時の舟中 での作である。
詩の構造は七言古詩の形であって、上声(仄韻)四紙(し)韻の喜、里、爾と下平声一先(せん)韻の船、前、邊の字が使われている。
作者略伝
賴 山陽 1780-1832
名は襄(のぼる)、字は子成(しせい)、号は山陽。安永9年12月大坂江戸堀に生まれた。父春水は安芸藩の儒者。7歳の時叔父杏坪について書を読み、18歳で江戸に遊学した。21歳京都に走り脱藩の罪により幽閉される。のち各地を遊歴し天保3年9月病のため没す。年53。 著書に「日本外史」「日本政記」「日本楽府(がふ)」などがある。
