漢詩紹介
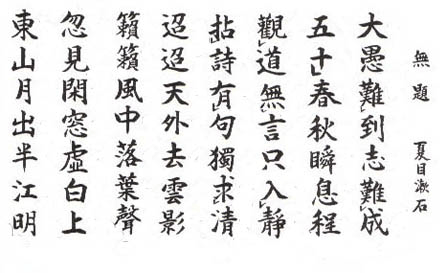
読み方
- 無題<夏目漱石>
- 大愚到り難く 志成り難し
- 五十の春秋 瞬息の程
- 道を觀じて言無く 只靜に入り
- 詩を拈じて句有り 獨り清を求む
- 迢迢たる天外 去雲の影
- 籟籟たる風中 落葉の聲
- 忽ち見る閑窓 虚白の上
- 東山月出でて 半江明らかなり
- むだい<なつめそうせき>
- たいぐいたりがたく こころざしなりがたし
- ごじゅうのしゅんじゅう しゅんそくのてい
- みちをかんじてことばなく ただせいにいり
- しをねんじてくあり ひとりせいをもとむ
- ちょうちょうたるてんがい きょうんのかげ
- らいらいたるふうちゅう らくようのこえ
- たちまちみるかんそう きょはくのうえ
- とうざんつきいでて はんこうあきらかなり
字解
-
- 大 愚
- 真の愚か者 荘子に「其の愚を知る者は大愚にあらず」とある
-
- 春 秋
- 年月 1年
-
- 瞬息程
- 瞬(まばた)いたり息をしたりするほどの短い時間
-
- 觀 道
- 道を考える 「道」は孔子のいう人の道ではなく 荘子のいう万物が生成流転するという宇宙の法則の道
-
- 拈 詩
- 詩をひねり出す
-
- 迢 迢
- 遠くはるかなさま
-
- 籟 籟
- 「籟」はもと簫に似た楽器 ここでは響きあう音
-
- 忽 見
- ふと見る
-
- 虚 白
- むなしい うつろな
-
- 半 江
- 川の半分
意解
真の愚か者にもなりきれず、志も成就することは難しいと思いつつ50年の年月は瞬(またた)く間にすぎてしまった。
いま万物が生成流転するという宇宙の法則の道を考えてみるとき、言うべき言葉もなく、無心の境に入り、詩をひねりだしては句を作り、ただ汚れのない清い心でありたいと願うばかりである。
はるか遠い大空に去り行く雲の姿を目にし、響きあう風の中に落ち葉の声を耳にする。
誰もいない窓辺でうつろな気持ちでいると、東の山に月が昇り、川のなかばを明るく照らしているのがふと目に入った。
備考
夏目漱石には、1916年(大正5年)8月14日から11月20日までに七言律詩64首の連作があり、この詩は63首にあたり、11月19日の作である。この詩の構造は、平起こり七言律詩の形であって、下平声八庚(こう)韻の成、程、清、聲、明の字が使われている。
| 尾聯 | 頸聯 | 頷聯 | 首聯 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者略伝
夏目漱石 1867-1916
慶応3年1月江戸牛込に生まれる。幼名を金之助という。明治・大正時代の小説家、英文学者。生家貧しくして、度々里子にだされた。 二松学舎、成立学舎に学んで、漢学・英語を学ぶ。東京大学英文学科卒。イギリスに留学、のち東大講師、朝日新聞社に入社。
「坊ちゃん」「吾輩は猫である」をはじめ数々の名作を残し大正5年12月没す。年50。
参考
呼び名について
(その1)
①幼名 元服に至るまでの一時的な名
②実名 昔社会的に独立した人格として待遇される元服の日につけられた終生の名
(例)西郷隆盛幼名は吉之助実名は隆盛
③通称 通常呼ばれる名俗称一般に通用するよび方
(例)賴襄通称は久太郎号は山陽
④字(あざな) 世に一人前の人として交わるときの名元服のとき実名のほかにつける
(例)賴襄字は子成
