漢詩紹介
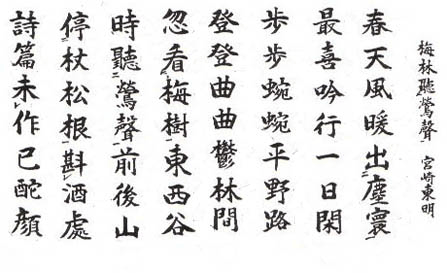
読み方
- 梅林鶯聲を聽く<宮崎東明>
- 春天風暖かにして 塵寰を出ず
- 最も喜ぶ吟行 一日の閑
- 歩歩蜿蜿 平野の路
- 登登曲曲 鬱林の間
- 忽ち梅樹を看る 東西の谷
- 時に鶯聲を聽く 前後の山
- 杖を松根に停めて 酒を斟む處
- 詩篇未だ作らず 已に酡顔
- ばいりんおうせいをきく<みやざきとうめい>
- しゅんてんかぜあたたかにして じんかんをいず
- もっともよろこぶぎんこう いちじつのかん
- ほほえんえん へいやのみち
- とうとうきょくきょく うつりんのあいだ
- たちまちばいじゅをみる とうざいのたに
- ときにおうせいをきく ぜんごのやま
- つえをしょうこんにとどめて さけをくむところ
- しへんいまだならず すでにだがん
字解
-
- 塵 寰
- 塵の世 俗世間
-
- 蜿 蜿
- うねりくねるさま
-
- 鬱 林
- こんもり茂る林
-
- 忽
- ふと
-
- 聽
- 聞こうとして聞く
-
- 酡 顔
- 酒に酔った顔
意解
春日和で風も暖かくなって俗世間から出ることにした。詩を作りながら一日のどかに出歩くのはこの上もない喜びである。
平野の道を一歩一歩うねりくねりしながら進み、こんもり茂った林の中を折れ曲がりながらぼつぼつ登りつづけていった。
ふと、東西の谷間に梅林が目に入り、折しも前後の山々から鶯の声がして耳を傾けた。
私は杖を松の根もとに置いて休み、酒を酌んでいると、思う詩がまだできていないうちにもう酔ってしまった。
備考
この詩の構造は平起こり七言律詩の形であって、上平声十五刪(さん)韻の寰、閑、間、山、顔の字が使われている。
| 尾聯 | 頸聯 | 頷聯 | 首聯 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者略伝
宮崎東明 1889-1969
名は喜太郎、東明は号。明治22年3月河内国四條村野崎(現在の大東市)に生まれる。京都府立医学専門学校を卒業、大阪玉川町に医院を開く。医業のかたわら詩を藤澤黄坡(ふじさわこうは)、書を臼田岳洲(うすだがくしゅう)、画を中国人方(ほうめい)、篆刻(てんこく)を高畑翠石(たかはたすいせき)、吟詩を眞子西洲(まなごさいしゅう)の各先生に学び、その居を五楽庵と称した。昭和9年関西吟詩同好会(現、公益社団法人関西吟詩文化協会)を創設し、昭和23年、藤澤黄坡初代会長没後二代目会長に就任。昭和44年9月18日没す。年82。
参考
呼び名について(その2)
⑤号 本名・通称・字のほかにつけた名で雅号ともいう文人・画家・書家などが実名以外につける風雅な名
⑥諱(いみな) 死者の名生きている時は実名といい死んでからは諱と言う
⑦謚(おくりな) 死者に対し生前の功績を讃え贈る名
(例)程明道謚は純公
