漢詩紹介
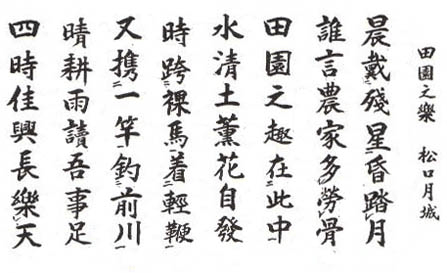
読み方
- 田園の樂しみ<松口月城>
- 晨に殘星を戴き 昏には月を踏む
- 誰か言う農家 骨を勞すること多しと
- 田園の趣 此の中に在り
- 水清く土薫り 花自ずから發く
- 時には裸馬に跨り 輕鞭を着け
- 又一竿を携えて 前川に釣る
- 晴耕雨讀 吾が事足る
- 四時の佳興 長く天を樂しむ
- でんえんのたのしみ<まつぐちげつじょう>
- あしたにざんせいをいただき くれにはつきをふむ
- たれかいうのうか ほねをろうすることおおしと
- でんえんのおもむき このうちにあり
- みずきよくつちかおり はなおのずからひらく
- ときにはらばにまたがり けいべんをつけ
- またいっかんをたずさえて ぜんせんにつる
- せいこううどく わがことたる
- しじのかきょう ながくてんをたのしむ
字解
-
- 晨
- 早朝 夜明け前
-
- 裸 馬
- 鞍のついていない馬
-
- 鞭
- 馬の鞭
-
- 四 時
- 一年中
-
- 佳 興
- すばらしい趣
意解
夜明け前から残り星を仰ぎ見、夕暮れには月の光を踏む頃まで働くので、農家の仕事は骨をおって苦労をすることが多いと誰かが言った。
しかし田園生活の中での趣というのはこういう生活の中にあるのであって、水は清らかで、土は良い香りがし、四季の花々も自然に咲く。
時には鞍のついていない馬にまたがり軽やかに鞭打って野を駆けめぐり、さらにまた一本の釣りざおを持って小川に糸を垂れる。
晴れたときには耕作に精を出し、雨が降れば読書に親しむという私の日常の営みは申し分なく、一年中のすばらしい趣を我がものにしていつまでも天から授かった生を楽しむのである。
備考
この詩は近体詩の平仄法にかなっていないので七言古詩であり、したがって平仄は問わない。韻は入声( 仄韻)六月(げつ)韻の月、骨、發と下平声一先(せん)韻の鞭、川、天の字が使われている。
作者略伝
松口月城 1887-1981
名は榮太(えいた)、号は月城、明治20年福岡市有田に生まれる。熊本医学専門学校を卒業し、18歳にして医師となり世人を驚かせた秀才である。医業のかたわら漢詩を宮崎来城に学び、詩、書画、共に巧みであった。 なお本会顧問を永年つとめられる。昭和56年7月16日没す。年95。
