漢詩紹介
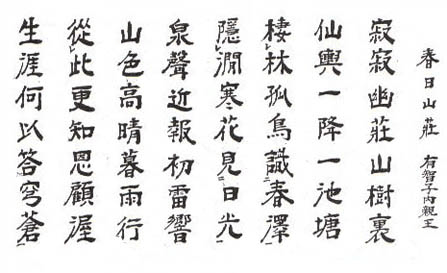
読み方
- 春日山莊<有智子内親王>
- 寂寂たる幽莊 山樹の裏
- 仙輿一たび降る 一池塘
- 林に棲む孤鳥 春澤を識り
- 澗に隱るる寒花 日光を見る
- 泉聲近く報じて 初雷響き
- 山色高く晴れて 暮雨行なる
- 此れ從り更に知る 恩顧の渥きを
- 生涯何を以てか 穹蒼に答えん
- しゅんじつさんそう<うちこないしんのう>
- せきせきたるゆうそう さんじゅのうち
- せんよひとたびくだる いちちとう
- はやしにすむこちょう しゅんたくをしり
- たににかくるるかんか にっこうをみる
- せんせいちかくほうじて しょらいひびき
- さんしょくたかくはれて ぼうつらなる
- これよりさらにしる おんこのあつきを
- しょうがいなにをもってか きゅうそうにこたえん
字解
-
- 幽 莊
- 奥深い山荘 内親王の住む賀茂神社の境内にある
-
- 仙 輿
- 仙人の輿(こし) ここでは天皇の神輿(みこし)
-
- 池 塘
- 池のつつみ
-
- 孤 鳥
- 一羽の鳥 ここでは斎院として寂しく暮らしている作者を暗示する 次句の「寒花」 も同じ
-
- 春 澤
- 春の恵み 天皇の御臨幸を暗示する 次句の「日光」も同じ
-
- 初 雷
- 夏の初めになる雷
-
- 恩 顧
- 天皇の慈愛
-
- 穹 蒼
- 大空 ここでは天皇の御恩沢 「穹」は弓なりの空 「蒼」は青い7
意解
静寂で奥深くうっそうと樹木の茂る山荘に、嵯峨天皇の神輿が池のほとりに御臨幸になった。
林に棲む鳥(私)も春の恵み(天皇の御臨幸)を知って喜び、谷間に隠れるようにひっそり咲いている花も日の光を仰ぎ見ている。
泉の音が近くで、まるで初雷のように響き、山の気配は高く晴れわたり、麓では夕暮れの雨が降っている。
このとき以来、私は天皇の御慈愛がどんなに深いものかを改めて知るのですが、生涯をかけてどのようにして大空のように高く深い御恩沢にお答えしたらよいのでしょうか。
備考
823年(弘仁=こうにん=14年)2月、嵯峨天皇が賀茂神社の斎院の花宴(はなのえん)に行幸された時、「春日山荘」の詩を有智子内親王に作らせた。内親王は17歳であった。
この詩の構造は仄起こり七言律詩の形であって、下平声七陽(よう)韻の塘、光、行、蒼の字が使われており、第一句は踏み落としになっている。
| 尾聯 | 頸聯 | 頷聯 | 首聯 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者略伝
有智子内親王 807-847
平安時代初期の女流詩人。嵯峨天皇の第八皇女で母は交野女王(かたののじょおう)。4歳で賀茂神社の斎院となる。承和14年10月26日没す。年41。墓陵は嵯峨野に在る。
参考
斎院斎宮について
【斎院】 京都賀茂神社の祭祀に奉仕した未婚の内親王、またその居所。天皇即位時に卜定(ぼくじょう)され、その天皇一代の間つとめるのを原則とした。嵯峨天皇の代に斎宮にならって設けられ、後鳥羽(ごとば)天皇の代まで続いた。
【斎宮】 天皇の名代として伊勢神宮に遣わされた内親王で、斉王ともいい、またその居所。天皇が即位すると未婚の内親王から選ばれ、原則として譲位まで仕えた。14世紀の後醍醐(ごだいご)天皇の代まで続いた。
