漢詩紹介
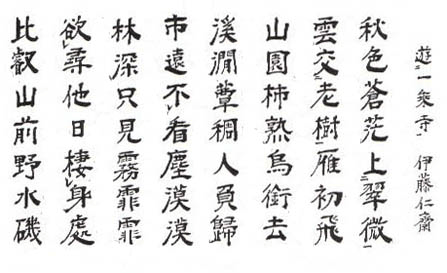
読み方
- 一乘寺に遊ぶ<伊藤仁齋>
- 秋色蒼茫 翠微に上り
- 雲は老樹に交わり 雁初めて飛ぶ
- 山園柿熟し 烏銜んで去り
- 溪澗蕈稠く 人負うて歸る
- 市遠ければ看ず 塵の漠漠たるを
- 林深ければ只見る 霧の霏霏たるを
- 尋ねんと欲す他日 身を棲ましむる處
- 比叡山前 野水の磯
- いちじょうじにあそぶ<いとうじんさい>
- しゅうしょくそうぼう すいびにのぼり
- くもはろうじゅにまじわり かりはじめてとぶ
- さんえんかきじゅくし からすふくんでさり
- けいかんきのこおおく ひとおうてかえる
- まちとおければみず ちりのばくばくたるを
- はやしふかければただみる きりのひひたるを
- たずねんとほっすたじつ みをすましむるところ
- ひえいさんぜん やすいのいそ
字解
-
- 一乘寺
- 京都市左京区一乗寺町 当時山紫水明の地であった
-
- 翠 微
- 山の七・八合目付近 ここでは瓜生山の中腹
-
- 山 園
- 山家の畑
-
- 銜
- 口に含む
-
- 溪 澗
- 谷川
-
- 蕈
- 茸(きのこ)
-
- 漠 漠
- 遠くはるかなさま
-
- 霏 霏
- 深く立ち込めているさま
-
- 野水磯
- 河原
意解
秋の気配はどこまでも広く青々として瓜生山の中腹あたりまで上り、(さらに頂上を仰げば)雲は老樹と交わるように低く垂れて、折から今年はじめて見る雁の群れが列を成して飛んでくる。
(少し歩みを進めると)山家の畑には柿が熟しており、それを烏が口に含んで飛び去ったり、また谷川近くでは茸がたくさん採れるというので、それを背負って帰ったりする人を見かける。
このあたりは町から遠いので車馬や人のあげる塵埃(じんあい)は全く見えず、また林が深いので見えるものといえば深く立ち込める霧ばかりである。
将来、隠棲の地を探すとしたら、比叡山の麓の清澄(せいちょう)な水をたたえた河原のあるこの一乗寺村あたりであろう。
備考
この詩は京都一乗寺村から望む風情を詠じたもので、1697年(元禄10年)仁齋71歳の作といわれる。
詩の構造は仄起こり七言律詩の形であって、上平声五微(び)韻の微、飛、歸、霏、磯の字が使われている。
| 尾聯 | 頸聯 | 頷聯 | 首聯 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者略伝
伊藤仁齋 1627-1705
江戸時代初期の儒者。京都の人で、幼名源七、名は維楨(これえだ)、字は源佐(げんすけ)、仁齋は号。父は材木商であったが仁齋は商人を嫌い学者を志す。古義学(論語や孟子の正しい道理を明らかにする学問)を主張し古義学派(堀川学派)を創始し塾を古義堂と称した。門下は三千余人に達したという。著書に「心学原論」「性善論」「論語古義」など文集・詩集が多数ある。長男が伊藤東涯である。宝永2年3月病のため没す。年79。
