漢詩紹介
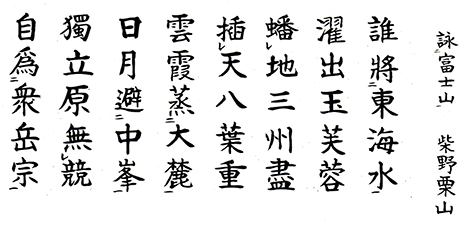
読み方
- 富士山を詠ず<柴野栗山>
- 誰か 東海の水を 將て
- 濯い出だす 玉芙蓉
- 地に蟠って 三州盡き
- 天に插んで 八葉重なる
- 雲霞 大麓に蒸し
- 日月 中峯を避く
- 獨立 原 競うこと無く
- 自ずから 衆岳の 宗と爲る
- ふじさんをえいず<しばのりつざん>
- たれか とうかいのみずを もって
- あらいいだす ぎょくふよう
- ちにわだかまって さんしゅうつき
- てんにさしはさんで はちようかさなる
- うんか たいろくにむし
- じつげつ ちゅうほうをさく
- どくりつ もと きそうことなく
- おのずから しゅうがくの そうとなる
字解
-
- 濯 出
- 洗い磨き出す
-
- 芙 蓉
- 富士山 頂上に八つの峰があって八弁の蓮華(れんげ=芙蓉)に似ているのでいう 蓮岳とも呼ぶ
-
- 蟠 地
- 大地に根を広げている 裾野が広がってどっしりしたさま
-
- 三 州
- 甲斐(かい=山梨)・相模(さがみ=神奈川)・駿河(するが=静岡)の三州
-
- 插 天
- 天空に高く聳(そび)える
-
- 八 葉
- 8枚の花弁
-
- 蒸
- 水蒸気などが湧き上がる
-
- 中 峯
- 中央の高い峰
-
- 衆岳宗
- 群山第一 天下第一
意解
いったい誰が、東海の水でこの玉の蓮(はす)のような富士山を洗い磨き出したのだろうか。
裾野を大地にどっしりと広げて、甲斐・相模・駿河の三州を覆い尽くし、その頂は高く天空に聳えて8枚の花弁が重なり合って見える。
雲や霞もその広い麓から湧き上がり、日や月も中央の峰を避けて通るかと思われる。
その独立した姿は、他に競うべきものもなく、自然に天下第一の山となったのである。
備考
この詩の構造は平起こり五言律詩の形であって、上平声二冬(とう)韻の蓉、重、峯、宗の字が使われている。
| 尾聯 | 頸聯 | 頷聯 | 首聯 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者略伝
柴野栗山 1736-1807
名は邦彦。字は彦輔(ひこすけ)、号は栗山。元文元年四国讃岐の生まれ。江戸中期の儒者。後藤芝山(しざん)に師事し、のち阿波蜂須賀藩の儒者となった。その後幕府に迎えられ昌平黌(しょうへいこう)教授となり、朱子学を振興させた。朱子学以外の学問を修めた者の登用を禁止する運動を幕府にし、「異学者登用禁止令」が発令されるに至った。文化4年没す。年71。著書に「栗山堂詩集」「冠服考証」等がある。なお、高松市の牟礼(むれ)町に栗山記念館がある。
