漢詩紹介
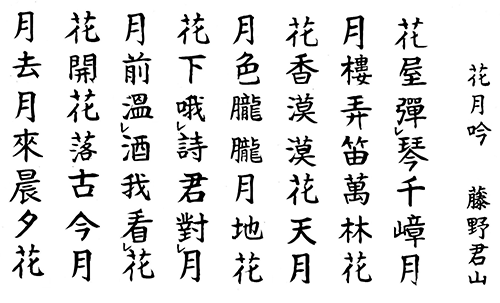
読み方
- 花月吟<藤野君山>
- 花屋琴を彈ず 千嶂の月
- 月樓笛を弄ぶ 萬林の花
- 花香漠漠たり 花天の月
- 月色朧朧たり 月地の花
- 花下詩を哦うて 君月に對し
- 月前酒を溫めて 我花を看る
- 花開き花落つ 古今の月
- 月去り月來る 晨夕の花
- かげつぎん<ふじのくんざん>
- かおくことをだんず せんしょうのつき
- げつろうふえをもてあそぶ ばんりんのはな
- かこうばくばくたり かてんのつき
- げっしょくろうろうたり げっちのはな
- かかしをうとうて きみつきにたいし
- げつぜんさけをあたためて われはなをみる
- はなひらきはなおつ ここんのつき
- つきさりつききたる しんせきのはな
字解
-
- 花 屋
- 花見の家 花を観賞する館
-
- 千 嶂
- たくさんの峰峰
-
- 月 樓
- 月見の高殿
-
- 漠 漠
- はてしないさま
-
- 花 天
- 次句の「月地」とともに「花天月地」の熟語として空には花が咲き地には月光が満ちわたる情景
-
- 朧 朧
- おぼろなさま
-
- 晨 夕
- 朝夕
意解
花を観賞する館で峰峰にかかる月を眺めて琴を弾き、また月を愛(め)でる高殿では林に咲く花を見ながら笛を吹く。
花の香りは天にまではてしなく広がり、月の光は地上を朧(おぼろ)に照らしている。
花のもとで詩を吟じながら君は月を仰ぎ見ており、私は月に対面して酒を温めながら花を眺めている。
花は咲いては散るがその花を照らす月は古来永遠のものであり、一方、月は欠けてはまた満ちてくるが、その月が照らす花は朝(あした)に咲き夕べに散るようにはかないものである。
備考
この詩の構造は、仄起こり七言律詩の形であって(七言古詩という説もある) 、下平声六麻(ま)韻の花、花、花、花の字が使われている。押韻は同族韻の文字を変えて使用するのが通常であるが、作者はあえて「花」の字を使っている。一句目は踏み落とし。全聯を対句とする全対格となっている点や、「月」「花」を交互にそれぞれ十回使っていることなど、一種の文字遊戯の感がある。
| 尾聯 | 頸聯 | 頷聯 | 首聯 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者略伝
藤野君山 1863-1943
明治・大正・昭和の漢学者・評論家。名は静輝(しずてる)。東京に生まれる。日露戦争に従軍したのち、演劇評論家として活躍した。宮内省式部職に勤務し、退官後、大正天皇より賜った菊にちなんで「賜菊園」(しぎくえん)を主宰した。漢詩をよくする。昭和18年11月没す。年80。
