漢詩紹介
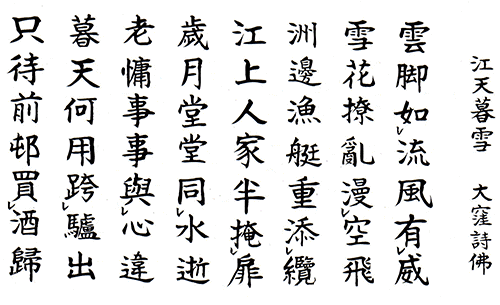
読み方
- 江天の暮雪<大窪詩佛>
- 雲脚流るるが如く 風に威有り
- 雪花撩亂として 空を漫して飛ぶ
- 洲邊の漁艇 重ねて纜を添え
- 江上の人家 半ばは扉を掩う
- 歳月は堂堂として 水と同じく逝き
- 老慵事事に 心と違う
- 暮天何ぞ用いん 驢に跨りて出ずるを
- 只だ待つ前邨より 酒を買うて歸るを
- こうてんのぼせつ<おおくぼしぶつ>
- うんきゃくながるるがごとく かぜにいあり
- せっかりょうらんとして そらをみたしてとぶ
- しゅうへんのぎょてい かさねてともづなをそえ
- こうじょうのじんか なかばはとびらをおおう
- さいげつはどうどうとして みずとおなじくゆき
- ろうようじじに こころとたがう
- ぼてんなんぞもちいん ろにまたがりていずるを
- ただまつぜんそんより さけをこう(オ)てかえるを
字解
-
- 江 天
- 川と空が連なるあたり
-
- 雲 脚
- 雲が低く垂れ下がった様子
-
- 漫 空
- 空一面にひろがる
-
- 老 慵
- おいぼれておっくうなさま
-
- 跨 驢
- 驢馬の背にまたがる 驢馬は詩人や隠者の乗物
-
- 前 邨
- 前方の村 隣村
意解
低い雲がまるで流れているような様子に見えるのは風が強く吹いているからである。雪が入り乱れて、空一面に飛び散っている。
川の洲のあたりでは漁舟(ぎょしゅう)が吹き流されないように、とも綱をいつもより余分に加えられ、川のほとりの人家の半数ほどは、しっかりと扉を閉ざしている。
年月はこの川の水と同じように、おし止どめることができず流れ去り、年をとってしまった自分には、何事も思い通りにはならない。
こんな天候の夕暮れには、驢馬の背にまたがって外出する気にはなれない。家人が隣村から酒を買ってきてくれるのを、じっと待つばかりである。
備考
この詩の構造は仄起こり七言律詩の形であって、上平声五微(び)韻の威、飛、扉、違、歸の字が使われている。
| 尾聯 | 頸聯 | 頷聯 | 首聯 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者略伝
大窪詩佛 1767-1837
江戸中期の漢詩人。明和(めいわ)4年、常陸(ひたち=茨城県)多賀郡大久保村に生まれる。通称柳太郎、名は行光(ゆきみつ)、字は天民、詩佛はその号、また痩梅(そうばい)、詩聖堂の別号あり。江戸に移り住み、諸州に遊び京師の賴山陽も訪ねた。草書と詩を以て名高く、市河寛斎(かんさい)、柏木如亭(じょてい)、菊池五山(ござん)と共に江戸の四詩家と称せられる。習性洒脱(しゃだつ)。谷文晁(ぶんちょう)と親交有り。好んで墨竹を画(えが)きその画は甚だ気品に富んでいる。天保8年2月に没す。年71。相州(神奈川県)藤沢に葬る。著書に「詩聖堂詩集」その他多数の詩集がある。
