漢詩紹介
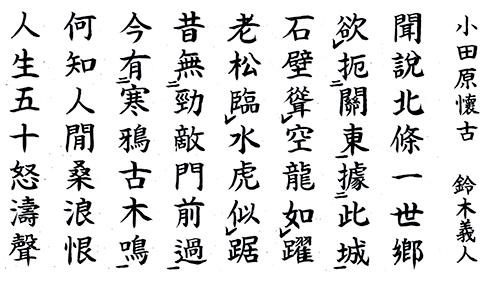
読み方
- 小田原懐古 <鈴木 義人>
- 聞説 北条 一世の郷
- 関東を扼さんと欲して 此の城に拠る
- 石壁空に聳え 龍躍るが如し
- 老松水に臨んで 虎踞るに似たり
- 昔は勁敵 門前を過ぐる無し
- 今は寒鴉の 古木に鳴く有り
- 何ぞ知らん人間 桑浪の恨み
- 人生五十 怒濤の声
- おだわらかいこ <すずき ぎじん>
- きくならく ほうじょう いっせいのきょう
- かんとうをやくさんとほっして このしろによる
- せきへきそらにそびえ りゅうおどるがごとし
- ろうしょうみずにのぞんで とらうずくまるににたり
- むかしはけいてき もんぜんをすぐるなし
- いまはかんあの こぼくになくあり
- なんぞしらんにんげん そうろうのうらみ
- じんせいごじゅう どとうのこえ
語句の意味
-
- 扼
- 抑えつける おしつぶす
-
- 勁 敵
- 強敵 「勁」は強い
-
- 寒 鴉
- もの寂しく鳴く烏
-
- 桑浪恨
- 運命の変わり易いことへの悲しみ 「桑田の変じて海と成るを」(代悲白頭翁)から派生した語
詩の意味
小田原城は北条氏の一世の居城で、関東を抑えつけようとして、この城を拠り所としたと聞いたことがあった。
城の石垣は空に聳え、あたかも龍が躍っているように勇壮で、老松は堀の水に臨んで、虎がうずくまっているようである。
その昔、強い敵も恐れて、門前を通り過ぎるものはいなかったが、今はさびれて、もの寂しく鳴く烏が古い木にいるばかりである。
世間の人は運命の変わり易いことの悲しみを、どうして知っているだろうか。いや知らないだろう。人生五十年というが、実に小田原城を築いた人々の怒濤の声が聞こえるようである。
備考
①小田原城とは
北条早雲が大森氏から奪った。その嫡男氏綱(うじつな)の時代(1500年ごろ)北条氏の居城とする。三代氏康(うじやす)、四代氏政(うじまさ)まで続き、五代氏直の時、豊臣秀吉・徳川家康らによって落城(1590年)。その後家康に譲渡された。最盛期には周囲が10㎞にも及ぶ大規模城であった。明治3年に廃城となり、今は一部の建物を残すのみで、跡は広大な公園となっている。
②北条早雲(1432~1519)という人物
戦国大名。本名は伊勢新九郎。京都の出身で(諸説あり)1469年、駿河に拠点を置いた。1516年には相模全域を掌握した。その祖先は伊勢氏と言い、備中の国(岡山県の西部)の人で、今の岡山県井原(いばら)市西江原(えばら)町に父盛定の菩提寺「法泉寺」がある。隣の東江原町には私鉄が通り「北条早雲の里」という駅がある。
鑑賞
「人生五十怒濤の声」の指すもの
北条氏の盛衰が事実どおりに歌われている。ただ尾聯はどうだろう。当時の人々の間では、北条氏は100年もの長きにわたって栄え、永遠に不滅だと称えているようだが、実はたった100年で滅んだと悲しんでいる作者がいる。歴史観の違いであろう。
「人生五十」とは「人生わずかに五十年」の常套語を念頭に置いているだろうが、ここでは北条氏の歴代城主がみんな50歳前後で他界しているので(早雲64、氏綱54、氏康56、氏政52、氏直49)、彼らの波乱万丈の人生と叫び声を「人生五十怒濤の声」と比喩していると考えるのはいかがであろうか。
詩の形
この詩は七言古詩の形であって、押韻は第一句末に下平声七陽(よう)韻の郷の字が独用され、下平声八庚(こう)韻の城、鳴、聲の字が通韻されている。第四句末は押韻されていない。
作者
鈴木義人
不詳
