漢詩紹介
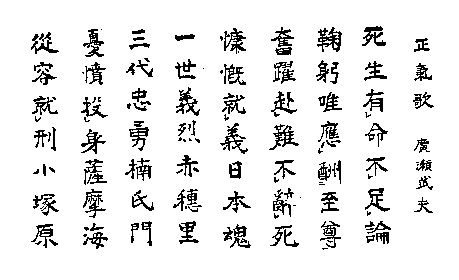
読み方
- 正氣の歌(2-1)<廣瀬武夫>
- 死生命有り 論ずるに足らず
- 鞠躬唯應に 至尊に酬ゆべし
- 奮躍難に赴きて 死を辭せず
- 慷慨義に就く 日本魂
- 一世の義烈 赤穗の里
- 三代の忠勇 楠氏の門
- 憂憤身を投ず 薩摩の海
- 從容刑に就く 小塚が原
- せいきのうた<ひろせたけお>
- しせいめいあり ろんずるにたらず
- きっきゅうただまさに しそんにむくゆべし
- ふんやくなんにおもむきて しをじせず
- こうがいぎにつく やまとだましい
- いっせいのぎれつ あこうのさと
- さんだいのちゅうゆう なんしのもん
- ゆうふんみをとうず さつまのうみ
- しょうようけいにつく こづかがはら
字解
-
- 正 氣
- 万物のおおもとである元気 人の正しい気性
-
- 鞠 躬
- 身をかがめる つつしむ
-
- 至 尊
- この上もなく尊い 天子の敬称
-
- 奮 躍
- ふるいたつ
-
- 赴 難
- 国家の大事に当たる
-
- 慷 慨
- 憤り嘆く 意気がさかんなこと
-
- 義 烈
- 正義の心が強くさかんなこと
-
- 憂 憤
- 憂いいきどおる
-
- 從 容
- ゆったりとおちつく
意解
人間死ぬも生きるも天命であって論ずるまでもなく、つつしんでただひたすら君国のため身を捧げ御恩に報いるべきである。
国難に当たっては奮起し死を辞するものではなく、憤り嘆いて義につくのが日本魂というものだ。
あの一世の正義の心がさかんな赤穂浪士の義挙といい、三代にわたる楠公の忠勇は歴史に今なお燦然と輝いているではないか。
また西郷隆盛は国事に奔走し、遂に追われて同志の僧月照と憂憤を抱いて薩摩湾に身を投じ、吉田松陰をはじめ多くの勤王の志士は安政の大獄に連座し、小塚原で刑についたではないか。
備考
この詩の構造は古詩の形であって、韻は次の通りである。
上平声十三元(げん)韻の論、尊、魂、門、原、痕、冤、存、言、恩の字が使われており、「一韻到底格」である。
作者略伝
廣瀬武夫 1868-1904
菊池氏の後裔(こうえい)にして代々岡藩(大分県)に仕える。明治元年5月27日大分県竹田に生まれる。22年4月海軍兵学校卒。少尉候補生、27年扶桑の航海士、28年海軍大尉、5カ年に亘って露国に留学駐在、33年少佐に進む。37年日露開戦当時は朝日の水雷長であった。
旅順港口閉塞(へいそく)隊長として2回参加、遂に散華(さんげ)した。時に37年3月27日払暁(ふつぎょう)である。年37。中佐に進級、軍神と仰がれる。
