漢詩紹介
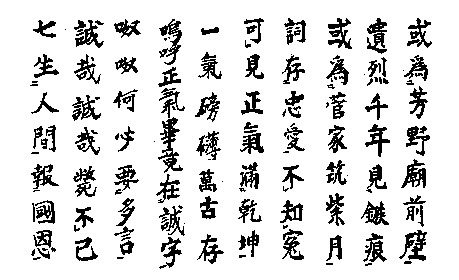
読み方
- 正氣の歌(2-2)<廣瀬武夫>
- 或いは芳野 廟前の壁と爲り
- 遺烈千年 鏃痕を見る
- 或いは菅家 筑紫の月と爲り
- 詞は忠愛を存して 冤を知らず
- 見る可し正氣の 乾坤に滿つるを
- 一氣磅礴して 萬古に存す
- 嗚呼正氣は 畢竟誠の字に在り
- 呶呶何ぞ必ずしも 多言を要せんや
- 誠なるかな誠なるかな 斃れて已まず
- 七たび人間に生まれて 國恩に報ぜん
- せいきのうた<ひろせたけお>
- あるいはよしの びょうぜんのへきとなり
- いれつせんねん ぞっこんをみる
- あるいはかんけ つくしのつきとなり
- ことばはちゅうあいをそんして えんをしらず
- みるべしせいきの けんこんにみつるを
- いっきほうはくして ばんこにそんす
- ああせいきは ひっきょうまことのじにあり
- どどなんぞかならずしも たげんをようせんや
- まことなるかなまことなるかな たおれてやまず
- ななたびにんげんにうまれて こくおんにほうぜん
字解
-
- 冤
- うらみ
-
- 磅 礴
- 広くゆきわたる
-
- 呶 呶
- あれこれやかましくいう
意解
更に南朝時代の楠正行は、芳野廟前の如意輪堂の壁に主従143人の名と辞世の句を鏃をもって永遠に書き残し、決死の覚悟をきめたではないか。
更にまた菅原道真は讒言にあって筑紫に流されたが、多くの詩を詠じて忠愛の誠を表し、決して天皇を恨むことはなかったではないか。
このように生気は天地に満ち満ちていまもなお長く世に残っているのである。
ああ、生気というものはつまるところ誠の一字にあるのであって、くどくどとあれこれ言う必要はない。
誠、この誠こそ終始貫いてたとえ斃れても挫折することなく、七たび人間に生まれて国恩に報いる覚悟である。
備考
この詩の構造は古詩の形であって、韻は次の通りである。
上平声十三元(げん)韻の論、尊、魂、門、原、痕、冤、存、言、恩の字が使われており、「一韻到底格」である。
作者略伝
廣瀬武夫 1868-1904
菊池氏の後裔(こうえい)にして代々岡藩(大分県)に仕える。明治元年5月27日大分県竹田に生まれる。22年4月海軍兵学校卒。少尉候補生、27年扶桑の航海士、28年海軍大尉、5カ年に亘って露国に留学駐在、33年少佐に進む。37年日露開戦当時は朝日の水雷長であった。
旅順港口閉塞(へいそく)隊長として2回参加、遂に散華(さんげ)した。時に37年3月27日払暁(ふつぎょう)である。年37。中佐に進級、軍神と仰がれる。
