漢詩紹介
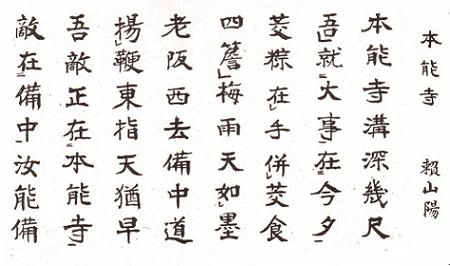
読み方
- 本能寺<賴山陽>
- 本能寺 溝の深さ 幾尺なるぞ
- 吾れ大事を就すは 今夕に在り
- 茭粽手に在り 茭を併せて食ろう
- 四簷の梅雨 天墨の如し
- 老阪西に去れば 備中の道
- 鞭を揚げて東を指させば 天猶早し
- 吾が敵は正に 本能寺に在り
- 敵は備中に在り 汝能く備えよ
- ほんのうじ<らいさんよう>
- ほんのうじ みぞのふかさ いくせきなるぞ
- われだいじをなすは こんせきにあり
- こうそうてにあり こうをあわせてくろう
- しえんのばいう てんすみのごとし
- おいのさかにしにされば びっちゅうのみち
- むちをあげてひがしをゆびさせば てんなおはやし
- わがてきはまさに ほんのうじにあり
- てきはびっちゅうにあり なんじよくそなえよ
字解
-
- 本能寺
- 京都市中京区寺町にある法華宗本山 明智光秀が主君織田信長をおそった「本能寺の変」で有名 ただし当時の本能寺は現在地よりやや位置を異にする
-
- 大 事
- 信長の命による備中高松城を攻めることをせず 信長を撃つために本能寺を攻撃すること
-
- 茭 粽
- ちまき
-
- 四 簷
- 軒の周囲 「簷」はひさし
-
- 老 阪
- 京都と亀岡を結ぶ峠
-
- 備 中
- 現在の岡山市高松にあった備中高松城 羽柴秀吉の「水攻め」で有名
意解
本能寺の溝の深さは一体どのくらいあるのだろうか、その本能寺にいる信長を撃つのは今夕が好機である。
はやる心の光秀はちまきを葉ごと食べてしまい、おりから梅雨が墨を流したように激しく降り、あたりは真っ暗になった。
老の阪から西へ向かえば、信長の命令どおり備中への道であるが、まだ夜の明けない早朝、鞭をあげて東へ向かったのである。
この時光秀は「我が敵は本能寺にあり」と部下に対して絶叫したが、光秀の本当の敵は備中にいる秀吉であり、これに対して十分な備えをしなければいけなかったのである。(と光秀を戒めている)
備考
この詩は賴山陽が日本国史を詠じた「日本楽府」六十六曲の第六十一曲である。
原詩には第一句の「本能寺溝幾尺」と深の字がない。詩の構造は七言古詩の形であって、韻は次の通りである。
第一・二句 入声十一陌(はく)韻の尺、夕
第三・四句 入声十三職(しょく)韻の食、墨
第五・六句 上声十九皓(こう)韻の道、早
第七・八句 去声四寘(し)韻の寺、備
の字が使われている。
作者略伝
賴 山陽 1780-1832
名は襄(のぼる)、字は子成(しせい)、号は山陽。安永9年12月大坂江戸堀に生まれた。父春水は安芸藩の儒者。7歳の時叔父杏坪について書を読み、18歳で江戸に遊学した。21歳で京都に走り、脱藩の罪により幽閉される。のち各地を遊歴し、天保3年9月病のため没す。年53。
著書に「日本外史」「日本政記」「日本楽府(がふ)」などがある。
