漢詩紹介
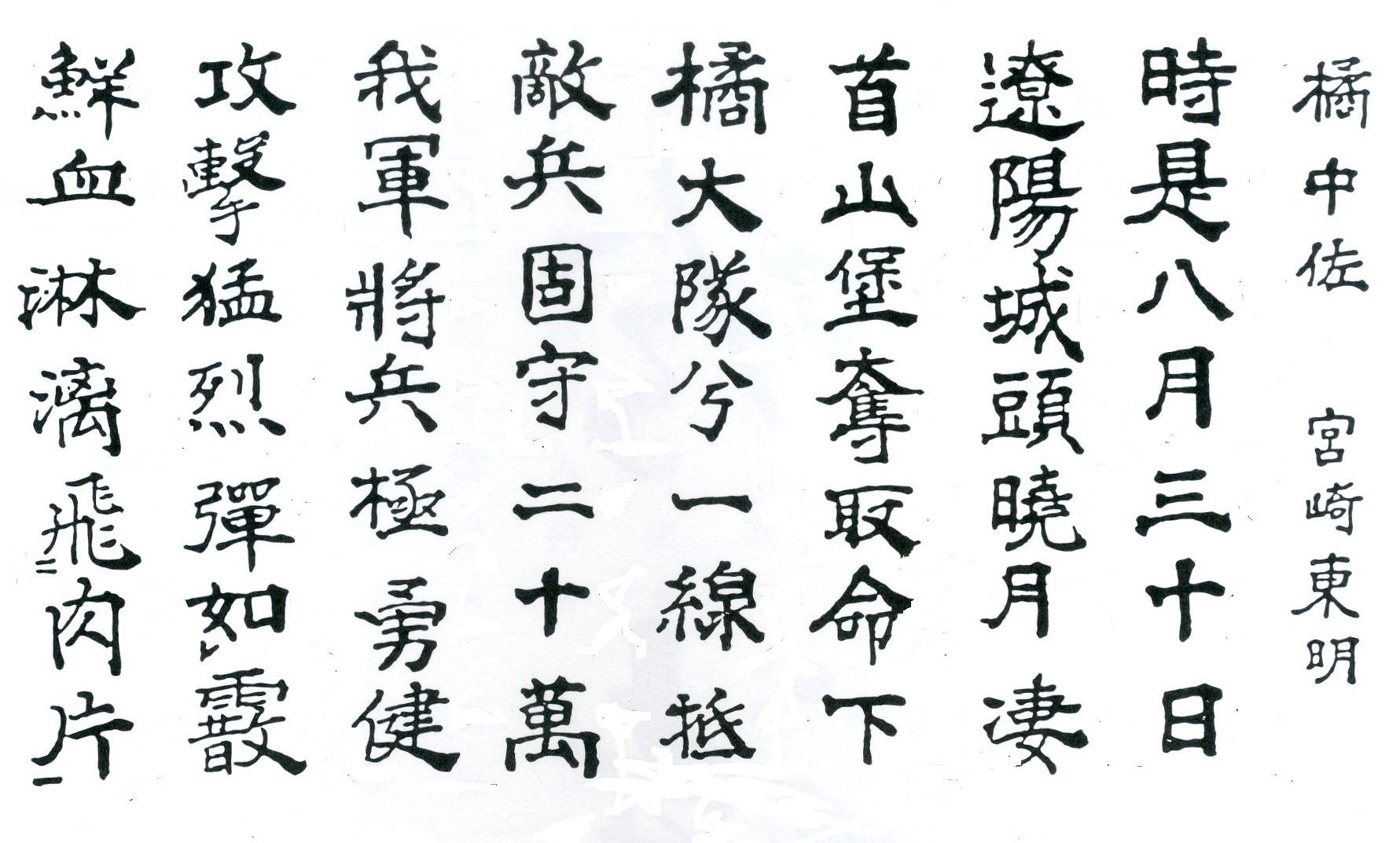
読み方
- 橘中佐 <宮崎東明>
- 時是八月 三十日
- 遼陽城頭 暁月凄し
- 首山堡奪取の 命下り
- 橘大隊 一線に抵たる
- たちばなちゅうさ <みやざき とうめい>
- ときこれはちがつ さんじゅうにち
- りょうようじょうとう ぎょうげつすごし
- しゅざんぽだっしゅの めいくだり
- たちばなだいたい いっせんにあたる
- 敵兵固守す 二十萬
- 我が軍將兵 極めて勇健
- 攻撃猛烈 彈霰の如く
- 鮮血淋漓として 肉片を飛ばす
- てきへいこしゅす にじゅうまん
- わがぐんしょうへい きわめてゆうけん
- こうげきもうれつ たまあられのごとく
- せんけつりんりとして にくへんをとばす
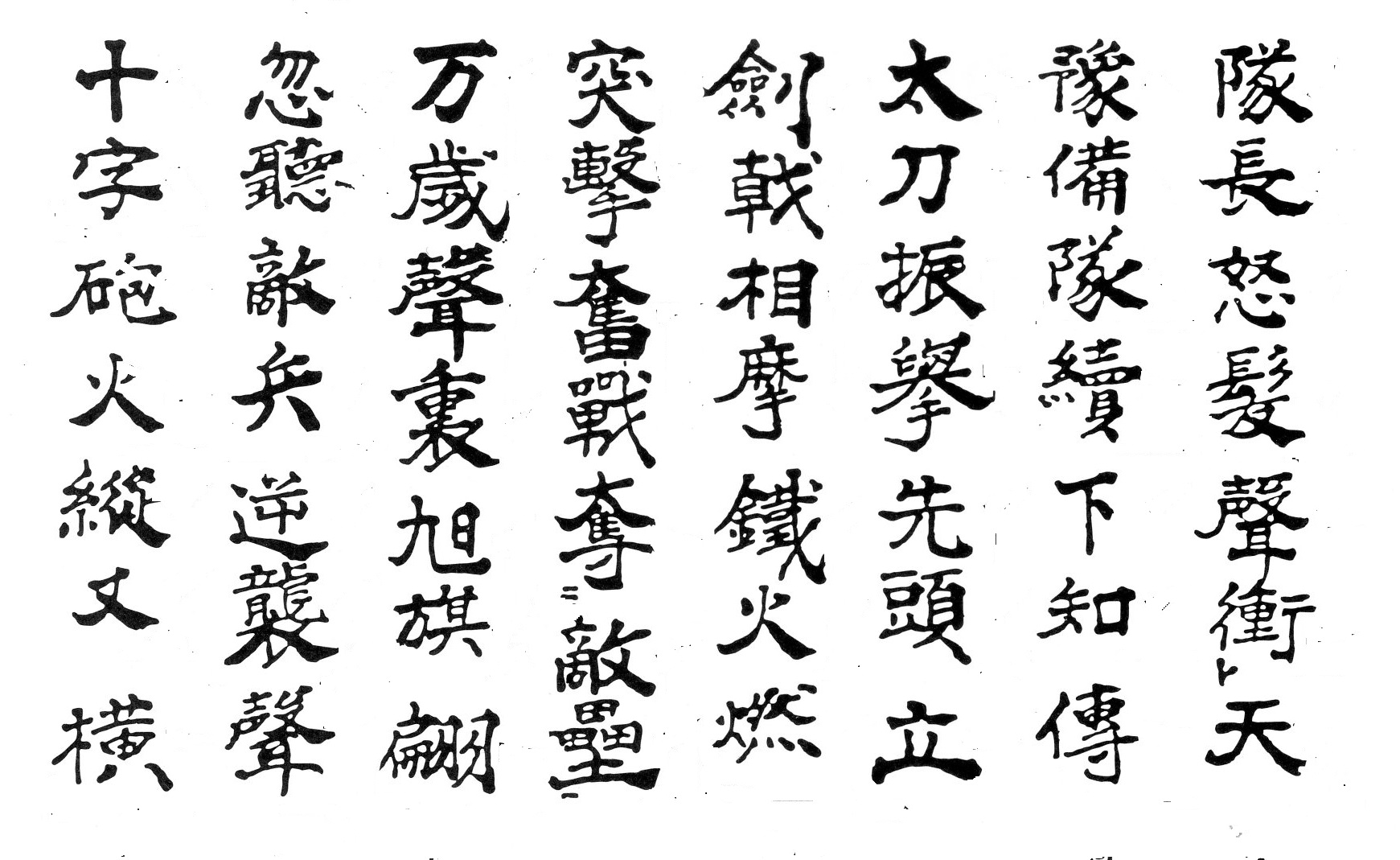
- 隊長怒髪 聲天を衝き
- 豫備隊續けと 下知傳う
- 太刀振り擧げて 先頭に立ち
- 劍戟相摩し 鐡火燃ゆ
- たいちょうどはつ こえてんをつき
- よびたいつづけと げちつとオ
- たちふりあげて せんとうにたち
- けんげきあいまし てっかもゆ
- 突撃奮戰 敵壘を奪い
- 万歳聲裏 旭旗翻る
- 忽ち聽く敵兵 逆襲の聲
- 十字砲火 縦又横
- とつげきふんせん てきるいをうばい
- ばんざいせいり きょっきひるがえる
- たちまちきくてきへい ぎゃくしゅうのこえ
- じゅうじほうか たてまたよこ
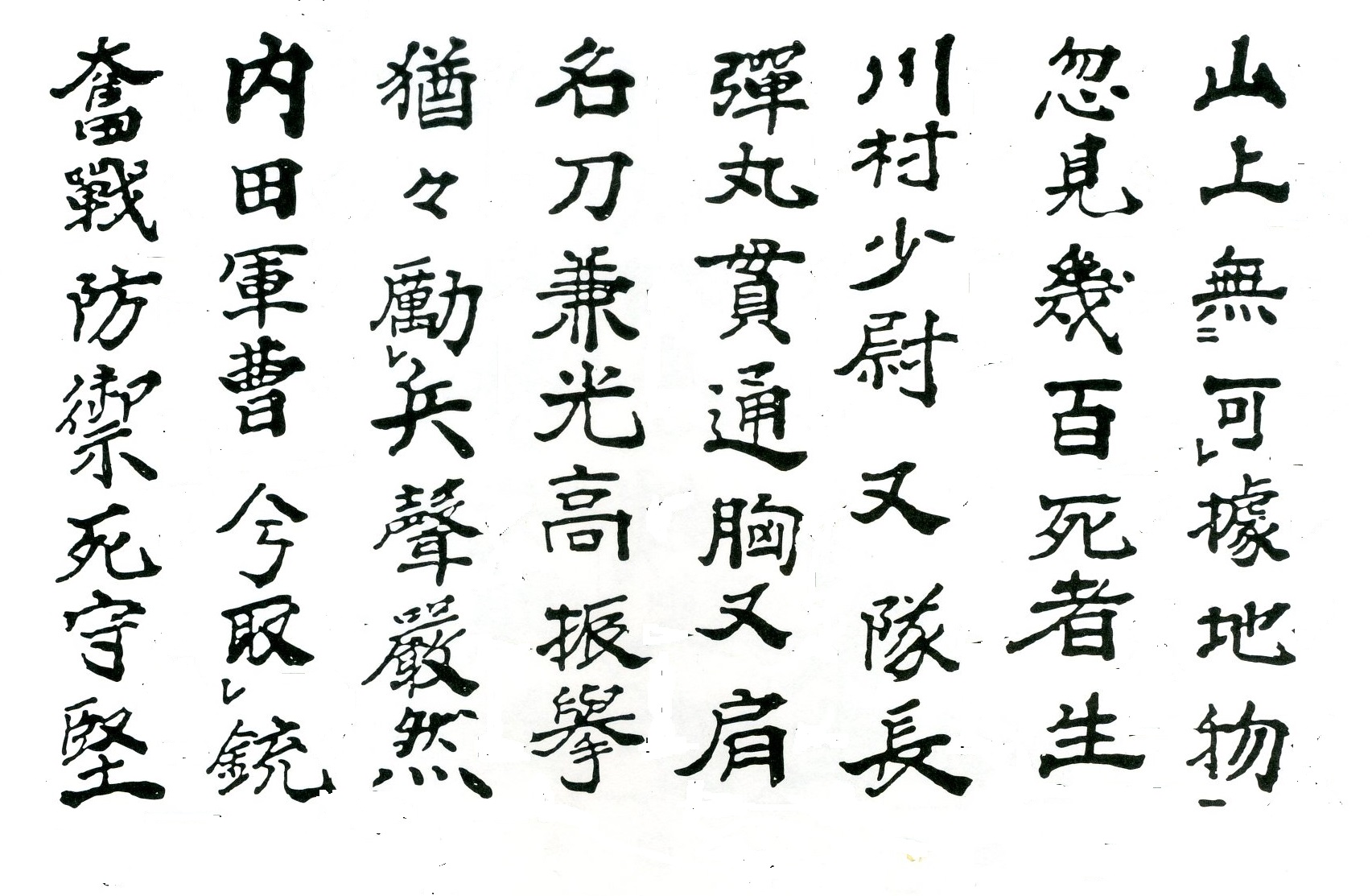
- 山上據る可き 地物無く
- 忽ち見る幾百 死者生ず
- 川村少尉 又隊長
- 彈丸貫通す 胸又肩
- さんじょうよるべき ちぶつなく
- たちまちみるいくひゃく ししゃしょうず
- かわむらしょうい またたいちょう
- だんがんかんつうす むねまたかた
- 名刀兼光 高く振り擧げ
- 猶猶兵を勵ます 聲巖然
- 内田軍曹 銃を取れ
- 奮戰防禦 死守堅し
- めいとうかねみつ たかくふりあげ
- なおなおへいをはげます こえげんぜん
- うちだぐんそう じゅうをとれ
- ふんせんぼうぎょ ししゅかたし
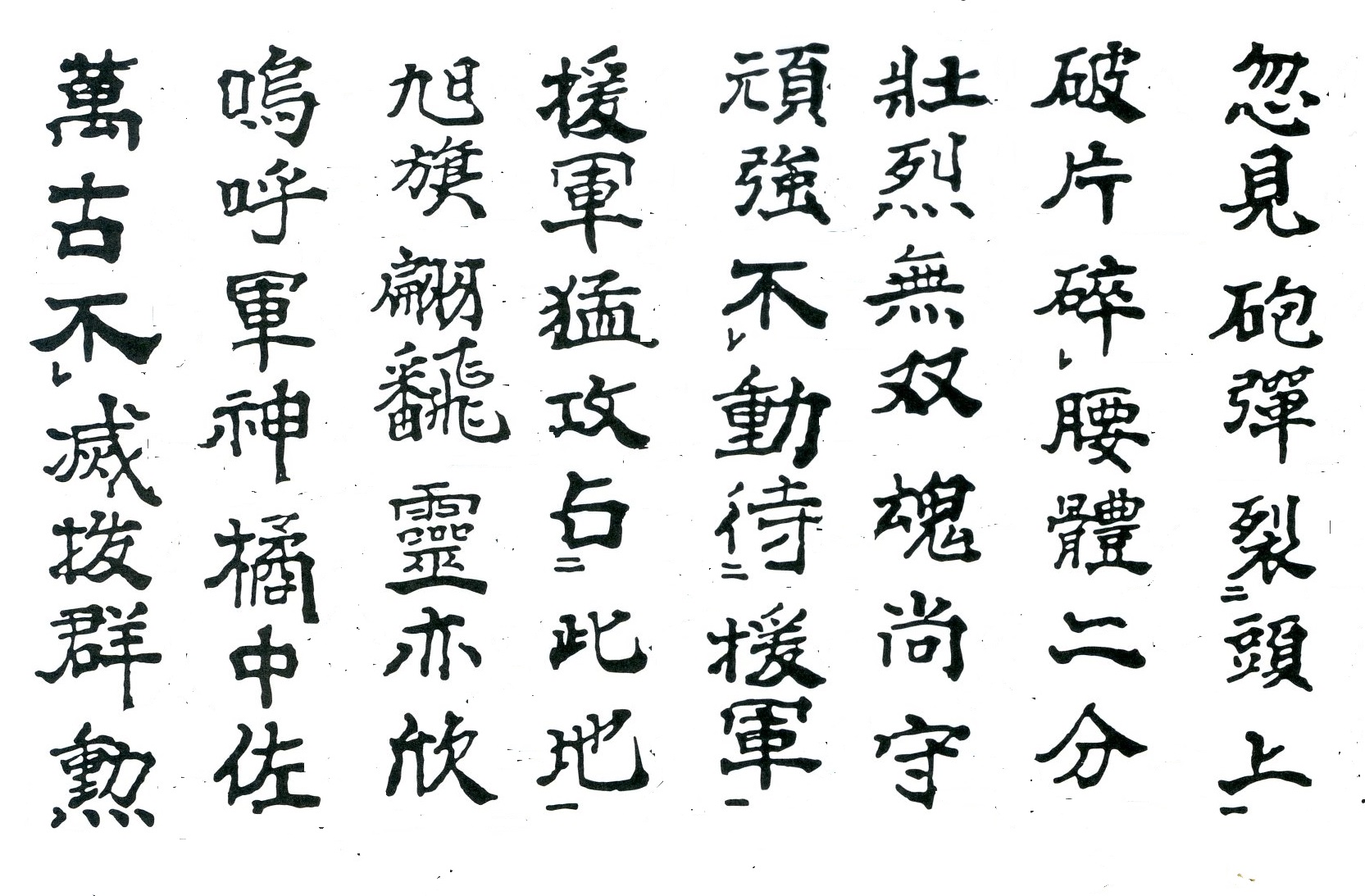
- 忽ち見る砲彈 頭上に裂け
- 破片腰を碎いて 體二分す
- 壯烈無雙 魂尚守り
- 頑強動かず 援軍を待つ
- たちまちみるほうだん ずじょうにさけ
- はへんこしをくだいて たいにぶんす
- そうれつむそう こんなおまもり
- がんきょううごかず えんぐんをまつ
- 援軍猛攻 此の地を占め
- 旭旗翩翻として 靈も亦欣ぶ
- 嗚呼軍神 橘中佐
- 萬古滅せず 抜群の勲
- えんぐんもうこう このちをしめ
- きょっきへんぽんとして れいもまたよろこぶ
- ああぐんしん たちばなちゅうさ
- ばんこめっせず ばつぐんのいさお
字解
-
- 橘中佐
- 本名は橘周太(たちばなしゅうた=1865~1904) 軍人 陸軍歩兵中佐 長野県の人 日露戦争で遼陽付近の大会戦大隊長として戦い首山堡で戦死 軍神とされた
-
- 八月三十日
- 明治37年(1904) 正しくは8月31日
-
- 遼 陽
- 遼寧省瀋陽市の西南太子河の南岸にある都市
-
- 暁 月
- 明け方の月
-
- 首山堡
- 遼東半島の要害の地 「堡」はとりで
-
- 鮮 血
- 真っ赤な血
-
- 淋 漓
- 汗や血のしたたるさま
-
- 怒髪聲衝天
- 甚だしく怒って髪の毛や声が天をつきあげる
-
- 下 知
- 下の者に命令する
-
- 劍 戟
- 剣とほこ
-
- 地 物
- 天然または人工の物 建物 立ち木 岩石など
意解
時は(明治37年)8月30日、遼陽の町あたりの明け方の月は寒ざむと輝いていた。
首山堡要害の地を奪取せよとの命令が下り、橘大隊がその第一線の任にあたった。
敵兵20万で守りは固く、我が軍の将兵もきわめて勇ましく立ち向かった。
敵の攻撃はすさまじく弾は霰のように飛んできて、真っ赤な血がしたたり肉片が飛んだ。
隊長の怒りの髪や声は天を衝くほどであり、予備隊続けと命令が伝わった。
太刀を振り上げて先頭に立ち、剣とほことが互いにすりあい火花が飛び散った。
突撃奮戦して敵の陣地を奪い、万歳の声とともに日の丸の旗が翻った。
忽ち敵兵の逆襲の声が聞こえ、砲弾が十字のごとく縦横に飛び散った。
山上には寄りかかる建物や岩などなく、忽ち幾百もの死者がでた。
川村少尉にもさらに隊長にも弾丸が胸や肩を貫通した。
それでも隊長は名刀兼光を高く振り上げ、なお一層厳然として我が兵を励ました。
内田軍曹に銃を取れと命じ、奮戦防御して必死に守りを固めた。
忽ち砲弾が頭上に炸裂し、破片が隊長の腰を砕き体を真っ二つにした。
勇気比類なき兵士の守りは固く、気丈にも不動のまま援軍を待った。
援軍が来て猛攻を加え、この地を占領し、日の丸が高く翻り、死者の霊も喜んだだろう。
ああ、軍神橘中佐、あなたの群を抜いた功績は永遠に消えることはなく、軍神として祀られることだろう。
備考
この詩は日露戦争に於ける橘中佐をたたえた軍歌「橘中佐」(鍵谷徳三郎作詞・安田俊高作曲)を下敷きにして作られたものである。
詩の構造は七言古詩の形であって韻は次の通りである。
-
- 第2句
- 上平声八齊(せい)韻の凄
-
- 第4句
- 上声八薺(せい)韻の抵
-
- 第5・6句
- 去声十四願(がん)韻の萬、健
-
- 第7・8句
- 去声十七霰(さん)韻の霰、片
-
- 第9・10・12・14・20・22・24句
- 下平声一先(せん)韻の天、傳、燃、翩、肩、然、堅
-
- 第15・16・18句
- 下平声八庚(こう)韻の聲、横、生
-
- 第26・28・30・32句
- 上平声十二文(ぶん)韻の分、軍、欣、勲
作者略歴
宮崎東明 1889~1969
名は喜太郎、東明は号。明治22年3月河内国四條村野崎(現在の大東市)に生まれる。京都府立医学専門学校を卒業、大阪玉川町に医院を開く。医業のかたわら詩を藤澤黄坡(ふじさわこうは)、書を臼田岳洲(うすだがくしゅう)、画を中国人方洺(ほうめい)、篆刻(てんこく)を高畑翠石(たかはたすいせき)、吟詩を眞子西洲(まなごさいしゅう)の各先生に学び、その居を五楽庵と称した。昭和9年関西吟詩同好会(現、公益社団法人関西吟詩文化協会)を創設し、昭和23年、藤澤黄坡初代会長没後二代目会長に就任。昭和44年9月18日没す。年81。
