漢詩紹介
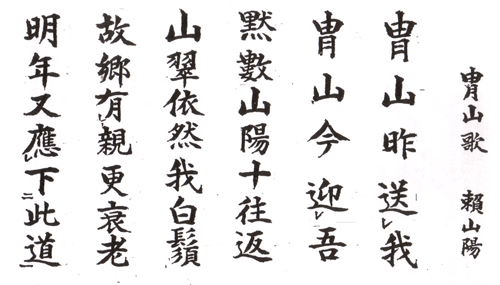
CD③収録 吟者:池田菖黎
2015年6月掲載
読み方
- 冑山の歌<賴山陽>
- 冑山 昨我を送り
- 冑山 今吾を迎う
- 黙して數うれば 山陽 十たび往返
- 山翠は依然たり 我は白鬚
- 故郷に親有り 更に衰老
- 明年又應に 此の道を下るべし
- かぶとやまのうた<らいさんよう>
- かぶとやま きのうわれをおくり
- かぶとやま いまわれをむこう
- もくしてかぞうれば さんよう とたびおうへん
- さんすいはいぜんたり われははくしゅ
- こきょうにおやあり さらにすいろう
- みょうねんまたまさに このみちをくだるべし
字解
-
- 冑 山
- 兵庫県西宮市にある 六甲山系の南東端に位置し標高309メートル 冑の形をしているのでこの名がある 中腹に真言宗神呪寺(かんのうじ)がある
-
- 山 翠
- 山のみどり
-
- 依 然
- もとのまま
-
- 白 鬚
- 白いあごひげ
-
- 故 郷
- 現在の広島市
-
- 親
- 山陽の母 父春水の妻 静子(梅=ばいし)夫人
-
- 應
- まさニ……べしと読む再読文字 きっと……するだろう
意解
冑山は昨年帰郷する私を見送ってくれたが、その同じ山が今年は上京する私を迎えてくれる。
目を閉じて静かに数えてみると、もう十度もこの山陽道を往復している。山のみどりは今も昔ももとのままなのに、自分は年とともに老いてあごひげも白くなった。
故郷には母がおり一層老いてゆくので、明年もまたこの道を下って、きっと会いにいくだろう。
備考
賴山陽は広島に母がいたため、京都と広島の間を何回も往復している。この詩は文政10年(1827)9月、48 歳の時の作である。
詩の構造は古詩の形であって韻は
第二・四句 上平声七虞(ぐ)韻の吾、鬚
第五・六句 上声十九皓(こう)韻の老、道
の字が使われている。
作者略伝
賴 山陽 1780-1832
名は襄(のぼる)、字は子成(しせい)、号は山陽。安永9年12月大坂江戸堀に生まれた。父春水は安芸藩の儒者。7歳の時叔父杏坪について書を読み、18歳で江戸に遊学した。21歳で京都に走り、脱藩の罪により幽閉される。のち各地を遊歴し、天保3年9月病のため没す。年53。
著書に「日本外史」「日本政記」「日本楽府(がふ)」などがある。
