漢詩紹介
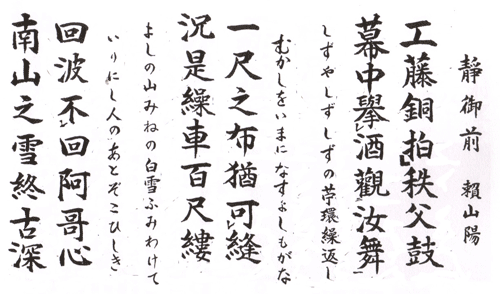
CD③収録 吟者:辰巳快水
2015年5月掲載
読み方
- 靜御前<賴山陽>
- 工藤の銅拍 秩父の鼓
- 幕中酒を擧げて 汝の舞を觀る
- しずやしず しずの苧環 繰返し
- むかしをいまに なすよしもがな
- 一尺の布 猶縫う可し
- 況や是 繰車 百尺の縷
- よしの山 みねの白雪 ふみわけて
- いりにし人の あとぞこひしき
- 回波回らず 阿哥の心
- 南山の雪 終古に深し
- しずかごぜん<らいさんよう>
- くどうのどうひょう ちちぶのつづみ
- ばくちゅうさけをあげて なんじのまいをみる
- しずやしず しずのおだまき くりかえし
- むかしをいまに なすよしもがな
- いっしゃくのぬの なおぬうべし
- いわんやこれ そうしゃ ひゃくしゃくのいと
- よしのやま みねのしらゆき ふみわけて
- いりにしひとの あとぞこいしき
- かいはめぐらず あかのこころ
- なんざんのゆき とこしえにふかし
字解
-
- 工 藤
- 源頼朝の家臣で工藤祐経(すけつね)
-
- 銅 拍
- 銅拍子ともいい銅で作ったドラ
-
- 秩 父
- 源頼朝の家臣で秩父三郎
-
- 幕 中
- 鎌倉の鶴岡八幡宮の垂れ幕の中
-
- 汝
- 義経の愛妾である静御前
-
- しずの苧環
- 「苧環」は麻糸を球状に巻いたもの 「しずやしずしずの苧環」は「繰る」の序詞で「繰る」を飾る役目
-
- 一尺之布
- 「史記」に「一尺之布尚可縫 一斗之粟尚可春 兄弟二人不能相容」(一尺の布なお縫うべし 一斗の粟なおうすづくべし 兄弟二人相容るるあたわず=一尺の布でも縫い合わせることができるし わずか一斗の粟でも臼でついて食べることができるのに 漢の淮南=わいなん=・厲王=れいおう=兄弟は不仲であった)とあるのによる
-
- 況
- まして……はなおさらだ
-
- 回 波
- もと舞曲の名 めぐり寄せる波
-
- 阿 哥
- 兄 ここでは頼朝
-
- 南 山
- ここでは吉野山
意解
頼朝は家臣の工藤祐経に銅拍子を、秩父三郎に鼓を打たせ、鶴岡八幡宮境内の垂れ幕の中で、杯を傾けつつ静御前の舞を悦に入って眺めている。
(和歌)しずやしず……過去をたぐりよせて昔のことを今に蘇らせる方法がほしい。
一尺の布でも衣服を縫いあわせることができるのに、まして糸車の百尺もある糸はなおさら立派な布に織ることができる。(頼朝・義経の契りの深い兄弟ならば仲良くできないことはない)
(和歌)よしの山……吉野山の嶺の白雪を踏み分けて東国に行った義経のあとが恋しい。
寄せては返す波の姿が変わらないように頼朝の心を翻すことはできなかったので、吉野山の雪が永遠に深く積もっているように、静御前の心も深い恨みから融けることはなかった。
備考
この詩は、賴山陽「日本楽府」66首の一つで、静御前が頼朝に呼ばれ、文治2年(1186)4月8日、鎌倉の 鶴岡八幡宮で舞った静の心情に寄せ、頼朝と義経兄弟の不和を詠じたものである。
詩の構造は七言古詩の形であって韻は
第一・二・四句 上声七麌(ぐ)韻の鼓、舞、縷
第五.六句 下平声十二侵(しん)韻の心、深
の字が使われている。
作者略伝
賴 山陽 1780-1832
名は襄(のぼる)、字は子成(しせい)、号は山陽。安永9年12月大坂江戸堀に生まれた。父春水は安芸藩の儒者。7歳の時叔父杏坪について書を読み、18歳で江戸に遊学した。21歳で京都に走り、脱藩の罪により幽閉される。のち各地を遊歴し、天保3年9月病のため没す。年53。
著書に「日本外史」「日本政記」「日本楽府(がふ)」などがある。
