漢詩紹介
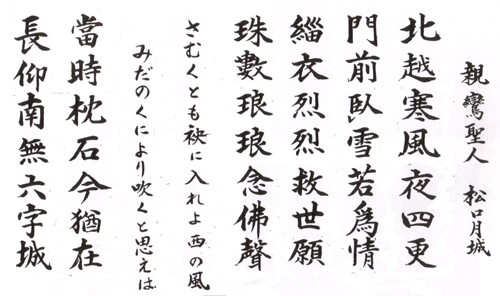
読み方
- 親鸞聖人<松口月城>
- 北越の寒風 夜四更
- 門前 雪に臥す 若爲の情ぞ
- 緇衣烈烈 救世の願い
- 珠數琅琅 念佛の聲
- さむくとも 袂に入れよ 西の風
- みだのくにより 吹くと思えば
- 當時の枕石 今猶在り
- 長く仰ぐ 南無 六字城
- しんらんしょうにん<まつぐちげつじょう>
- ほくえつのかんぷう よるしこう
- もんぜん ゆきにふす いかんのじょうぞ
- しいれつれつ きゅうせいのねがい
- じゅずろうろう ねんぶつのこえ
- さむくとも たもとにいれよ にしのかぜ
- みだのくにより ふくとおもえば
- とうじのちんせき いまなおあり
- ながくあおぐ なむ ろくじじょう
字解
-
- 四 更
- 午前2時頃
-
- 緇 衣
- 墨染の衣 「緇」は黒色 転じて墨染の衣を着た僧侶
-
- 烈 烈
- 力強く烈しいさま
-
- 琅 琅
- 清らかな声 「琅」は玉のように澄んだ声
-
- 南無六字城
- 南無阿弥陀仏の六字の教え 「城」は教え
意解
北越地方布教の折、大雪に遭い、寒風が吹きすさぶ中を午前2時頃、民家の門前に立ち一夜の宿を乞うたが拒まれ、雪の中で石を枕にして寝た親鸞の気持ちはどのようなものであったろう。
墨染の衣を着た親鸞の、世を救う願望は力強く激しく燃え、珠数を手に清らかな声で念仏を唱えた。
(和歌)さむくとも……寒くても西から吹く風が袂に入るのを拒まないでほしい。阿弥陀様の国から吹いてくると思うから。
当時枕にした石は今も枕石寺に遺跡としてあり、南無阿弥陀仏の六字の教えは永く世の人々に仰がれている。
備考
この詩は浄土真宗の開祖親鸞聖人が北越(常陸?)地方布教の折、大雪に遭い一夜の宿を拒まれ苦労を重ねられたことを詠じたもので詩題は「親鸞聖人雪中布教の図に題す」であるが、本会では「親鸞聖人」と簡略化した。
詩の構造は七言古詩の形であって下平声八庚(こう)韻の更、情、聲、城の字が使われている。
作者略伝
松口月城 1887-1981
名は榮太(えいた)、号は月城、明治20年福岡県筑紫郡那珂川町今光に生まれる。熊本医学専門学校を卒業し、18歳にして医師となり世人を驚かせた秀才である。医業のかたわら漢詩を宮崎来城に学び、詩、書画、共に巧みであった。
なお本会顧問を永年つとめられる。昭和56年7月16日没す。年95。
参考
親鸞聖人と枕石寺の関係
親鸞聖人(1173-1262)は9歳で出家し20年間比叡山で修行していたが、叡山は出家の住むところに非ずとして京都六角堂にこもり、法然の門に入って専修念仏にはげんだ。しかし承元元年(1207)法然と共に正法紊乱(しょうほうぶんらん)の罪科に処せられ、法然は土佐に親鸞は越後に配流された。建暦(けんりゃく)元年(1211)罪は許されたが、翌年師の法然の死にあい、伝道の地を東国にもとめ常陸・下総・下野(しもつけ)・武蔵・奥州等をめぐっている。
枕石寺伝によると、建暦2年(1212)布教中の親鸞は二人の弟子と共に常陸を通りかかり、吹雪のために日野左衛門頼秋という武士の家を訪ね一夜の宿を請うと、頼秋は「仏道を修行する者が雪や寒さを苦にして安楽に宿をとるとは何事か」と断ったので聖人たちは石を枕に雪中で休まれた。その夜頼秋は夢の中で千手観音のお告げを受け、外に出てみると石を枕に念仏する聖人の姿を見て改心し、聖人の教えを受けて帰依し、「道円」の法名を得て邸宅を寺として「枕石寺」を創建したとある。
倉田百三の戯曲「出家とその弟子」のモチーフともなった枕石の伝承がある寺である。
「月城詩集」では「北越で聖人が雪中一夜日野左衛門を感化さされた」とあるが、「布教の図は北越ではなく常陸では」との疑問がわくものである。
枕石寺所在地 茨城県常陸太田市上河合町1102-1
