漢詩紹介
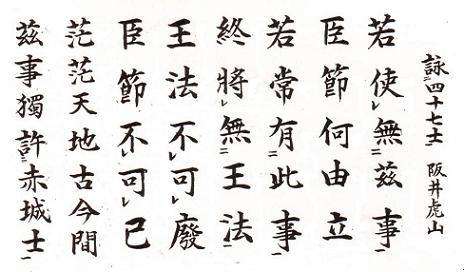
読み方
- 四十七士を詠ず<阪井虎山>
- 若し茲の事 無からしめば
- 臣節 何に由ってか立たん
- 若し常に 此の事有らば
- 終に將に 王法無からんとす
- 王法は 廢す可からず
- 臣節は 已む可からず
- 茫茫たる天地 古今の間
- 茲の事獨り 赤城の士にのみ許す
- しじゅうしちしをえいず<さかいこざん>
- もしこのこと なからしめば
- しんせつ なにによってかたたん
- もしつねに このことあらば
- ついにまさに おうほうなからんとす
- おうほうは はいすべからず
- しんせつは やむべからず
- ぼうぼうたるてんち ここんのかん
- このことひとり せきじょうのしにのみゆるす
字解
-
- 茲 事
- 赤穂浪士の討入り
-
- 臣 節
- 臣としての忠節
-
- 王 法
- 王者の作った法律 国の法律
-
- 茫茫天地
- ひろびろした世の中
-
- 古今間
- 昔から今まで
-
- 赤城士
- 赤穂城の四十七士
意解
もしこの事、即ち赤穂浪士の討ち入りを起こさせなかったら、臣として守るべき忠節は何によってたてられたであろうか。
もしこのような事が常に起これば、国の法律は無いようなもので、世の中の秩序は乱れてしまうだろう。
国の法律は無視してはならず、臣としての忠節をたてるための行いもまたやむを得ないことでもある。
ひろびろとした世の中において、昔から今までこの復讐の義挙はただ赤穂浪士にのみ許されるべきことである。
備考
この詩の構造は一句から六句までは五言、七・八句は七言からなる古詩の形であって韻は
第二句 入声十四緝(しゅう)韻の立
第四句 入声十七洽(こう)韻の法
第六・八句 上声四紙(し)韻の已、士
の字が使われている。
作者略伝
阪井虎山 1798-1850
江戸後期の儒学者。広島に生まれる。東派(とうは)の子。名は華(ひかる)、字は公実(こうじつ)、通称は百太郎(ひゃくたろう)、号は虎山。父と賴春水(らいしゅんすい)に学び、文政8年(1825)安芸藩校教授に任命された。天保8年(1837)藩令を受けて江戸に上り、松崎慊堂(まつざきこうどう)・佐藤一斎(さとういっさい)らと交流し、名声ますますあがる。
史論・文章にたけ、家塾「百千堂」には500人の門人を数えた。著書に「杞国策(きこくさく)」「論語講義」等がある。嘉永3年没す。年53。
