漢詩紹介
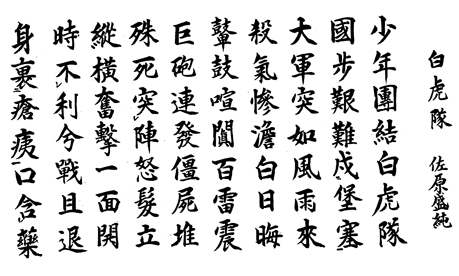
読み方
- 白虎隊(2-1)<佐原盛純>
- 少年團結す 白虎隊
- 國歩艱難 堡塞を戍る
- 大軍突如 風雨來る
- 殺氣慘澹 白日晦し
- 鼙鼓喧闐 百雷震う
- 巨砲連發して 僵屍堆し
- 殊死陣を突いて 怒髪立つ
- 縦横奮撃 一面を開く
- 時に利あらず 戰い且つ退く
- 身に瘡痍を裹み 口に藥を含む
- びゃっこたい<さはらもりずみ>
- しょうねんだんけつす びゃっこたい
- こくほかんなん ほさいをまもる
- たいぐんとつじょ ふううきたる
- さっきさんたん はくじつくらし
- へいこけんてん ひゃくらいふるう
- きょほうれんぱつして きょうしうずたかし
- しゅしじんをついて どはつたつ
- じゅうおうふんげき いちめんをひらく
- ときにりあらず たたかいかつしりぞく
- みにそういをつつみ くちにくすりをふくむ
字解
-
- 國歩艱難
- 国勢が振るわず危機に瀕する
-
- 堡 塞
- とりで ここでは会津城
-
- 慘 澹
- ものすごいさま
-
- 白 日
- 昼
-
- 鼙 鼓
- 攻撃合図の太鼓
-
- 喧 闐
- 人の声がやかましい ここでは陣太鼓がなりわたる
-
- 僵 屍
- 倒れた死体
-
- 殊 死
- 決死 死ぬ覚悟を決める
-
- 瘡 痍
- きず
意解
明治戊辰(ぼしん)戦争の時、会津藩に忠誠を誓う少年達は、雄々しく団結して白虎隊と名乗り、国勢振るわず危機に瀕する会津城を必死に守ろうとした。
数千の大軍が突如嵐のように押し寄せ、殺気は天地に漲り、打ち出す砲煙で昼なお暗いありさまであった。
陣太鼓は百雷が鳴るように響き渡り、大砲は雨霰と連発され屍は山と化した。
少年達の怒髪は天を突き、決死の覚悟で奮い立ち、縦横に戦い血路を開いた。
しかし戦いに利なく戦いつつ後退し、傷を負った身を繃帯で包み薬を口にしている。
備考
この詩は、明治元年戊辰戦争で会津の少年白虎隊が官軍を迎え撃ち、飯盛山で自刃して悲劇的に散った事績を伝えようとしたものである。
詩の構造は七言古詩の形であって韻は次の通りである。
第1・2・4句 去声十一隊(たい)韻の隊、塞、晦
第6・8句 上平声十灰(かい)韻の堆、開
第10句 入声十藥(やく)韻の藥
第12句 入声三覺(かく)韻の嶽
第13・14・16句 下平声七陽(よう)韻の、徨、僵
第17・18・20句 下平声一先(せん)韻の年、傳、賢
の字が使われている。
作者略伝
佐原盛純 1835-1908
幕末から明治の儒者。会津若松の人。名は盛純、字は業夫(なりお)、号は豊山。18歳の時江戸に出て桜田虎門に学ぶ。業を終えて外国奉行に従い欧州各国を視察、鎖国の暴挙を認識し、帰国後開国を唱えたが目的を果たせなかった。
明治維新後郷里に帰り子弟の教育にあたる。明治41年没す。年74。
参考
中国の故事に四方を司る神(四神)として
青竜 東を司る神
白虎 西を司る神
朱雀 南を司る神
玄武 北を司る神がある。
会津藩では、1868年(明治元年)軍政の改革をして中国の故事にならい年齢別に軍を編成した。
白虎隊16歳から17歳
朱雀隊18歳から35歳
青竜隊36歳から49歳
玄武隊50歳以上
の四隊に分けた。
