漢詩紹介
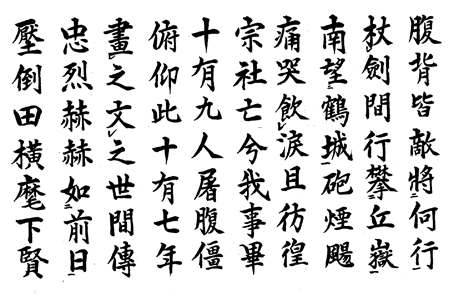
読み方
- 白虎隊(2-2)<佐原盛純>
- 腹背は皆敵 將に何くにか行かんとす
- 劍を杖つき間行 丘嶽を攀ず
- 南鶴城を望めば 砲煙が颺る
- 痛哭涙を飮んで 且つ彷徨す
- 宗社亡びぬ 我が事畢わる
- 十有九人 屠腹して僵る
- 俯仰す此に 十有七年
- 之を畫にし之を文にして 世間に傳う
- 忠烈赫赫として 前日の如し
- 壓倒す田横 麾下の賢
- びゃっこたい<さはらもりずみ>
- ふくはいはみなてき まさにいずくにかゆかんとす
- けんをつえつきかんこう きゅうがくをよず
- みなみつるがじょうをのぞめば ほうえんあがる
- つうこく なみだをのんで かつほうこうす
- そうしゃほろびぬ わがことおわる
- じゅうゆうくにん とふくしてたおる
- ふぎょうすここに じゅうゆうしちねん
- これをがにしこれをぶんにして せけんにつとう
- ちゅうれつかくかくとして ぜんじつのごとし
- あっとうすでんおう きかのけん
字解
-
- 間 行
- 間道(抜け道)をゆく
-
- 鶴 城
- 会津若松城のこと 黒川城ともいう
-
- 彷 徨
- さまよう
-
- 宗 社
- 宗廟と社稷 ここでは会津藩
-
- 俯 仰
- うつむき仰ぐ ここではふり返る
-
- 赫 赫
- 明らかでさかんなさま
-
- 田 横
- 中国斉の王 漢の高祖が天下を統一した時斉王の田横を招いたが漢に屈するのをいさぎよしとせず洛陽に到る途中自殺した
-
- 麾 下
- 将軍直属の部下 田横の部下の将兵 田横が自殺したことを知り部下500人が殉死した
意解
見渡せば前も後も皆敵でどちらに行こうか迷いながら、剣を杖にして間道づたいに飯盛山にたどりついた。
遥か南の方を望むと鶴ヶ城は砲煙に包まれ、落城したかと涙を呑んでさまようのであった。
ああ、会津藩も亡んで我ら臣下のつとめも終わったかと、19人は腹をかき切って果てたのである。
振り返って見れば時は移り17年、世の中は変わったけれど、白虎隊の勇壮悲惨な事績は、画にし文にして世間に伝えられている。
白虎隊の忠烈は今なお明らかに光り輝き、あたかも昨日の事のようであり、これは昔、漢に屈しなかった田横に忠節を誓って殉死した部下の心を圧倒するほどである。
備考
この詩は、明治元年戊辰戦争で会津の少年白虎隊が官軍を迎え撃ち、飯盛山で自刃して悲劇的に散った事績を伝えようとしたものである。
詩の構造は七言古詩の形であって韻は次の通りである。
第1・2・4句 去声十一隊(たい)韻の隊、塞、晦
第6・8句 上平声十灰(かい)韻の堆、開
第10句 入声十藥(やく)韻の藥
第12句 入声三覺(かく)韻の嶽
第13・14・16句 下平声七陽(よう)韻の颺、徨、僵
第17・18・20句 下平声一先(せん)韻の年、傳、賢
の字が使われている。
作者略伝
佐原盛純 1835-1908
幕末から明治の儒者。会津若松の人。名は盛純、字は業夫(なりお)、号は豊山。18歳の時江戸に出て桜田虎門に学ぶ。業を終えて外国奉行に従い欧州各国を視察、鎖国の暴挙を認識し、帰国後開国を唱えたが目的を果たせなかった。
明治維新後郷里に帰り子弟の教育にあたる。明治41年没す。年74。
参考
中国の故事に四方を司る神(四神)として
青竜 東を司る神
白虎 西を司る神
朱雀 南を司る神
玄武 北を司る神がある。
会津藩では、1868年(明治元年)軍政の改革をして中国の故事にならい年齢別に軍を編成した。
白虎隊16歳から17歳
朱雀隊18歳から35歳
青竜隊36歳から49歳
玄武隊50歳以上
の四隊に分けた。
