漢詩紹介
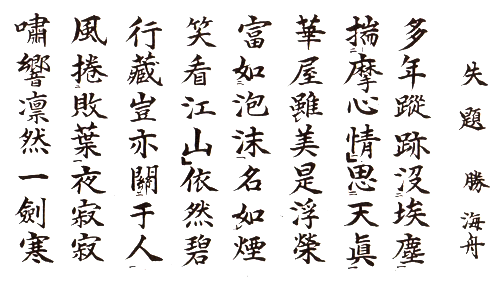
読み方
- 失題<勝海舟>
- 多年の蹤跡 埃塵に没す
- 心情を揣摩して 天眞を思う
- 華屋美なりと雖も 是浮榮
- 富は泡沫の如く 名は煙の如し
- 笑って看る江山の 依然として碧なるを
- 行藏豈亦 人に關せんや
- 風は敗葉を捲いて 夜寂寂
- 嘯響凛然 一劍寒し
- しつだい<かつかいしゅう>
- たねんのしょうせき あいじんにぼっす
- しんじょうをしまして てんしんをおもう
- かおくびなりといえども これふえい
- とみはほうまつのごとく なはけむりのごとし
- わらってみるこうざんの いぜんとしてみどりなるを
- こうぞうあにまた ひとにかんせんや
- かぜははいようをまいて よるせきせき
- しょうきょうりんぜん いっけんさむし
字解
-
- 蹤 跡
- 足跡
-
- 埃 塵
- 塵(ちり)と埃(ほこり) 世間
-
- 揣 摩
- 心を推し測る
-
- 天 眞
- 天から与えられた純粋無垢な気持ち
-
- 華 屋
- 豪華な邸宅
-
- 浮 榮
- はかない栄華 見栄
-
- 行 藏
- 世に出て道を行うことと世をのがれて隠れること
-
- 豈 亦
- どうして……であろうか いやない
-
- 敗 葉
- 落ち葉 枯れ葉
-
- 嘯 響
- 詩を詠ずる声 またその響き
意解
官途より退いて長い歳月が過ぎ、自分のこれまでの足跡は全く世間の中に埋没してしまったが、今、自分の心情を推し測ってみれば、いつも純粋無垢でありたいと思っている。
大体豪華な邸宅を構えて美しく立派といっても、それははかない見栄に過ぎないし、富は水の泡のようなものであり、名声も煙のようにはかなく消え去るものである。
それに比べ、自然の山河が昔ながらに碧の色をたたえているのを嬉しく笑って見るにつけ、自分が世の中に出て道を行うにせよ、世をのがれて隠れるにせよ、それは世の人事と関係があるわけではない。
今、閑居の窓外には風が落ち葉を巻き上げてさびしい音を立て、夜は静かに更けていくが、この時、好きな詩を詠ずると、凛然となり、愛剣の鞘を払えば冷たいことは氷のようで心がひきしまる。
参考
「行藏」について
「論語」述而(じゅつじ)編に孔子の言葉として「用之則行、舎之則蔵」(之を用ふれば則ち行ひ、之を舎=す=つれば則ち蔵=かく=る)とあり、 自分を必要とするものがあれば世に出るし、必要としなければ身を隠しておくのが君子の行動であると説くのによる。
備考
この詩の構造は七言古詩の形であって韻は次の通りである。
第一・二・六句 上平声十一眞(しん)韻の塵、眞、人
第四句 下平声一先(せん)韻の煙
第八句 上平声十四寒(かん)韻の寒
の字が通韻して使われてぃる。
作者略伝
勝 海舟 1823-1899
江戸末期から明治初期の政治家。文政6年江戸本所に生まれる。名は義邦、通称麟太郎、号は海舟、後名を安房(あわ=安芳とも)と改める。旧旗本で、剣と読書を修め、とりわけ蘭学に秀でた。安政7年幕府から遣米使節が派遣されると咸臨丸の船長となり初めて太平洋を渡った。元治元年(1864)軍艦奉行となる。その後事実上の幕閣主席となり将軍慶喜(よしのぶ)を助けた。朝廷より江戸城攻撃の計があることを聞き、西郷隆盛と会談し江戸城を無血開城に導いた功績は広く知られている。維新後伯爵・枢密(すうみつ)院顧問官となり、明治32年1月没す。年77。「勝海舟全集」がある。
